粉砕モミガラ培地耕に適用可能な極微量多頻度潅水施肥法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
時間流量12L/hrの給水停止機構を備えたボタン型点滴潅水装置に、60の吐出孔を持つ点滴チューブを接続すれば、点滴孔当たりの時間流量0.2L/hrの極微量潅水同時施肥が可能となり、保水量が少なく、透水性の高い粉砕モミガラ培地でも養液栽培ができる。
- キーワード:有機質培地、粉砕モミガラ、多頻度潅水、極微量潅水
- 担当:近中四農研・中山間傾斜地域施設園芸チーム
- 連絡先:電話084-923-41000、電子メールwenarc-seika@affrc.go.jp
- 区分:近畿中国四国農業・生産環境、共通基盤・土壌肥料
- 分類:技術・参考
背景・ねらい
養液栽培で用いられているロックウールは、回収が義務付けられることから、ロックウールに替わる廃棄処理が可能で低コストな培地資材が求められている。有機質培地には、ヤシガラ、スギ皮、粉砕モミガラ等があるが、ヤシガラは輸入資材であり、品質にばらつきがある点、スギ皮は連年使用により、透水性が著しく低下する点、粉砕モミガラは保水力に乏しい等の欠点がある。保水力が乏しいという欠点は給液方法で解消可能と考えられることから、入手が簡単で、コストが最も安く、処分も楽な粉砕モミガラを培地とする肥培管理を可能とするため、極微量の養液を多頻度で給液する方法を確立する。
成果の内容・特徴
- 給液管内の水圧が0.06MPa以上では、時間流量12L/hrの一定量の給液を行い、水圧が0.03MPaに低下すると給液を停止する機構を備えたボタン型点滴装置を給液管に接続し、ボタン型点滴装置からの給液を60個の点滴孔(2次点滴孔)を持つ点滴チューブに分配すると、2次点滴孔の時間吐出量が0.2L/hrとなり、時間吐出量が2L./hrの通常点滴潅水に比べ、時間吐出量1/10の極微量潅水施肥が可能になる(図1)。
- 点滴孔間隔20cmの点滴チューブを12mまで延長しても、時間吐出量0.2L/hr、偏差5%以下の均一性の高い極微量潅水が可能となる。チューブ内の給液はボタン点滴装置の給液停止機構で、数時間は保持されることから、次の給液時には一斉に給液が開始され、多頻度潅水による給液ムラは生じない(図2)。
- コンテナに粉砕モミガラ(乾燥容積重:133g/L、24時間保水量18.6% w/v)を横38cm、縦58cm、深さ15cmに充填し、6株のトマトを定植した場合、培地内の含水率は2次点滴孔直下から離れるに従って低下するが、末端点滴孔から15cm離れた培地末端部でも最大保水量の50%程度の水分が保持され、培地全体へ水分が浸透する(図3)。
- 一日12回の潅水開始時刻を設定でき、潅水時刻になると、6つの電磁弁を設定時間だけ順番に開閉するタイマー式電磁弁制御装置を用い、一つの電磁弁を一つおきに3つの開閉制御接点に接続すると、設定時間の給液後、設定時間だけの給液停止を3回行い、最大36回/日の多頻度潅水を行える。極微量潅水法で、設定潅水時間を10分にすれば、33mL/点滴孔の給液を10分間隔で行う。潅水時間は1分単位で設定できる。
- トマト促成栽培で、朝7:00から、窒素400mg/Lの養液を株当たり0.025L給液し、その後は水のみを0.018L、3回、0.005L、21回給液する定量施用による肥培管理法を行えば、萎凋や尻腐れ等、水ストレスに起因する生理障害は認められない(図4)。
成果の活用面・留意点
- トマト3段摘心密植促成栽培(10月定植)の結果で、夏秋栽培、抑制栽培では施肥量・潅水量を変える。
- 2次点滴孔には高低差がないように設置する。
具体的データ
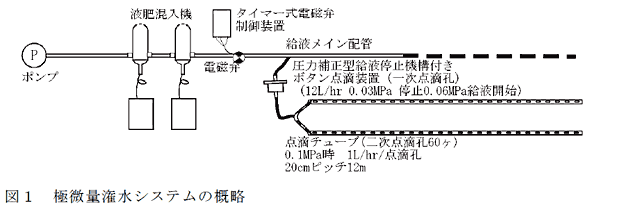
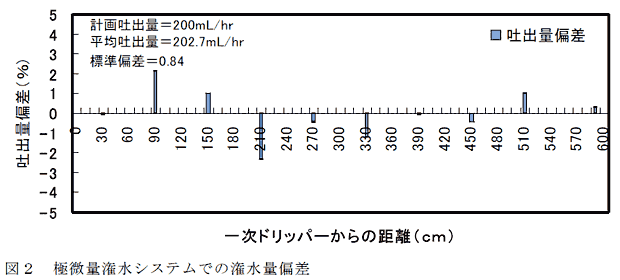
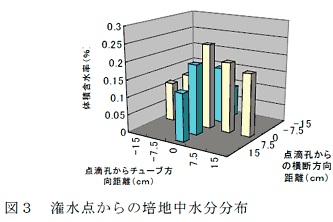

その他
- 研究課題名:標高差を活用した高付加価値生産技術体系のシステム化 ー有機質資材等を利用した環境保全型養液栽培技術の開発
- 課題ID:213-c
- 予算区分:傾斜地特性野菜
- 研究期間:2005~2006年度
- 研究担当者:吉川弘恭、渡邊修一、笠原賢明、東出忠桐、伊吹俊彦
- 発表論文等:吉川ら(2005)、日本における超低流速潅水システム発展の可能性 I、
超低流速潅水の進歩と現状、農及園、80(12)、1242-1248
