食育事業としての料理教室が食材や地場野菜のイメージを変える効果
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
食育を目的とした料理教室の開催は、参加者ほぼ全員の「食材」イメージを変える効果がある。一方「地場野菜」イメージを変える効果は食材よりも低いので、説明中心から体験中心の企画に変えることで地場野菜イメージを訴求していく方策が必要である。
- キーワード:食育、料理教室、食材、地場野菜、イメージ、ソシオグラム
- 担当:近中四農研・農業・農村のやすらぎ機能研究チーム
- 連絡先:電話084-923-4100
- 区分:近畿中国四国農業・営農
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
食育の普及啓発のため、食育基本法でも食育推進基本計画でも推奨している方式が料理教室である。行政が主催・補助し、「親子」 「キッズ」「米粉」「野菜」「くだもの」などを名称に冠して各地で開催されている。食育事業は、2006年度から本格的に展開されている。ここでは食育事 業の実施効果を把握し、事業の改善方策を提示する。
成果の内容・特徴
- 食育目的の料理教室は、講習・調理・試食というパターンに沿いつつも、「食育のための企画」を付加して、参加者の食意識を変 え、自らの食意識に基づいた食行動をとるように促すことが目的である。特に今回の料理教室の目的は、開催地である大阪産の野菜(以下、地場野菜)を食材に 使うことを参加者に明らかにし、地場野菜を活用して食意識を変えることにある(表1)。
- 食意識の変化を把握するために、料理教室受講後に「食材のイメージは変わりましたか?」とたずねたところ、変わった者は3回 平均で96.1%とほぼ全員にイメージの変化が認められる。一方、地場野菜イメージの変化は食材イメージの変化よりも低く、3回平均で73.6%である。 自ら調理したり、またその魅力を他の人に伝達するなどの食行動を高めるには、食意識、特に地場野菜イメージを向上させる方策が必要である(図1)。
- 「食材」「地場野菜」に対するイメージの変化は、具体的にどのような言葉で表現されるのかを料理教室受講後の感想文にもとづ き、単語の関係をソシオグラムで可視化すると、食材のイメージは「『コマツナ』を『生』で『食べる』と『おいしい』」というイメージが形成されている。こ れは、毎回調理の前に、講師が参加者に生の試食体験をうながしていたことが作用している。一方、地場野菜のイメージは「『野菜』は『おいしい』と『思 う』」という、単語数も修飾・被修飾も少ない弱いイメージが形成されている。「生」での試食のような体験的要素を企画に取り入れることで、食材イメージと 同程度のイメージ形成が期待できる(図2)。
- 図1に示すように「食育のための企画」は説明が中心である。これらの企画を図3に 例示する体験中心型に改善すると、「地場野菜」、「食事バランスガイド」、「栽培農家」について、参加者は自らの感覚を通じて強く印象づけられる。食意 識、特に地場野菜イメージが強くなれば、参加者の食行動は、コマツナやシュンギクといった特定の食材に対してではなく、地場野菜全体に対する内発的な食行 動へと展開される。
成果の活用面・留意点
- 料理教室は農水省「民間における食育活動促進支援事業」の助成を受け、(株)東果大阪が主催した。参加者はタウン誌で募集し、堺市と周辺に居住する主に20~60代の主婦が各回20数名、延べ80人が参加した。
- 調査法は、各回同じ質問によって回答者の変化をたどるパネル調査法である。
具体的データ
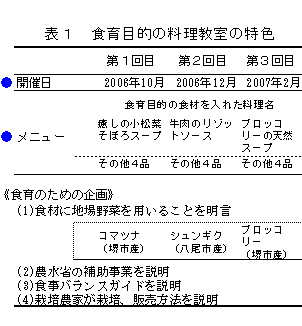
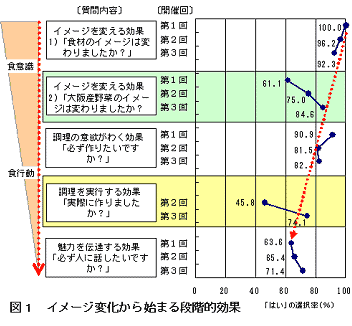
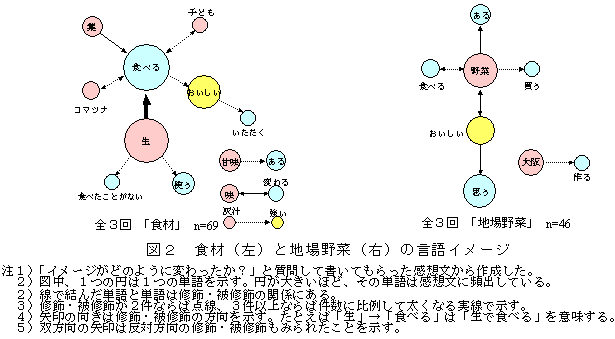
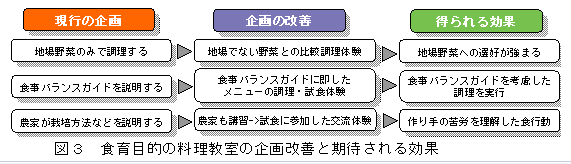
その他
- 研究課題名:農業・農村の持つやすらぎ機能や教育機能等の社会学的解明
- 課題ID:421-e
- 予算区分:基盤研究、依頼研究
- 研究期間:2006~2007年度
- 研究担当者:室岡順一
- 発表論文等:室岡順一・野崎壱子(2008)農村生活研究 51(2):9-21
