シバを植栽した畦畔法面の造成初期における植生の特徴
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
畦畔法面の造成年にはメヒシバの発生が多く、シバの被度の拡大と造成年のメヒシバの発生量には負の相関がある。シバの植栽によって造成2年目以降においてメヒシバの発生割合は減少する。
- キーワード:畦畔法面、シバ、メヒシバ、被度、植被率
- 担当:近中四農研・カバークロップ研究近中四サブチーム
- 連絡先:電話084-923-5343
- 区分:近畿中国四国農業・作物生産、共通基盤・作付体系・雑草
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
元来、シバはほふく茎によってマット状に生育し、草高が低いことを生育の特徴とし、これら特徴の利用は畦畔植生の群落の高さを低く維持し、草刈りをはじめとする畦畔管理の省力化に繋がることが期待される。
新たな畦畔が造成された場合、土壌の侵食回避のため植栽したシバの被度の拡大を主にして迅速な植被率の増加が望まれる。そこで、今回は畦畔法面の造成時に
おけるシバの植栽が、植被率、シバおよび雑草の発生草種毎のそれぞれの被度と草高に及ぼす影響を調査し、シバの被度の拡大に影響する雑草を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 植被率はシバの植栽の有無に関わらずほぼ同様に推移する。造成2年目及び3年目の5月では他の雑草の発生が少ないため、シバの植栽によって植被率は増加する(表1)。
- 群落の最大の高さはシバの植栽の有無に関わらず常に草刈りの目安となる30cm以上を示す。群落の平均の高さは造成2年目5月以降に30cmを上回ることはほとんど無いが、シバの植栽により造成2年目10月以降の群落の高さの平均は低くなる(表1)。
- 造成年ではシバの植栽の有無に関わらず他の雑草に比べてメヒシバの発生割合は大きい。シバの植栽によって造成2年目にメヒシバの発生割合は減少するが、シバの植栽が無い場合は造成2年目もメヒシバの発生割合は大きい(表2)。
- 造成2年目10月、3年目5月のシバの被度と造成年7月、10月のメヒシバの発生量には負の相関が認められ、造成年のメヒシバの発生量が多いとシバの被度の拡大が抑制される(表3)。
成果の活用面・留意点
- メヒシバは東北南部以南の畑地や畦畔における最も一般的な優占雑草のひとつである。畦畔法面を造成する場合、造成年の雑草防除の対象としてメヒシバを制御することで、迅速なシバの被度拡大が見込める。
- 本試験は栽培管理歴がカンショ栽培3年後1年休耕した近中四農研(福山市)の畑土壌・褐色森林土の圃場で、前植生を1ヶ月前にグリホサート剤で処理し、耕耘後にシバを植栽し、メヒシバが優占した畦畔で得られた結果である。
- シバ品種「朝駆」はほふく茎の伸長性に優れ、畦畔法面の迅速な被覆が期待できる。
具体的データ
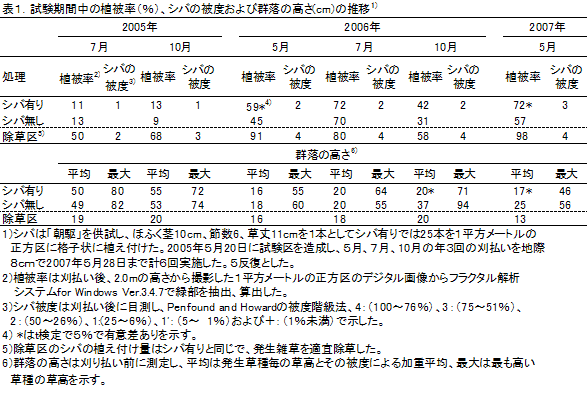
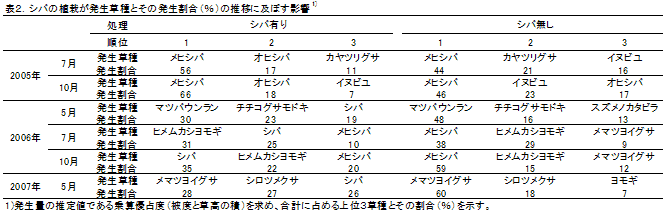
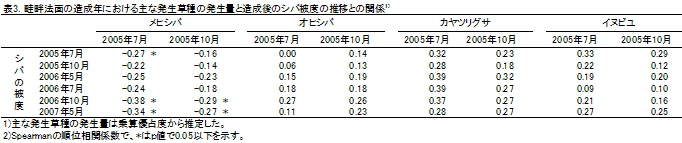
その他
- 研究課題名:カバークロップ等を活用した省資源・環境保全型栽培管理技術の開発
- 課題ID:214c
- 予算区分:基盤
- 研究期間:2006~2007年度
- 研究担当者:伏見昭秀、大谷一郎、亀井雅浩、奥野林太郎、窪田 潤
