農家行動のシミュレーションによる耕作放棄の発生条件と抑制策
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
農家は加齢や省力的な作物の価格低下等により耕作放棄する。抑制策としては、保全管理・作付面積に応じて補助金を支払うことが有効であり、60歳代で農地面積80aの場合、保全管理・作付面積に対して2,500円/10a支払えば耕作放棄を抑制できる。
- キーワード:耕作放棄、農産物価格、農家行動、農地保全意向、目標計画法
- 担当:近中四農研・地域営農・流通システム研究チーム
- 連絡先:電話084-923-4100
- 区分:近畿中国四国農業・営農
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
耕作放棄地が増加し問題となっている。農家の農地保全意向は強く、これが農家行動に影響していると考えられる。そこで、農家は農 地保全自体から効用を得ていると仮定して、効用関数を推定、かつ得られた効用関数を基にモデルを作成し、シミュレーションを行うことにより、各農産物価格 水準、経営規模、年齢について農家が耕作放棄する条件を定量的に明らかにする。さらに耕作放棄抑制策を検討する。
成果の内容・特徴
- 作成したモデルは、耕作放棄する可能性が高いと考えられる、集落営農・農作業委託等を行わず個別で独立した経営を行う高齢零 細な農家を想定した農家行動モデルである。その特徴は、1)目標計画法を適用する点、2)目的式に効用関数を用いる点、3)効用関数に保全管理面積と作付 面積を設定する点、4)年代毎に異なった技術係数を用いることで加齢による労働の質的低下を扱う点、5)パラメータを変化させ、モデルによる農地利用の再 現性から効用関数を推定する点の5点である(表1)。なお、中山間直払制度不参加、品目横断的経営安定対策導入以前、転作助成は転作割合4割超過分にも支払われることを想定する。
- シミュレーションから、農家は、強い農地保全意向を持つため、省力的な作物(事例では小麦)の作付けや保全管理を行い、耕作 放棄を回避する傾向にある。従って、省力的な作物・農地利用の導入・普及が重要である。しかしそれでも、現状の農産物価格水準において、比較的広い農地面 積を所有し、農地面積に対して労働力が不足する場合(60歳代で農地面積80a、70歳代で農地面積60a以上)に耕作放棄する。また、加齢によって(農 地面積60a以上で60歳代から70歳代へ)も耕作放棄する(表2)。
- 事例集落の平均農地面積を所有する農家において、米価が20%低下する場合、より省力的な作物があれば、その作付けを拡大するため、農家は耕作放棄しない。しかし、米価は現状水準でも、その省力的な作物の価格が低下する場合に、農家は耕作放棄する(表3)。従って、省力的な作物の収益性維持が重要である。
- 耕作放棄抑制策として、保全管理面積及び作付面積に応じて補助金を支払う(保全・作付補助)、作付面積に応じて補助金を支払う(作付補助)、経営外部の労働力を利用する(労働対策)の3対策の効果をみる(表4) と、中山間直払制度のように保全管理面積及び作付面積に応じて補助金を支払うことが、耕作放棄の抑制に有効である。例えば、60歳代で農地面積80aの場 合には2,500円/10aを、70歳代で農地面積80aの場合には6,500円/10aを支払えば耕作放棄を抑制できる(表4対象ケースB、C)。
成果の活用面・留意点
- 耕作放棄発生予測、耕作放棄対策を立案する際に、基礎的知見として活用できる。
- 岡山県中山間一集落の経営者が60歳以上の農家7戸に対する調査に基づきモデルを作成している。シミュレーション結果は作目構成等によって異なる。各地域において耕作放棄対策を立案する際には、それぞれの状況に応じた検討が必要である。
具体的データ
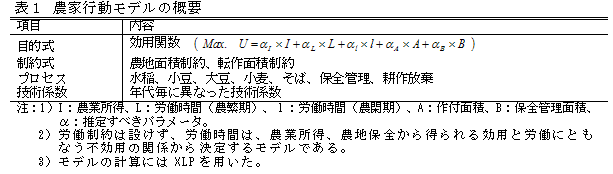
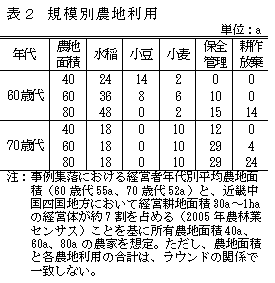
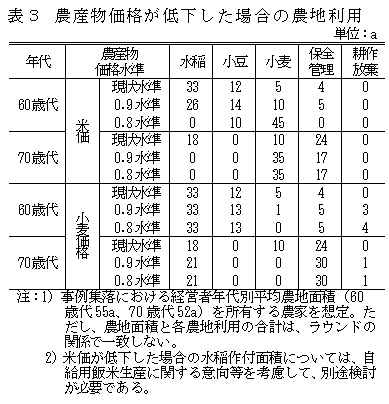
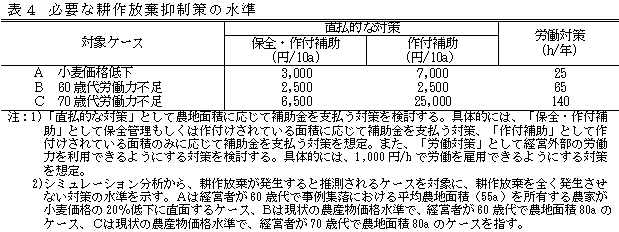
その他
- 研究課題名:地域の条件を活かした水田・畑輪作を主体とする農業経営の発展方式の解明
- 課題ID:211-a
- 予算区分:基盤
- 研究期間:2006~2007年度
- 研究担当者:吉田晋一、棚田光雄
- 発表論文等:吉田ら(2007)農林業問題研究43(1):25-30
