飼料用稲の生産と利用による集落営農連携型耕畜連携営農モデルの策定
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
集落営農組織が中心となり、自ら飼料用稲を栽培し、他からの受託を含め15ha程度の収穫作業を担う営農モデルである。集落営農推進の政策と現場ニーズに合致し、生産面・経営管理面での優位性も発揮できる。畜産部門との信頼関係の構築が重要となる。
- キーワード:耕畜連携、飼料用稲、稲発酵粗飼料、WCS、集落営農、水田転作
- 担当:近中四農研・中山間耕畜連携・水田輪作研究チーム
- 連絡先:電話084-923-4100
- 区分:近畿中国四国農業・営農、共通基盤・総合研究(飼料イネ)
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
中山間地域の多くで水田農業の担い手不足が深刻化しているが、有力な対処方法として集落営農への期待が高い。こうした集落営農 (組織)が飼料用稲生産に取り組む場合、専用収穫機の経済的な利用規模(15~20ha程度)を単独組織で確保するのは難しいことから、複数の集落組織が 連携して飼料用稲を作付け、生産した稲発酵粗飼料(WCS)を周辺の畜産農家に販売する耕畜連携を地域営農システムの一方式として想定することができる。 その普及定着を図るためには、地域体制像を描き、設立運営の課題等を整理し、各主体とシステム全体の経済性を明示する必要がある。
成果の内容・特徴
- 複数の集落営農組織が連携して耕畜連携に取り組んでいる実践事例の実態把握と分析に基づき、組織体制を営農モデルとして整理する(図1)。 中心となる法人Aは飼料用稲の栽培を行い、収穫機を所有し、作業受託分と合わせて15haの収穫調製作業を行う。法人Bは飼料用稲を栽培し、収穫調製作業 をAに委託する。地域が異なるため生産したWCSは各々の組織で畜産経営に販売する。畜産側にとってWCSは地域内産ではあるが購入飼料の一つと位置づけ られる。堆肥の積極的な還元利用を行う。
- 営農モデルの特徴と留意点を表1に 示す。集落営農組織による生産活動は中山間水田営農の振興方策として行政等の支援を得やすい。生産単位の拡大と経営管理の一元化、水稲作との一体的な管理 作業などで生産の合理化やコストの削減が可能となる。飼料用稲生産の収益性は転作助成金の水準に依存しているため限界はあるが、転作対応の手段と安定的収 入源として組織運営の安定化に寄与し、また、集落営農組織の重要な設立動機である農地資源の保全と地域社会の維持にはよく適合する。
- 集落営農組織は畜産側との信頼関係構築に努める必要がある。WCS品質の安定化を図るため特に収穫調製・運搬の作業の適正化に留意し、情報交換と交流の場を設ける。
- 15ha規模の営農モデルの経済性について目安の指標を表2に 示す。A法人10ha(購入苗移植)、B法人5ha(鉄コーティング散播)の作付け、転作助成6万円/10aとする。労賃差し引き後の栽培過程のA法人の 余剰(構成員への地代配当と内部留保の原資)は1.25万円/10a、A法人の全所得(個人配分+法人余剰)は427万円となる。この収益は集落営農間連 携によって初めて可能となった点に着目する必要がある。
成果の活用面・留意点
- この営農モデルは水田率の高い地帯で集落営農を推進する場合に適用可能である。耕畜間の関係を形成する取り組みの初期段階では関係機関の役割が重要となる。
- 経済性のデータは事例分析や統計に基づく目安の値である。畜産側の経済性は金額のみを示したが、品質や取扱い適性も考慮する必要がある。集落営農の収益配分が労働重視型か地代重視型かで具体的な配分内容は異なる。
- モデルは飼料用稲への助成を前提としたものである。他の形態の営農モデル、助成金や技術水準等の条件が変化した場合の影響など、詳しい情報は刊行予定の「飼料用稲の生産・利用による耕畜連携へ向けて(成果マニュアル)」を参考とされたい。
具体的データ
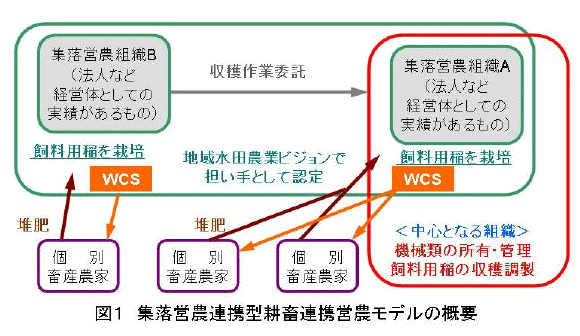
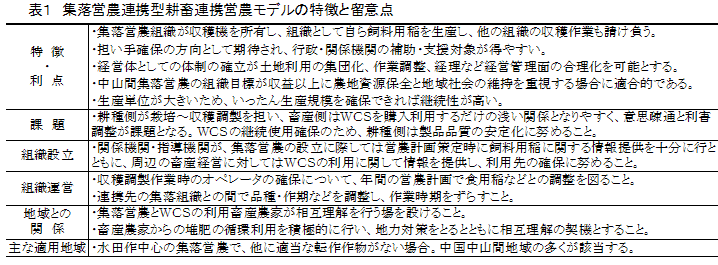
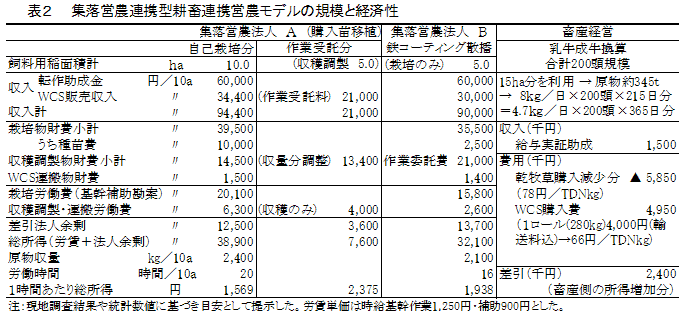
その他
- 研究課題名:近畿・中国・四国地域における中小規模水田利用システムの開発
- 課題ID:212-b
- 予算区分:中山間耕畜連携
- 研究期間:2006~2007年度
- 研究担当者:恒川磯雄(中央農研)、堀江達哉、井上憲一(島根大)、棚田光雄、加藤克明
