イチゴに対する緑色蛍光灯終夜照明の影響の品種間差異
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ヤガ類防除を目的とする緑色蛍光灯の終夜照明は、従来の黄色蛍光灯に比較してイチゴの花房出蕾への悪影響が同等または小さい。品種ごとに緑色蛍光灯の光強度に対する感受性が異なり、「さがほのか」、「とちおとめ」に比べて「さちのか」は光強度が低くても出蕾が遅れやすい。
- キーワード:イチゴ、緑色蛍光灯、黄色蛍光灯、花芽分化、防蛾灯
- 担当:近中四農研・環境保全型野菜研究チーム
- 代表連絡先:電話084-923-4100
- 区分:近畿中国四国農業・野菜
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
黄色灯の終夜照明は、害虫であるヤガ類防除に有効であるが、日長反応性を有する作物では生産上不利な影響を及ぼす場合があり限定的な利用に留まっている。これに対して近年、植物の日長感応に関与するフィトクロムが主に吸収する600 nm以上の赤色光域をほとんど含まない緑色蛍光灯が、防除効果を保持しつつ植物への光影響が小さいとして、その利用が提案されている(図1)。しかし、短日植物であるイチゴでの研究事例はまだ少なく情報が不足している。そこで近畿中国四国地域での主要5品種「章姫」「さがほのか」「さちのか」「とちおとめ」「紅ほっぺ」について、黄色蛍光灯による影響と比較して緑色蛍光灯の終夜照明による影響を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 短日夜冷処理によって頂花房の花芽を分化させた苗を定植し、その後に緑色あるいは黄色蛍光灯により光強度0~0.1 μmol/ m2/sで終夜照明すると、「さがほのか」、「とちおとめ」では一次腋花房の出蕾日に与える光質、光強度の影響は小さい。これら品種の二次腋花房の出蕾は、0.08 μmol/ m2/s(照度に換算すると緑色蛍光灯では10 lx、黄色蛍光灯では8 lx)以上では光質に関わらず数日から10日程度遅れる傾向がある(図2)。
- 「章姫」、「紅ほっぺ」の一次および二次腋花房の出蕾は、両光質とも光強度が大きくなるにつれて遅延する傾向がある。光強度が0.08 μmol/ m2/s以上の場合に明確に遅延する。光源として緑色および黄色蛍光灯を用いた場合、両者の差は大きくない(図2)。
- 「さちのか」は一次および二次腋花房出蕾日が他品種より遅く、終夜照明の光質、光強度の影響が最も大きい。一次腋花房において緑色蛍光灯下では0.06 μmol/ m2/s以上で出蕾が遅延するのに対して、黄色蛍光灯下では0.02 μmol/ m2/sの光強度でも出蕾が遅延する。二次腋花房では、両光質とも、低い光強度でも照明なしの場合に比べ出蕾が遅延するが、黄色蛍光灯下で光強度が高くなるほど遅延日数が大きくなる(図2)。
- 葉柄長、葉身、葉幅は、品種によらず光強度が高くなるほど伸長するが、緑色蛍光灯下の方が黄色蛍光灯下より影響が小さく、草姿が維持しやすい(データ略)。
成果の活用面・留意点
- 既成果として「福岡S6号(商標名:あまおう)」に関しては、緑色蛍光灯の終夜照明では成長や花芽分化に及ぼす影響は黄色蛍光灯に比べ小さい(平成18年度九州沖縄農業研究成果情報)との報告がある。
- 光強度は、プランタあたりの平均水平面強度をもって示している。
- 植物体への光照射であることを踏まえ、光の強さを示す単位は光合成有効光量子束密度(PPFD、μmol/ m2/s)を中心に記載している。照度(lx)との対応は図2の数値を参照。
具体的データ
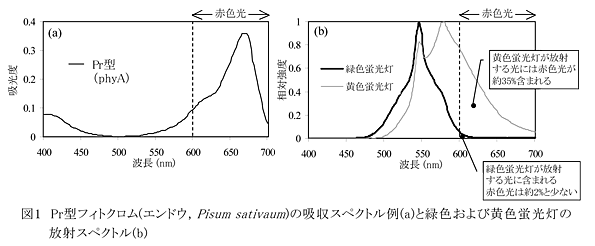
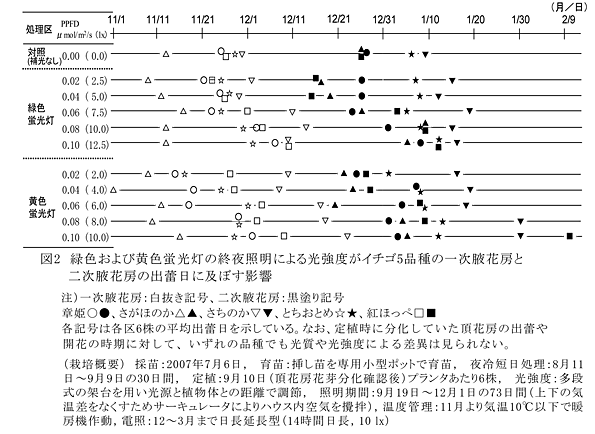
その他
- 研究課題名:中山間・傾斜地における環境調和型野菜花き生産技術の開発
- 課題ID:214-u
- 予算区分:基盤
- 研究期間:2007年度
- 研究担当者:山崎敬亮、熊倉裕史、山田真(パナソニック電工(株))、石渡正紀(パナソニック電工(株))
