細菌群集構造解析のための植物根からの迅速かつ簡便なDNA抽出法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
植物根からのDNA抽出法として、ガラスビーズで細胞破砕を行うビーズ法は、従来のCTAB法に比べて迅速かつ簡便、市販キットに比べて安価な手法である。抽出されたDNAは植物根の細菌群集構造を明らかにするための細菌の16S rDNAのPCR-DGGE解析に供試可能である。
- キーワード:DNA抽出、植物根、16S rDNA、PCR-DGGE、細菌群集構造解析
- 担当:近中四農研・環境保全型野菜研究チーム
- 代表連絡先:電話084-923-4100
- 区分:近畿中国四国農業・生産環境(土壌)
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
植物根圏・根面の微生物群集構造は、非根圏土壌とは大きく異なり、植物生育の促進や抑制および病原微生物の植物体内への侵入について関与することが知られている。これらの機構解明や土壌病害拮抗菌の植物根面への定着程度を評価するために、DNA解析による植物根の微生物群集構造解析が行われている。植物根からのDNA抽出法は、これまで臭化セチルトリメチルアンモニウム(CTAB)を用いるCTAB法が一般的に用いられてきたが、CTAB法は時間や手間がかかる。近年DNA抽出には、ガラスビーズで細胞を破砕する方法(以下、ビーズ法)が用いられるようになり、ビーズ法は市販のDNA抽出キットにも取り入れられている。しかし、DNA抽出キットの価格は1サンプルにつき約500~1,300円と非常に高く,多数のサンプルを扱う場合には経済的な負担が大きい。そこで、DNA抽出キットを使わずに、一般的なビーズ法で植物根からDNAを抽出する方法を検討する。この抽出法が、CTAB法やDNA抽出キットと比較して、植物根からの迅速かつ簡便、安価なDNA抽出法として適当であるか、また抽出されたDNAが細菌の16S rDNAのPCR-DGGE(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)解析に供試可能かどうかを検討する。
成果の内容・特徴
- ビーズ法の作業フローを図1に示す。6サンプルの抽出を行う場合の作業時間は、CTAB法は3時間半、ビーズ法は1時間半程度で、ビーズ法はCTAB法に比べて、植物根から迅速かつ簡便にDNAを抽出することができる手法である。
- 抽出DNA量はビーズ法に供試する根の量が多いほど増加する(図2)。また、細菌の16S rDNAのPCR-DGGE解析によって得られたDGGEパターンは、ビーズ法に根を直接0.1~0.2g供試した場合および多量の根のホモジナイズ処理液の一部を用いた場合でも違いは認められない(データ略)。根を約5mmの長さに切断し、よく混合すれば、供試する根の量が0.2gと少量でも十分DNAは抽出され、その根のDNAの代表サンプルとして細菌の16S rDNAのPCR-DGGE解析に供試可能である。
- ビーズ法,CTAB法,ビーズ法を用いたDNA抽出キットの3種類のDNA抽出法のうち、抽出DNA量が最も多いのはビーズ法である(図3)。DGGEパターンは、ビーズ法およびDNA抽出キットを用いた場合ではほぼ同一である(図4)。これら2つに比べて、CTAB法を用いた場合、DGGEゲル上で同じ泳動距離のDGGEバンドの濃度が薄くなる場合がある(図4矢印)。
- ビーズ法では、キットと同仕様の試薬や消耗品類の価格は1サンプル約70円である。価格,作業時間,実験操作や試薬作製の手間等を考え合わせると,細菌群集構造解析のための植物根からのDNA抽出法として,ビーズ法がCTAB法やDNA抽出キットに比べて優れているといえる。
成果の活用面・留意点
- 本研究成果で用いた植物根はトマトのものであるが、ホウレンソウ等の軟弱野菜類の根でもビーズ法を適用できることを確認している。また、PCR増幅用プライマーは、細菌の16S rDNAのV6-V8可変領域を標的とするプライマーセット(F985GC,R1384)を用いている。
- 研究機関において、植物根の細菌群集構造解析に活用できる。
具体的データ
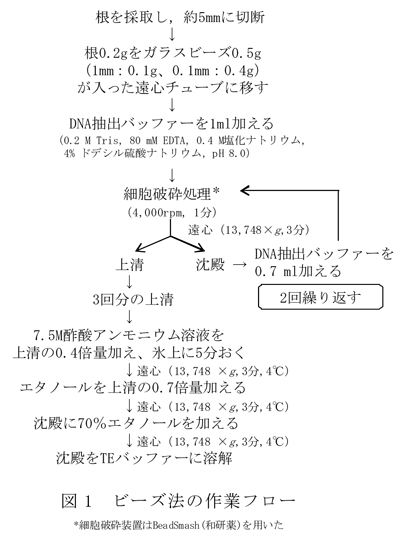
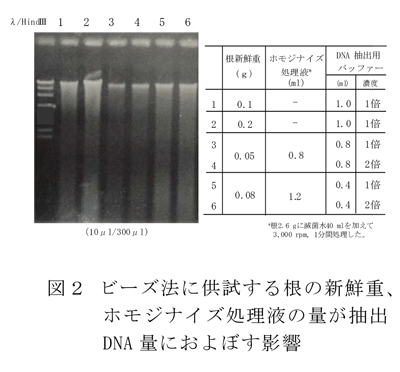
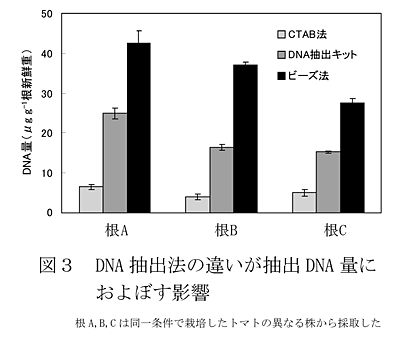
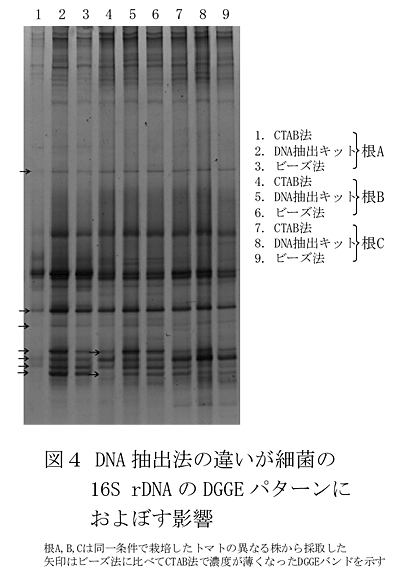
その他
- 研究課題名:中山間・傾斜地における環境調和型野菜花き生産技術の開発
- 課題ID:214-u
- 予算区分:委託プロ(実用技術)、基盤
- 研究期間:2005~2007年度
- 研究担当者:須賀有子、堀兼明、小森冴香、福永亜矢子、池田順一、豊田剛己(東京農工大)
- 発表論文等:須賀ら(2008)土と微生物、62(2):121-125
