チョウの食草オミナエシを保全するススキ型草地の管理技術
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
ススキ型草地において、ウスイロヒョウモンモドキの食草であるオミナエシを保全する管理方策としては、6月に採草し、刈り取った草を搬出する方法が望ましい。また、長期的にみれば放牧は不利なことが示唆される。
- キーワード:オミナエシ、採草、放牧、半自然草地、植生
- 担当:近中四農研・粗飼料多給型高品質牛肉研究チーム、草地多面的機能研究チーム
- 代表連絡先:電話0854-82-0144
- 区分:近畿中国四国農業・畜産草地
- 分類:行政・参考
背景・ねらい
ウスイロヒョウモンモドキ(Melitaea protomedia Menetries)は、オミナエシ科の植物を食草とする草原性のチョウで、環境省のレッドデータブックに記載されている絶滅危惧種である。全国的に個体群や生息地が失われつつある中、島根県三瓶山地域のススキ型草地は同県下で唯一の生息地であり、当地におけるこのチョウの保護は重要な問題である。しかし、近年の過放牧や管理放棄に伴う生息地(ススキ型草地)の減少により、その個体群は衰退しつつある。そこで、その保全策の確立に資するため、ススキ型草地での管理条件(採草、放牧)がこのチョウの食草である草原性植物オミナエシ(Patrinia scabiosaefolia Fisch.)の生育に及ぼす影響を解明する。
成果の内容・特徴
- 年1回,10月に刈取り管理されてきたススキ草地に、1ha当たり1頭の放牧強度で3年間放牧を繰り返した結果、ススキ型草地に自生するオミナエシの出現個体数ならびに草地群落の出現植物種数、多様度指数への放牧による顕著な悪影響は認められない(表1、図1)。しかし、オミナエシの花序数は放牧処理により減少し、無放牧である対照区(10月1回刈り)の約60%にまで低下する(図1)。
- 20年以上にわたり放牧を繰り返すと、植生はススキ型草地からシバ型草地へと変化し、ここではオミナエシの個体はほぼ消失する(表1)。また、出現植物種数や多様度指数も極めて低い水準にとどまる(表1)。
- 刈取条件下における出現植物種数とオミナエシの個体数は、6月刈り区(6月と10月刈り)で最も多く、8月刈り区(8月と10月刈り)がそれに続き、対照区(10月1回刈り)に最も少なくなる傾向が認められる(表2、図2)。また、刈り取った草を除去(収穫・搬出)することによりオミナエシ個体数や出現植物種数が高まる傾向にある(表2、図2)。
- 優占種であるススキの被度は、6月刈り区と8月刈り区で低く、とくに6月刈りによるススキのダメージが顕著に認められ、地上部合計現存量の体積近似値(PVI)にも同様の傾向が認められる(表2)。
- 以上の点から、慣行の10月刈りに加えて、オミナエシが伸長する前の6月頃に刈取りを行うことで、優占種であるススキ等の優占度が低下し、オミナエシなどの随伴種の生育環境が改善されるものと考えられる。また、放牧は優占種であるススキを抑制する効果はあるものの、オミナエシの花序数を減少させるので、長期的にみればオミナエシの保全には不利なことが示唆される。
成果の活用面・留意点
- ウスイロヒョウモンモドキの生息する、あるいはオミナエシの生育する半自然草地を保全管理する上での基礎資料となる。
- 本成果は、試験処理としての撹乱要因が加わった状態での結果であり、今後、同一の管理条件下(無刈取り条件など)での検証が必要である。
- 緩やかな季節放牧や休閑を組み合わせた放牧による植生管理については未検討である。
具体的データ
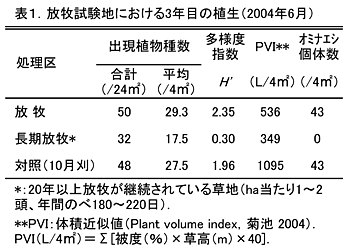
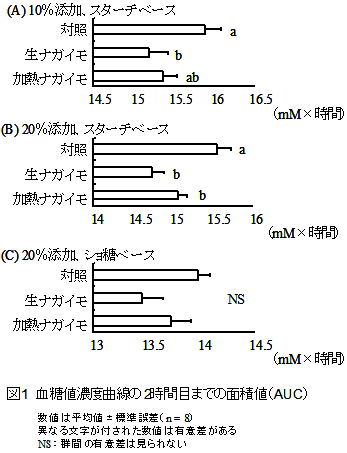
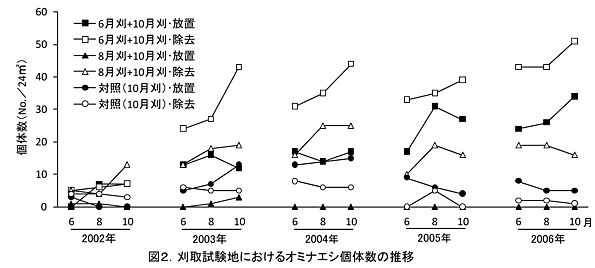
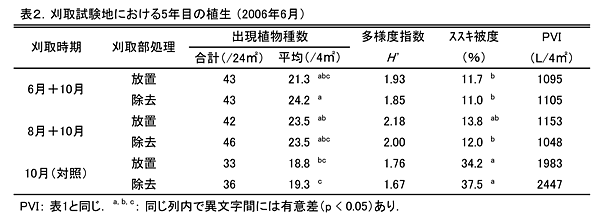
その他
- 研究課題名:草地生態系の持つ多面的機能の解明
- 課題ID:421-b
- 予算区分:基盤、所特定、科研費、委託(島根県)
- 研究期間:2002~2006年度
- 研究担当者:高橋佳孝、井上雅仁(三瓶自然館)、黄 双全(武漢大)、井出保行、小林英和
- 発表論文等:1)高橋ら(2008)島根県立三瓶自然館研究報、6: 1-6
