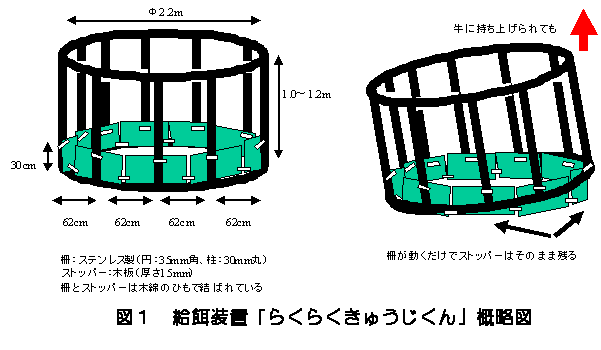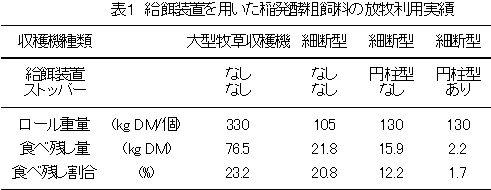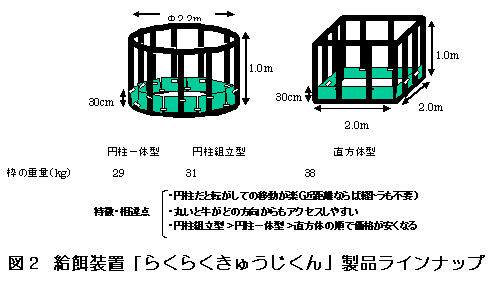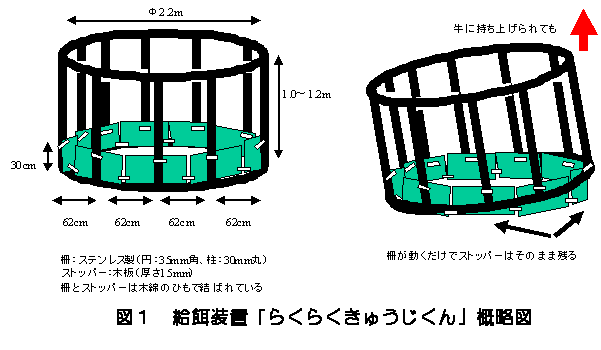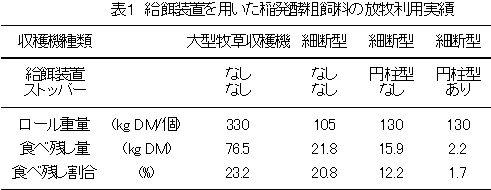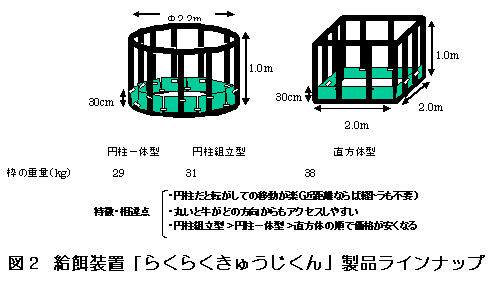研究の社会的背景と技術開発の経緯
1.水田で生産される飼料の利用を推進する上での課題
水田の有効活用、飼料自給率の向上、家畜飼養の省力化を実現するため、水田で栽培可能な飼料イネや牧草の作付け、稲発酵粗飼料の利用、牧草の放牧 利用が推進されています。しかし、高水分の稲発酵粗飼料は畜舎への運搬や家畜への給与作業の負担が大きいばかりでなく、運搬の際の燃料使用量が多く環境面 からも課題を抱えています。他方、牧草に依存した季節放牧では冬季はすべての家畜を舎飼いにせざるを得ないため、頭数を増やせないなど経営改善効果は限ら れます。
2.飼料イネを利用した水田周年放牧モデルの開発
そこで、水田で生産される飼料の効率的な利用と畜産経営の発展を図るため、水田放牧向きの牧草や飼料イネ、稲発酵粗飼料を組み合わせて、1頭あた り40aの水田で繁殖和牛を周年放牧飼養可能なモデルを茨城県常総市において開発してきました。このモデルでは、冬季飼料として稲発酵粗飼料を飼料イネ生 産ほ場や放牧地で放牧給与しますが、簡便な給餌方法や食べ残しの削減が課題でした。
研究の内容
1.給餌装置の概要
「いつでも、どこでも、誰にでも」をコンセプトに、人力で移動可能な軽量(最軽量タイプの重量29kg)の給餌装置「らくらくきゅうじくん」(図1)を開発しました。
家畜への給餌の際には、「らくらくきゅうじくん」を飼料ロールベールの上から被せて使用します。給餌の際に牛の力で給餌装置は簡単に動きますが、 むしろ動くことで給餌装置への物理的衝撃を緩和します。また、牛の力で簡単に持ち上がる給餌装置の場合、持ち上げられた下の隙間から細断されている飼料が 給餌装置の外にこぼれ出てしまいます。そこで、給餌装置の下方に可動式のストッパーを付けて飼料の漏出を削減しました(写真1)。
2.給餌装置導入の効果
「らくらくきゅうじくん」はロールベールの周りを囲うことにより、食べ散らかしや排せつ物の汚染等による飼料の食べ残しを減らすことができます。 給餌装置を用いずに飼料ロールベールをほ場で給与すると、20%以上の食べ残し量が発生します。給餌装置を用いると食べ残し量は、細断型ロールベールで約 12%に低減します。さらにストッパーを利用すると細断型ロールベールの食べ残し量は約2%に低減します(表1)。
収穫した飼料をその場でロールベールにした後、ほ場に適切に配置して給餌することで、飼料の運搬および家畜排せつ物処理作業が軽減できます。その 結果、堆肥の運搬作業まで軽減されます。また、「らくらくきゅうじくん」は軽量で給餌作業の軽労化も図れるため、「らくらくきゅうじくん」を動かせる方な らどなたでも(女性、お年寄り、子供を含む)給餌作業に携われます。
さらに、「らくらくきゅうじくん」を用いれば、放牧に興味がある農家や放牧初心者の農家が餌不足を心配することなしに放牧を導入できます。また、 ロールベールを搬入時に適切に配置することで牧草量が不足する晩秋から早春でもほ場で牛を飼養できるため、周年屋外飼養が可能になります。「らくらくきゅ うじくん」は導入コストが低いため、はじめて放牧する牛を放牧環境へ慣れさせる等、様々な畜産場面での活用が考えられます。
なお、申請中の特許を含むこの技術は、農林水産大臣認定TLOを通じて(株)大成工機に供与しており、本装置は(株)大成工機(茨城県つくば市)から複数の形状のラインナップでテスト販売されます(図2)。
今後の予定・期待
今後は稲発酵粗飼料生産の盛んな水田地帯において、中山間地域の畜産農家の牛を預かり、稲発酵粗飼料と牧草を用いた冬春放牧モデルの開発等を行う予定です。これらのモデルと合わせ、今回開発した給餌装置が普及することで周年放牧利用の拡大に貢献することが期待されます。
用語の解説
- ロールベール
- ロールベールラップサイロとも言う。円筒状(タイコ形)に梱包した牧草、飼料イネ、トウモロコシ等をラップしてサイレージ化する手段。牧草を大型機械で直径2m程度の円筒形に整形、ポリエチレンでできた幅広のラップで巻き上げて仕上げる。
- 稲発酵粗飼料
- イネの子実が完熟する前に、子実と茎葉を一体的に収穫・密封し、ロールベールなどの嫌気的条件のもとで発酵させた貯蔵飼料。近年、作物が作付けされていない水田の有効活用と飼料自給率の向上に資する飼料生産の形態として注目されている。
- 周年放牧
- ロールベール等の長期保存が可能な飼料や牧区の利用を一部中止することで牧草等を生育させて冬場のエサとして備蓄し、12月以降の冬季も放牧 地で家畜を越冬させ、一年を通じて放牧地で家畜を使用する技術。この技術が確立する以前は冬季になる前に放牧地から引き上げ、畜舎で越冬させていた。
参考データ