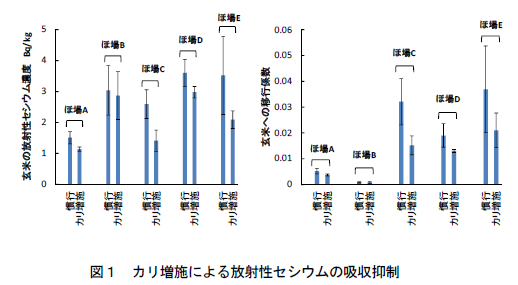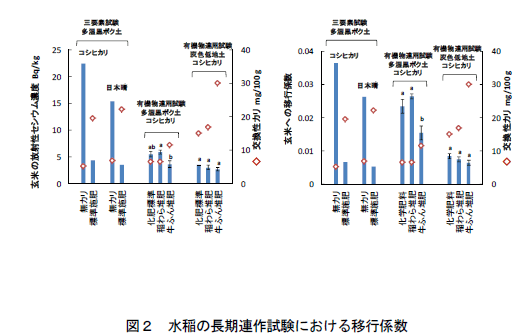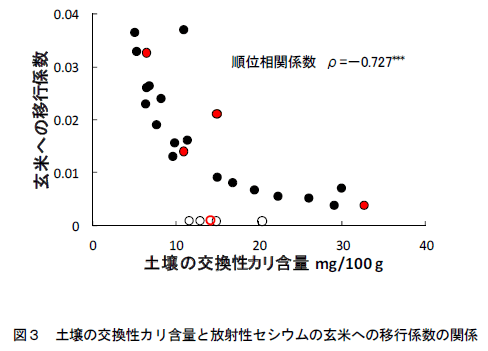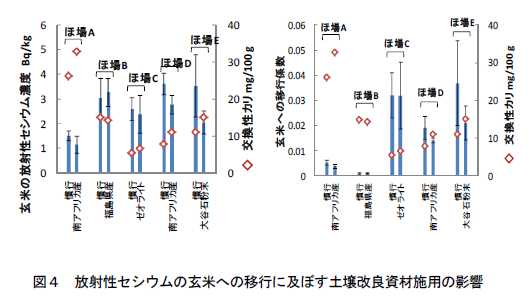背景
東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、平成23年産米において広範囲で放射性セシウムが検出されました。食品の摂取による内部被曝を低
減するため、特に主食である米の放射性セシウム濃度の低減は急務であり、生産者が容易に取り組める対策技術を早期に示す必要があります。
経緯
中央農業総合研究センターが中核となり、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の各試験研究機関と連携し、カリの施用量を地域慣行施肥の3倍とした試験区
を共通的に設置し、水稲のほ場栽培試験を行いました。また、各研究機関で一定の施肥条件で長年にわたり維持・管理している水田ほ場(長期連作試験ほ場)に
おいても水稲の栽培試験を行いました。これらの栽培試験において、土壌と玄米の放射性セシウム濃度を調査し、土壌の交換性カリ含量と放射性セシウムの玄米
への移行係数との関係を解析しました。玄米試料中の放射性セシウム濃度の測定は(独)農業環境技術研究所が行いました。
内容・意義
カリ増施による玄米中放射性セシウム濃度の低下
粘土鉱物としてバーミキュライトを多く含み放射性セシウムの移行係数が低い土壌(圃場B)を除き、カリを慣行施肥の3倍施用すると、玄米の放射性セシウム濃度や移行係数が低下しました(図1)。
長期連作試験ほ場を活用した調査
化学肥料に加えて牛ふん堆肥を長年にわたり施用した土壌は、化学肥料のみを施用した土壌に比べて、交換性カリ含量が高く、玄米の放射性セシウム濃度
や移行係数が低くなりました(図2)。また、三要素試験ほ場において、長年にわたりカリを施用していない土壌では、施用した土壌に比べて玄米の放射性セシ
ウム濃度や移行係数が高いことがわかりました(図2)。
土壌の交換性カリと放射性セシウムの玄米への移行係数の関係
各ほ場試験の結果から、土壌の交換性カリ含量が高いほど、玄米への移行係数が低下することが示されました(図3)。また、交換性カリ含量を25
mg/100
g以上としても低減効果は小さいことが明らかになりました。水稲の健全な生育には、カルシウムやマグネシウム等、他の養分とのバランスも考慮する必要があ
るため、玄米中の放射性セシウム低減対策として、交換性カリ含量25 mg/100 gを目標とした土壌改良が推奨されます。
土壌改良資材等の施用と放射性セシウムの玄米への移行係数の関係
産地の異なる2種のバーミキュライトとゼオライト(市販品)(各々500 kg/10 a施用)およびゼオライト含有資材(大谷石粉末、1
t/10
a)について検討しました。玄米の放射性セシウム濃度や移行係数に低下傾向が認められる事例もありましたが、統計的有意差は得られませんでした。また、低
減傾向が認められた事例では、栽培後土壌の交換性カリが無施用に比べて高く(図4)、資材に含まれていたカリが移行係数に影響を及ぼした可能性があります
(図3、赤のプロット)。これらの資材による放射性セシウムの吸収抑制効果は、資材の鉱物組成や土壌特性によって異なることも考えられるため、効率的な施
用条件や方法についてはさらに検討が必要です。
留意点
従来の水田土壌における交換性カリの目標値は、地域によって多少異なりますが、黒ボク土で30 mg/100
g程度、非黒ボク土(砂質土を除く)で20~30 mg/100 g程度、砂質土で15~20 mg/100
g程度であり、今回示した目標値はこれらと比べて大きくは違いません。土壌診断を実施して、交換性カリ含量が低い場合には、25 mg/100
g程度を目標に土壌改良を実施した上で、地域慣行の施肥を行ってください。
今後の予定・期待
放射性セシウムの移行係数は、交換性カリ含量だけではなく、土壌の粒径組成や粘土鉱物組成によって異なることが知られていますので、このような土壌
特性に対応したカリ施肥法の策定に取り組む予定です。また、移行係数の経年的変化を追跡調査するとともに、他の作物についても土壌特性と移行係数との関係
を解析します。
用語の解説
カリ
カリウムは、植物の肥料要素の1つで、主にイオンの形で植物に吸収され、植物体内の糖類やタンパク質の生成、浸透圧の維持調節、細胞内のpH調整などに関与している。
肥料成分として示すため、元素名の「カリウム」ではなく、「カリ」と表記し、酸化物(K2O)としての重量を表示した。
交換性カリ
土壌の腐植や粘土表面のマイナス荷電に吸着されているカリウムで、他の陽イオン(カルシウム、マグネシウム、アンモニウムなど)によって容易に交換
されて土壌溶液中に溶出し、作物に吸収されやすい。土壌のカリウム供給力を示す指標として、土壌診断で一般的に使用されている。乾土100
g当たりのカリ含量で表す。
放射性セシウム濃度
セシウム134の濃度(Bq/kg)とセシウム137の濃度(Bq/kg)の合計値。
粘土鉱物
風化作用により生成した土壌中の鉱物。その種類と含量は土壌の養水分の保持能などの性質を大きく左右する。結晶性粘土として、カオリナイト、スメク
タイト、イライト、バーミキュライト、クロライトなどがあり、非結晶性粘土としてはアロフェン、イモゴライトがある。イライトやバーミキュライトは放射性
セシウムを吸着・固定する能力が高いので、これらの粘土鉱物を多く含む土壌では移行係数が低くなることが知られている。
移行係数
土壌の放射性セシウム濃度に対する植物体の放射性セシウム濃度の比。ここでは、玄米の放射性セシウム濃度(Bq/kg、水分15 %換算)を土壌の放射性セシウム濃度(Bq/kg乾土)で除して求めた。
三要素試験
作物の代表的な養分である窒素、リン酸、カリについて、それらを欠如した場合の生育・収量、土壌の理化学性に対する影響を長期的に調査する栽培試験。
土壌の粒径組成
土壌の無機質粒子を粒径別に粗砂(2.0~0.2 mm)、細砂(0.2~0.02 mm)、シルト(0.02~0.002
mm)、粘土(0.002
mm未満)に区分し、それらの重量割合を示したもの。「土性」とも呼ばれ土壌の肥沃度や水分保持など様々な性質に深くかかわっている。
順位相関係数
二つの変量のそれぞれの順位の一致度を表す指標。図3では、土壌の交換性カリ含量で順番を決めた場合と、玄米への移行係数で順番を決めた場合で、ど
れくらい順番に一致性が認められるかを示している。両方の場合で順位が完全に一致していると順位相関係数は1となり、完全に逆であれば-1となる。
参考データ
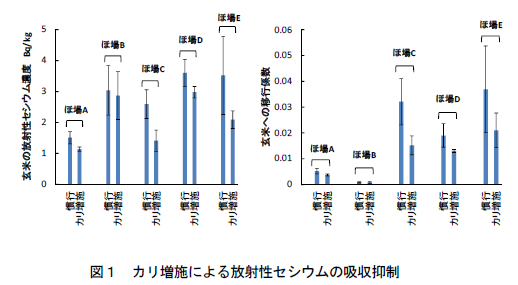
カリ増施は、カリの基肥と追肥がともに慣行の3倍量。ただし、ほ場Eは基肥のみ3倍量。ほ場AとB:灰色低地土、C:低地水田土(造成)、DとE:
多湿黒ボク土。土壌(栽培後)の放射性セシウム濃度(Bq/kg):A;300、B;3680、C;90、D;210、E;100。品種はすべてコシヒカ
リ。エラーバーは標準偏差。圃場ごとでは慣行とカリ増施との間に有意差はなかったが、試験全体では1%水準で有意差有り。
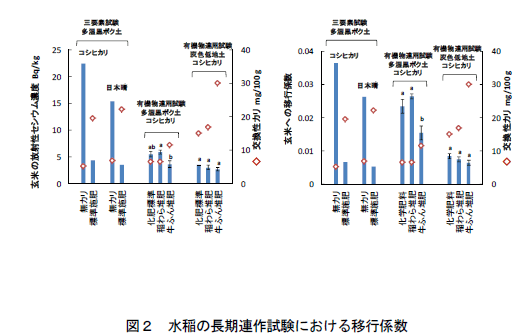
三要素試験は30年間、有機物連用試験は多湿黒ボク土で39年間、灰色低地土で33年間、それぞれの施肥処理を継続した長期ほ場試験。
稲わら堆肥600 kg/10 a、牛ふん堆肥は多湿黒ボク土で1.2 t/10 a、灰色低地土で2 t/10
a連用。交換性カリは栽培後の土壌の数値。三要素試験;1反復、有機物連用圃;2反復。エラーバーは標準偏差。有機物連用試験の土壌ごとに同一アルファ
ベットが付されていない処理区の間には5%水準で有意差有り(Tukey-Kramer多重比較)。
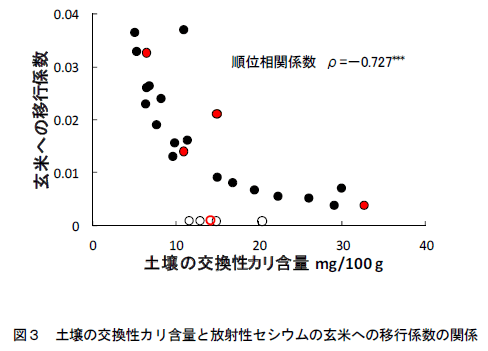
図1、2の各ほ場試験のデータ。交換性カリは栽培後の土壌の数値。白抜きプロット(○)は粘土鉱物としてバーミキュライトを多く含む土壌(図1のほ場B)。赤のプロットは図4に示した土壌改良資材施用区。***は0.1%水準で有意であることを示す。
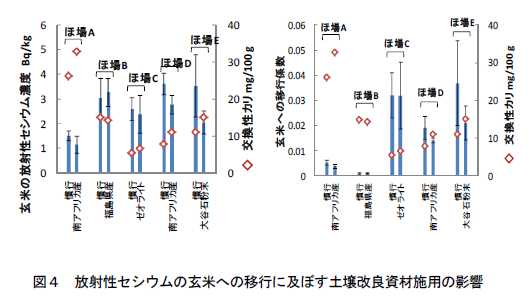
南アフリカ産および福島県産の資材はバーミキュライト。バーミキュライトとゼオライトの施用量は500 kg/10 a。大谷石粉末は1000
kg/10 a施用。交換性カリは栽培後の土壌の数値。エラーバーは標準偏差。慣行と土壌改良資材施用区の間には、いずれも有意差は認められなかった。