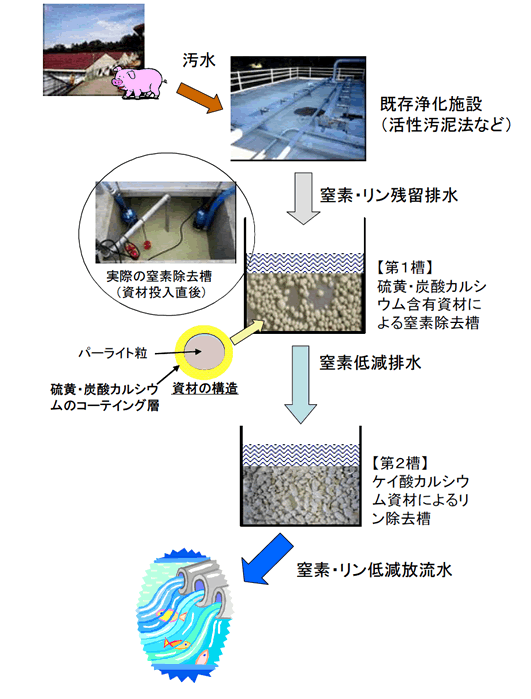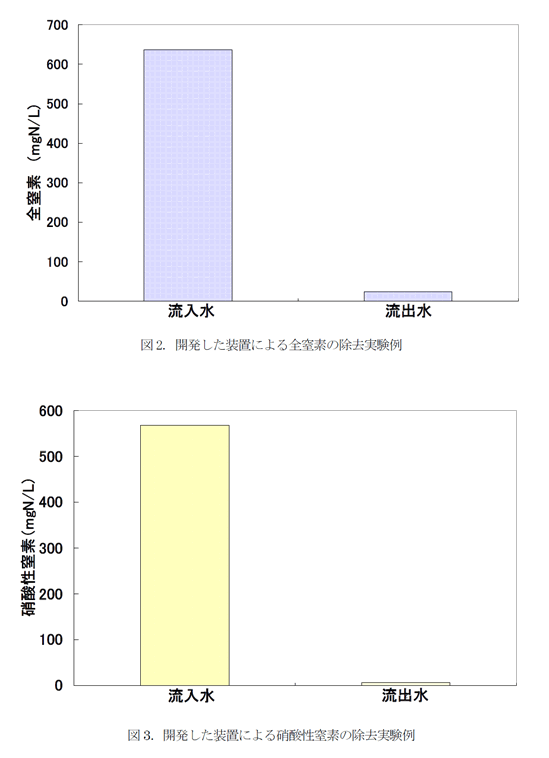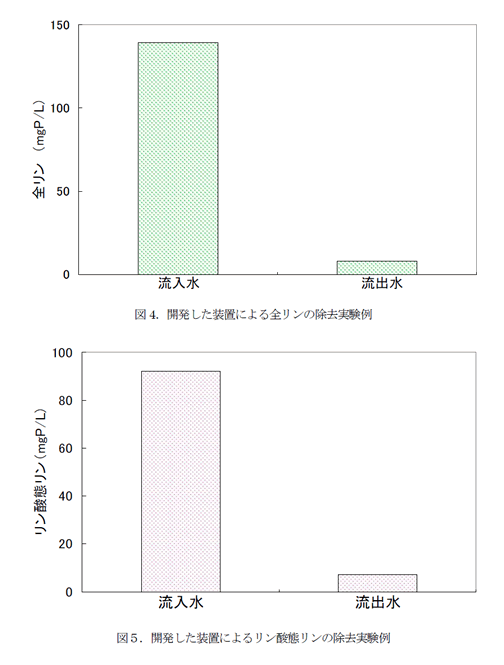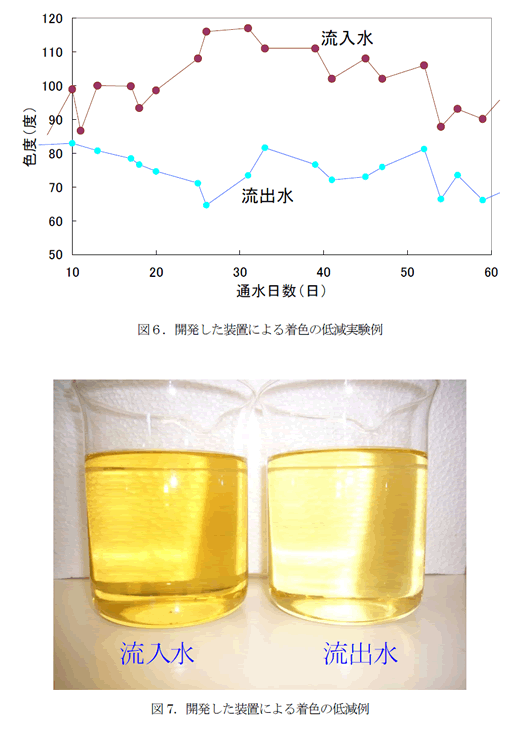プレスリリース
畜舎排水の簡易な水質向上技術
- 畜舎汚水浄化施設処理水の窒素・リン等を簡易な方法で更に低減 -
ポイント
- シンプルな構造、簡単な管理の処理装置により畜舎排水の水質向上。
- 窒素・リンの規制の厳しい地域に適した技術としての実用化を目指す。
概要
- 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という)畜産草地研究所【所長 武政正明】は、畜舎排水の放流水質を一層向上させることを目的とした簡易な処理技術を開発し、実用化に向けた取り組みを始めています。
- 近年、畜産農業は、環境面への配慮を強く求められています。養豚農家の多くは、畜舎から出てくる汚水を浄化して放流していますが、規制の厳しい地域では良好な放流水質を常に維持することが重要になります。
- 開発した技術は、異なる無機資材を充填した2つの槽を通常の浄化施設に付加することで、排水中の窒素・リンを低下させるものです。
- 第1槽では、硫黄含有資材の表面に増殖する硫黄酸化細菌の働きで硝酸性窒素を除去し、第2槽では、ケイ酸カルシウム含有資材によりリン酸を吸着して除去し、また、酸性化した排水に対しては中和効果も発揮します。これにより、通常処理を行った後の排水に含まれる窒素とリンが、さらに最大95%程度除去されます。
- 現在、福岡県農業総合試験場と共同研究を行うとともに、東京農業大学、群立機器(株)、クリオン(株)とも連携協力し、コスト低減も含め実用化に向けた検討を行っています。
詳細情報
開発の社会的背景と研究の経緯
特定の規模を越える畜舎からの排水については、全国一律に各種項目の水質基準が定められています。しかし、自治体の定めた条例によ
り、さらに厳しい水質基準が課せられている地域では、畜舎排水の窒素・リン濃度を通常の処理を行った場合よりもさらに低下させることが求められ、付加的な
処理が必要な場合があります。このための技術として各種の選択肢がありますが、多くの場合施設の構造や維持管理が複雑になり、業務負担の増加につながりま
す。そこで、施設構造が単純で維持管理の容易な窒素・リン低減技術を開発しました。
研究の内容・意義
- 処理プロセス(連続流式)の全体イメージを図1に示しました。既存の汚水処理施設での浄化後に残留している硝酸性窒
素は、硫黄と炭酸カルシウムをパーライト表面にコーテイングした粒径3~5mmの粒状資材(連携会社が試作し、本研究で始めて畜舎汚水処理に適用)を充填
した第1槽に流入させて除去します(図2、3が実験結果の一例)。この除去は、資材表面に自然増殖する硫黄酸化細菌の働きによります。また、畜舎排水に特
有の茶褐色の着色も若干改善され、さらにpHも調整されます。
-
上記粒状資材は、数ヶ月使用するとコーテイング層が消失し、パーライトが残りますが、パーライトは土壌改良資材として有効利用が可能です。
-
次に、第1槽からの流出水を、軽量発泡コンクリートの製造副産物から調製した粒径5~8mmの資材(ケイ酸カルシウムが主成分。連携会社が製造市販。)を
充填した第2槽に流入させて、リン酸を除去します(図4、5が実験結果の一例)。第1槽の流出水が充分中和されていない場合は、ここでさらに中和もされま
す。また、この槽でも排水の着色が改善されます。
-
処理実験での、第1槽流入水と第2槽流出水の色度(色の濃さを示す指標)の差の例を図6に示しました。この場合、低減率は平均3割でした。また、実際の着色の変化例を図7の写真に示しました。
-
第2槽のリン除去能力は、徐々に低下しますが、資材を一時的に流動させ表面を摩耗させると吸着能が復活します。試験では、これを繰り返すことで少なくとも
3ヶ月程度、高い除去能力が維持されました。現在、より長期間の能力維持について検討中です。剥離した粉末は、リン含有物質としての有効利用が期待されま
す。
今後の予定・期待
資材の価格は本技術の処理費用に大きく影響する要因なので、一層の価格低減に向けた検討を行っています。さらに、実際の規模での長期試験により普及に向けた利用法を確立することが期待されます。
|
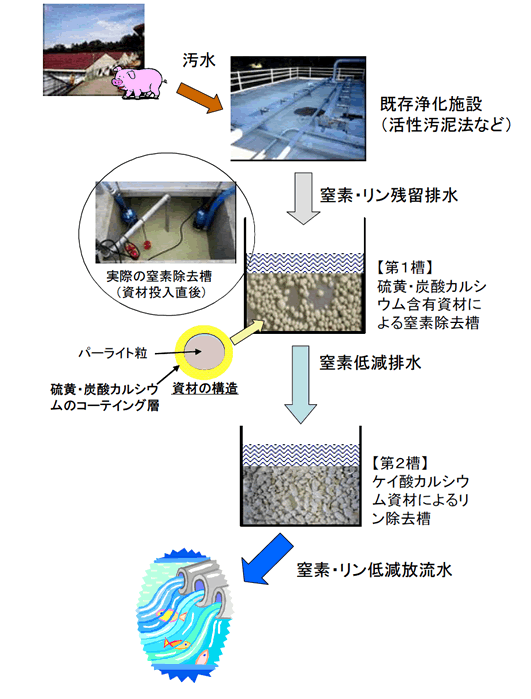
|
| 図1 処理プロセスの全体イメージ |
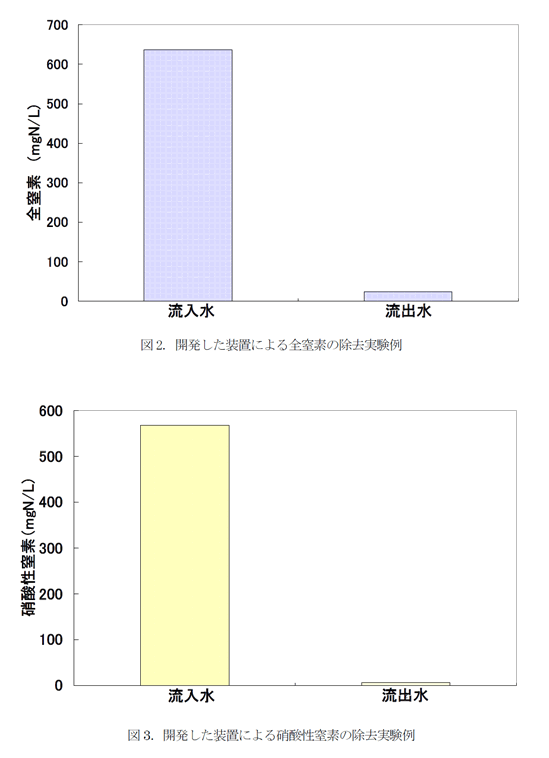
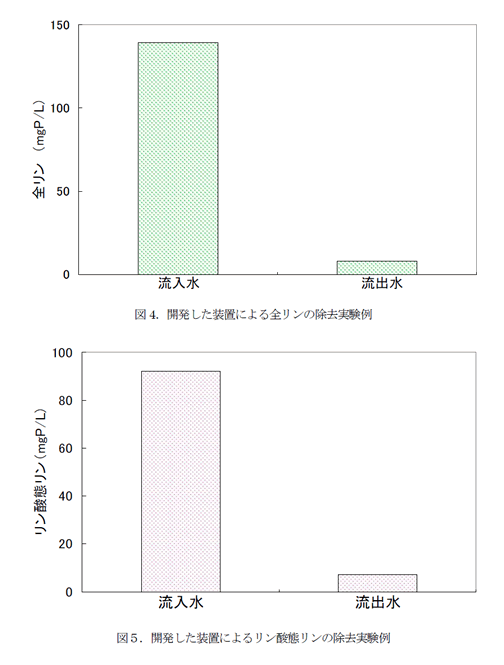
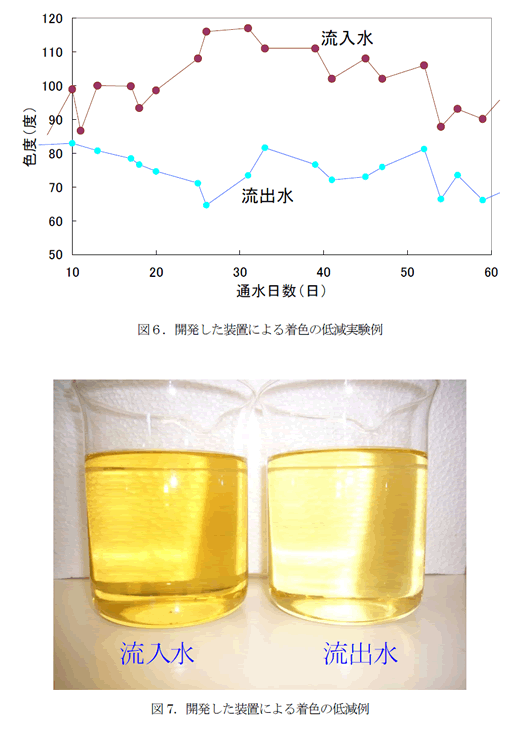
用語の解説
畜舎排水
養豚では、多くの場合、畜舎から汚水が発生します。これらの汚水は、適切な浄化処理を行って河川などに放流しなければなりません。このような場合、微生物を活用した浄化処理施設で汚水処理を行い、処理後の排水を河川などに放流しています。
窒素除去
畜舎排水中に残留している硝酸性窒素を除去するには、嫌気性条件下で有機物や硫黄などを添加し、脱窒細菌の働きにより窒素ガスにして除去します。このプロセスを脱窒と呼びます。
硫黄酸化細菌
硫黄を酸化して硫酸イオンにすることでエネルギーを獲得して生きている細菌。この細菌の仲間には、硫黄酸化と同時に脱窒を行うものも存在します(硫黄脱窒細菌と呼ばれます)。硫黄脱窒細菌を活用すると、硫黄を使って硝酸性窒素を除去できます。特別に接種したりせずに硫黄資材表面に自然に増殖します。
硫黄脱窒資材
硫黄と炭酸カルシウムの混合物をパーライト粒の周囲にコーテイングした細粒状資材。硫黄酸化細菌がこの資材表面に増殖し、硫黄を酸化しながら脱窒が起こります。発生する硫酸イオンは酸性ですが、資材に含まれた炭酸カルシウムで中和されます。資材が細粒状であるため排水と資材の接触面積が大きく、このため効率の高い脱窒が実現できます。
パーライト
園芸店などでも通常に売られている土壌改良資材です。原料鉱石を溶融し発泡後細粒にくだいたもので、軽量な多孔性無機物です。土壌の通気性や保水性を改善する効果があります。
ケイ酸カルシウム資材
建築用の軽量発泡コンクリート(ALC)を製造する際の副産物として市販されています。この、資材はリン酸を吸着する性質を持っており、また中和効果もあるので、硫黄脱窒と組み合わせると効果的な水質向上が可能となります。