情報修正 : 2025年3月19日 (水曜日)
ポイント
- 農研機構は、コムギ縞萎縮病1)に抵抗性をもつ寒冷地向け軟質小麦2)「ナンブキラリ」3)の標準作業手順書を本日ウェブサイトで公開しました。
- 本手順書は「ナンブキラリ」の耐病性や収量性、うどん等の製めん適性といった品種特性および栽培方法について解説したものです。
- 本手順書に記載された栽培方法によって、コムギ縞萎縮病による収穫量の低下を防ぎ、日本めん (うどん) に適した品質のコムギを生産できます。
概要
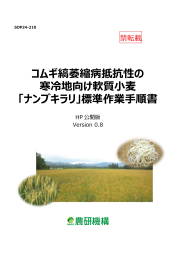
3月18日、農研機構は「コムギ縞萎縮病抵抗性の寒冷地向け軟質小麦 『ナンブキラリ』 標準作業手順書」を公開しました。
東北地域の小麦の10a当たり収量は257kgで、都府県平均の379kgと比較して低い状況で推移しています(農水省作物統計 令和5年産小麦の収穫量)。
東北地域における小麦の収量向上を図るため、コムギ縞萎縮病に抵抗性をもつ多収品種「ナンブキラリ」を育成しました。「ナンブキラリ」の粉は、色が明るく、黄色みが強い特性をもち、日本めん (うどん) に適します。
本手順書では、「ナンブキラリ」のコムギ縞萎縮病抵抗性、うどん等の製めん適性といった品種特性および東北地域における栽培方法について解説しています。
本手順書の活用により「ナンブキラリ」が普及することで、東北地域における小麦の収量の向上が期待されます。
< 利用方法 >
- 以下のURLより、標準作業手順書のサンプル版 (PDF) をどなたでもご覧いただけます。
- 標準作業手順書全編のご利用には、利用者登録 (無料) またはログインが必要です。
以下のURLより、「ログイン/利用者登録」のページにアクセスできます。
コムギ縞萎縮病抵抗性の寒冷地向け軟質小麦「ナンブキラリ」標準作業手順書
URL : https://sop.naro.go.jp/document/detail/176
URL : https://sop.naro.go.jp/document/detail/176

用語の解説
- コムギ縞萎縮病
- コムギ縞萎縮病はコムギ縞萎縮ウイルス (Wheat yellow mosaic virus) を病原とし、土壌中の微生物Polymyxa graminis Ledinghamによって媒介される土壌伝染性の病害です。融雪後の小麦に葉の黄化症状、かすり状のモザイク症状、葉がアントシアンの蓄積により紫色を帯びる症状および株全体が小さくなる萎縮症状を引き起こし、発病株では著しい減収が生じます。コムギ縞萎縮病は北海道から九州まで発生が確認されており、有効な薬剤が無いことから、抵抗性品種を栽培することが重要です。[ポイントへ戻る]
- 軟質小麦
- 軟質小麦は小麦子実に含まれる澱粉粒子やその隙間を埋めるタンパク質が固着しないので粒が柔らかく、粒子の細かい小麦粉がとれます。一般にタンパク質含有率が少なくて生地が強くない品種が多く、中力粉や薄力粉として日本めんや菓子に加工されます。[ポイントへ戻る]
- 「ナンブキラリ」
- 「ナンブキラリ」は寒冷地向けの日本めん(うどん) 用の小麦品種で、根雪期間が80日以下の地域で栽培が可能です。「ナンブコムギ」と比較してコムギ縞萎縮病に強く、多収で、小麦粉の色が優れています。品種名の「ナンブキラリ」は、小麦粉の色が明るい特徴を「キラリ」で表現し、「ナンブ」には、寒冷地で長年親しまれている「ナンブコムギ」のように広く普及する願いを込めています。2022年に品種登録されました。 (登録番号 第29297号)[ポイントへ戻る]
問い合わせ先
研究推進責任者 :
農研機構東北農業研究センター 所長川口 健太郎
研究担当者 :
同 畑作園芸研究領域伊藤 裕之
広報担当者 :
同 広報チーム長田村 徳寿
