
みどりの技術カタログ
一酸化二窒素の発生を抑制する茶園の土壌管理技術
温室効果ガス
| 作目 | 茶 |
|---|
| 技術の概要 |
|---|
|
近年、施肥場所であるうね間に刈り落とされた枝葉(以後、整せん枝残さ)が未分解のまま堆積した茶園が増加している。うね間に整せん枝残さが堆積した状況では、肥料として与えられた窒素の利用効率が低下するとともに、温室効果ガスの一つである一酸化二窒素(N2O)が多く発生することが報告されている。 堆積した整せん枝残さを土壌と混和する技術と効率的な施肥技術を組み合わせることで、茶の収量・品質を維持し、茶園からのN2O発生量を削減させることが可能である。 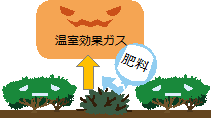 |
| 効果 |
|---|
整せん枝残さが堆積したうね間で土壌混和をすることにより温室効果ガス発生量の削減が可能茶園に堆積した整せん枝残さを適切に土壌と混和することにより、温室効果ガス発生量を約40%削減できる。土壌混和により増加するCO2発生量は、削減されるN2O発生量(CO2換算)と比べて少ない。 石灰窒素の施用によるN2O発生量の削減と整せん枝残さの分解促進二番茶摘採後の深刈り更新後に、石灰窒素を施用することでN2O発生量を約35%削減できる。また、石灰窒素の施用により、整せん枝残さの分解が促進される。 |
 |
| 導入の留意点 |
|---|
|
| その他(価格帯,改良・普及状況,適応地域) |
|---|
普及の状況滋賀県において、普及が進んでいる(「緩効性肥料の利用および深耕」が、環境保全型農業直接支払交付金の地域特認取組として支援の対象となっている)。 適応地域整せん枝残さの堆積が10cm以上認められる全国の茶園。 |
| 関連情報 |
|---|
|
・茶の生産性の向上と環境への配慮を両立する 整せん枝残さ土壌還元技術マニュアル ((独)農研機構 野菜茶業研究所(平成27年)) 
|
