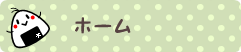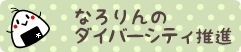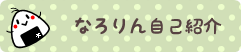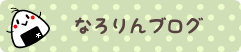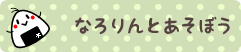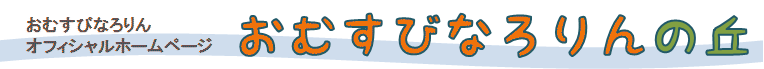

なろりん、薩摩富士を望むお茶の研究拠点へ行く!の巻
お天気: 晴れ
こんにちは なろりんです♪
気の向くままに全国にある農研機構の研究所を巡って紹介しています。
97回目のなろりんリポート、略して「なろリポ」です。
今回は、鹿児島県枕崎市にある「果樹茶業研究部門 枕崎茶業研究拠点」をリポートするよ。
こちらの拠点は小高い場所にあるので、見晴らしがよく、開聞岳がとってもよく見えるよ♪

今回訪ねたお部屋は、「茶業研究領域茶品種育成・生産グループ」。
こちらでは、お茶の需要拡大を目指して茶品種の育成や技術の開発などをしているよ。
枕崎市は、1931年に国内で初めて、紅茶に向くアッサム変種の露地栽培に成功した場所なんだって!
当時、紅茶生産が盛んなインドのアッサム地方から紅茶の種子を持ち帰って育てたところ、枕崎の温暖な気候が適していたのだそう。
日本で初めて育ったアッサム変種の紅茶の原木の葉っぱを見せてもらったよ。
緑茶向きのお茶の葉より大きいね!


日本国内でも紅茶を生産できるよう、1960年ごろにこの拠点(前 農林省茶業試験場枕崎支場)ができて、耐寒性のある紅茶品種の育種を始めたんだって。
ところが、時代が進むにつれ、紅茶の輸入が自由化されて海外産の安くて品質のいいものが手に入るようになり、国産紅茶は太刀打ち出来なくなって、緑茶品種の育種へ転換したのだそう。
そして、緑茶に転換して最初に作った品種が「さえみどり」。
30年以上前の品種なのだそう。
今も栽培面積が増えていて、現在、日本で3番目に多く作られている早生品種なんだって。

よく見ると茶畑のあちこちに、大きな扇風機のようなものがあるよ。
これは霜害を防ぐ「防霜ファン」なのだそう。
温暖な枕崎拠点でも一部の圃場は霜が降りやすく寒さがたまりやすいので、ファンを使って上の温かい空気を下に送って、霜からお茶の芽を守っているんだって。

新しい品種が誕生するまでに、何度も選抜を重ねるのだそう。
こちらは、最初の選抜段階の畑。
同じお茶の木のように見えるけど、実は3,000個体くらいあって、1つ1つ遺伝的に違うのだそう。それぞれに個体番号のプレートが付いているよ。
畑に植えて4年目にこの畑から良さそうなものを500種くらい手で摘んで、製茶するのだそう。
ちなみに、紫っぽい色の葉っぱはアントシアニンを多く含む赤い緑茶「サンルージュ」の子どもたち。
枕崎茶業研究拠点うまれの品種だよ。

別の畑では、お茶の木がかまぼこ型になっていたよ。
お茶畑でよく見られる形だね。
これは機械で効率よく茶摘みができるよう、摘み取る機械の形に合わせて整えているのだそう。

次に案内してもらった建物に入ると、大きな機械がいっぱい!
機械の動く音が響き渡っているよ。
畑から摘んできたお茶の葉っぱをこの場所で製茶するんだって。
よく見る針状のお茶っ葉になるまで、いくつも工程があるのだそう。
この機械は粗揉機といって、熱風をかけながら茶葉を大きなヘラで揉んで、葉の中に含まれた水分を乾燥させるものだよ。

こちらは揉捻機。クルクルまわりながらも揉み込んで、茶葉全体の水分を均一にするよ。

こちらは精揉機。熱と力を加えて針状の形に整えながら乾かすよ。

下の階に移動すると、先ほどの機械のミニサイズが!
摘み取ってきた数種類のお茶の葉を、一気に製茶できるんだって。


最後にお茶をごちそうになったよ!
いただいたのは、こちらの研究拠点が育成した「せいめい」。
抹茶や粉末茶に適していて、高品質で病害にも強く、2020年に品種登録された新品種!
日本産緑茶のブランド力強化と需要拡大が期待されているよ。

甘みがあって苦みや渋みが少なく上品なお味♪
抹茶は、鮮やかな深いみどり色がとってもきれい!

今回案内してくれたのは、日本茶インストラクターの資格を持っている研究者さん。
煎れてくれたお茶もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。

おまけ
枕崎駅は、JR線の最南端始発終着駅なんだって!

駅周辺に敷かれた石畳の中には、一つだけハート型の石が混じっているのだそう。

次はどこの研究所へいこうかな。
「果樹茶業研究部門」の詳細は、ホームページを見てね。