極早生で良食味のニホンナシ新品種「蒼月(そうげつ)」
要約
「蒼月」は7月下旬から8月上旬に収穫可能な極早生としては大果の青ナシである。関東以南の地域では露地栽培でもニホンナシの需要の高い盆前出荷に対応可能な青ナシ品種として普及が期待される。
- キーワード:ニホンナシ、新品種、極早生、黒斑病抵抗性
- 担当:果茶研・果樹品種育成研究領域・落葉果樹品種育成グループ
- 代表連絡先:
- 分類:普及成果情報
背景・ねらい
ニホンナシは果面のコルク層が発達する赤ナシと、発達しない青ナシに大別される。現在の青ナシの品種構成は、9月上旬から中旬に収穫される中生の「二十世紀」と「ゴールド二十世紀」がその大半を占めており、労力分散のために熟期の異なる新品種の育成が求められている。また、ニホンナシでは8月13日から15日ごろの盆より前の時期に大きな需要があるが、「二十世紀」や早生の主力品種「幸水」でこの時期の需要に対応するためには資材費や燃料費の負担が大きい施設栽培や加温栽培等による生育促進が必要であり、露地栽培でも8月上旬に収穫可能な極早生品種の育成が求められている。そこで、7月下旬から8月上旬に収穫できる極早生の良食味品種の育成を目的とする。
成果の内容・特徴
- 2007年に早生の青ナシである「なつしずく」に極早生の赤ナシ「はつまる」を交雑して育成した品種である。個体番号は「515-19」で2009年に選抜圃場に定植し、2014年に一次選抜している。2015年から「ナシ筑波59号」の系統名で、ナシ第9回系統適応性検定試験に供試してその特性を検討した結果、2020年度の同試験成績検討会において新品種候補となる。2021年7月19日に品種登録出願し、同年11月29日付で出願公表されている。
- 樹勢は「幸水」よりやや強く、枝の発生密度は「幸水」よりもやや少なく、短果枝およびえき花芽の着生はいずれも「幸水」より少ない。育成地(茨城県つくば市)における開花期は「幸水」と同時期で、収穫期は7月下旬~8月上旬と「幸水」より20日程度早い (表1)。
- 果形は円形、果実の大きさは約370gで「幸水」と同程度であり、極早生品種としては大果である。果肉硬度は「幸水」より軟らかく、糖度とpHは「幸水」と同程度で食味は良好である。年によりみつ症が発生する場合があるが、その程度は軽微である。心腐れの発生は見られない(図1、表2)。
- S遺伝子型はS1S3であり、同一遺伝子型の「凜夏」とは交雑不和合であるが、「幸水」、「豊水」等の主要品種とは交雑和合である。黒斑病には抵抗性で、黒星病に対しては罹病性であるが、慣行防除で問題は見られていない。
普及のための参考情報
- 普及対象:ニホンナシ生産者
- 普及予定地域・普及予定面積・普及台数等:東日本を中心に、従来露地栽培の「幸水」の盆前収穫が困難であった地域において、7月下旬以降から収穫可能な極早生品種として、直売所や観光果樹園等への普及が期待される。
- その他:有袋栽培を行うことで外観を綺麗に仕上げることが可能であるが、無袋栽培果実に比べて糖度が1度程度低下する点に注意が必要である。短果枝、えき花芽ともに着生が少ないため、剪定時の待ち枝の確保や夏季の新梢誘引等を実施し、花芽確保に努める必要がある。花芽の枯死や発芽不良が九州地方を中心に一部の場所で認められている。発芽不良の発生を低減できることから、「幸水」等で発芽不良が発生している地域に導入する際には施肥時期の冬季から春季への変更について検討することが望ましい。苗木販売は供給体制が整い次第、提供開始予定。
具体的データ
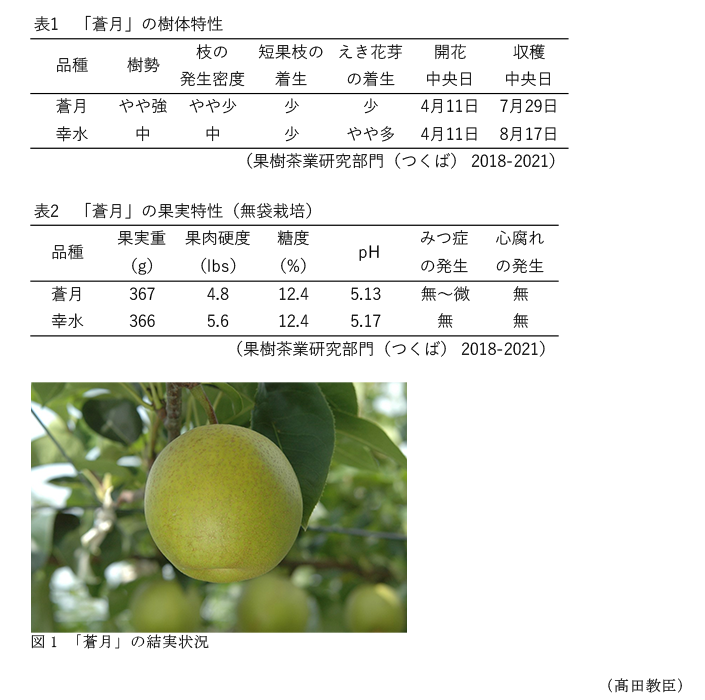
その他
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2007~2020年度
- 研究担当者:髙田教臣、齋藤寿広、西尾聡悟、加藤秀憲、寺上伸吾、澤村豊、竹内由季恵、平林利郎、佐藤明彦、尾上典之
- 発表論文等:髙田ら「蒼月」品種登録出願公表第35580号(2021年11月29日)
