土壌繊毛虫1個体からのDNA抽出法とそれを用いた系統樹作成
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
培養を必要とせずに土壌繊毛虫1個体をろ紙で押しつぶすことによりDNA抽出をする手法を開発した。この手法を形態画像撮影後の試料に適用することで、形態およびDNA塩基配列情報の両方を組み合わせた系統樹作成を効率的に行うことが可能になる。
- キーワード:土壌繊毛虫、DNA抽出、形態画像、DNA塩基配列、同定、系統樹
- 担当:九州沖縄農研・土壌環境指標研究チーム(兼:土壌生物機能研究チーム)
- 代表連絡先:電話096-242-1150
- 区分:九州沖縄農業・生産環境(土壌肥料)、共通基盤・土壌肥料
- 分類:研究・参考
背景・ねらい
土壌繊毛虫は、土壌生態系の食物連鎖の中で細菌群集の上位に位置づけられることから、土壌評価の新たな生物指標としての利用が期待されているが、必要情報のデータベース化はまだ不十分である。これまで土壌繊毛虫の同定は形態で行われてきたが、この識別は熟練を要する。近年、分子生態学的手法が用いられてきているが、土壌繊毛虫は温度や水分等の環境の変化ですぐに死滅してしまうため培養が困難であり、DNA抽出法から塩基配列解析による同定までの手法も十分に確立されていない。そこで、形態画像撮影後の土壌繊毛虫1個体を用いて培養を必要としないDNA抽出法を開発する。さらにその方法を用いて、単離した土壌繊毛虫の形態画像とDNA塩基配列解析結果を組み合わせた、より詳細な情報に基づく系統樹作成を効率化する。
成果の内容・特徴
- 土壌から遊泳してきた土壌繊毛虫1個体を実体顕微鏡下で単離し、動画撮影した後に、形態画像により土壌繊毛虫の種を同定する(図1(1)~(3))。
- 実体顕微鏡下で観察しながら水分が蒸発して土壌繊毛虫のみが残るまで待ち、約1.5 mm角に切ったろ紙をピンセットでつまんで土壌繊毛虫の上に載せ、ピンセットの先で強く押しつぶす(図1(4))。
- スライドグラスに残る土壌繊毛虫の残渣をろ紙で拭き取った後、PCR用チューブに移し、プロテイネースKを0.1μg加えて、60°Cで1時間処理した後、95°Cで10分加熱する。最後に-20°Cで1時間以上凍結させ、PCRのための鋳型とする(図1(5))。
- 繊毛虫に特異的なプライマーセット(Puitika et al. (2007) Microbes Environ., 22, 78-81)でPCR反応を行い、PCR産物の塩基配列解析により土壌繊毛虫の種を同定する(図1(6)~(7))。
- 形態画像による種名とDNA塩基配列解析による種名を比較し、これらを組み合わせた土壌繊毛虫の系統樹を作成できる(図2)。
成果の活用面・留意点
- 培養を必要とせずに土壌繊毛虫1個体からDNAを抽出できるので、これまで培養が困難で解析できなかった繊毛虫にも活用できる。
- 形態画像とDNA塩基配列解析結果が組み合わされたデータベースを作成することができ、形態またはDNA塩基配列から種を同定できるシステムの構築に活用できる。
具体的データ
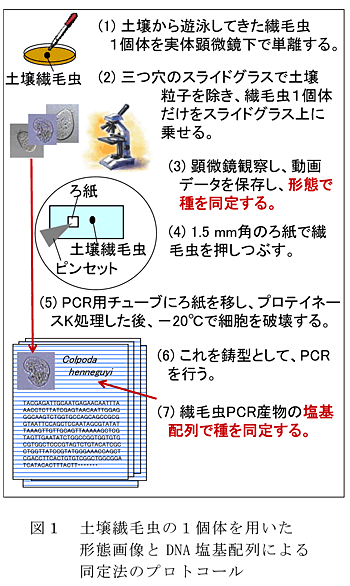
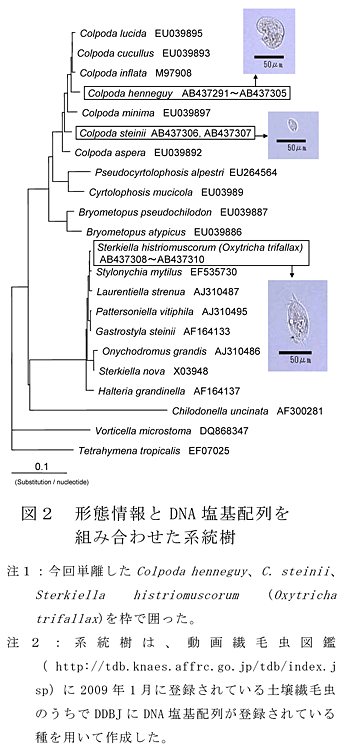
その他
- 研究課題名:土壌生物相の解明と脱窒などの生物機能の評価手法の開発
- 課題ID:214-j
- 予算区分:基盤研究費、交付金プロ(日本型有機農業)
- 研究期間:2006~2008年度
- 研究担当者:嶋谷智佳子
