かんしょ葉柄食用の新品種候補系統「関東109号」
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
かんしょ「関東109号」は葉柄の食用向けに育成した系統で、葉柄が極めて長くて太く、上葉柄収量が高い。苦みがなく、良食味であるため、真夏の野菜不足を補うものとして、また惣菜等の原料としての利用が期待される。
- 担当:農業研究センター作物開発部甘しょ育種研究室
- 連絡先:0298-38-8500
- 部会名:水田・畑作物
- 専門:育種
- 対象:いも類
- 分類:普及
背景・ねらい
かんしょは青果用、食品加工用、でん粉原料用などに利用されているが、地域特産品としてはいもだけでなく、タンパク、ミネラル、ビタミン類等に富む茎葉部についても素材として利用が検討されていた。三重、福岡などでは、かんしょの茎葉部のうち葉柄が市場販売されており、夏の野菜の一つとして利用されていたが、「高系14号」などの品種が主体であり、葉柄収量や食味については不十分であった。「関東109号」はこれらの点を改善し、いものみならず、かんしょ葉柄を真夏の野菜不足を補う品目として、また地域特産加工品の原料としての利用を促進することを目標に育成したものである。
成果の内容・特徴
- 「関東109号」は葉柄が比較的長く太い「関東99号」と「九州92号」の交配組合せから選抜された系統である。
- 本系統は従来の品種に比べて葉柄が極めて長く太く、揃いがよく、緑色である。
- 株当たりの上葉柄数及び上葉柄重は「ベニアズマ」や「高系14号」より著しく高い。
- 葉柄を生で食べても、他の品種のように苦みがなく、ゆで、揚げなど調理したときの食味が優れる。
成果の活用面・留意点
- 温暖地・暖地の真夏の野菜の一つとして、お浸しや炒め物など様々な利用が考えられ、また、地域特産的な惣菜(佃煮など)の原料としての利用が可能である。
- かんしょ葉柄に対する過去のイメージを払拭するような販売戦略を立てることが必要である。
- 黒斑病及び立枯病に対する抵抗性がやや弱であるので、種いも・苗の消毒、土壌pHを高めないなどの対策を行う。
具体的データ
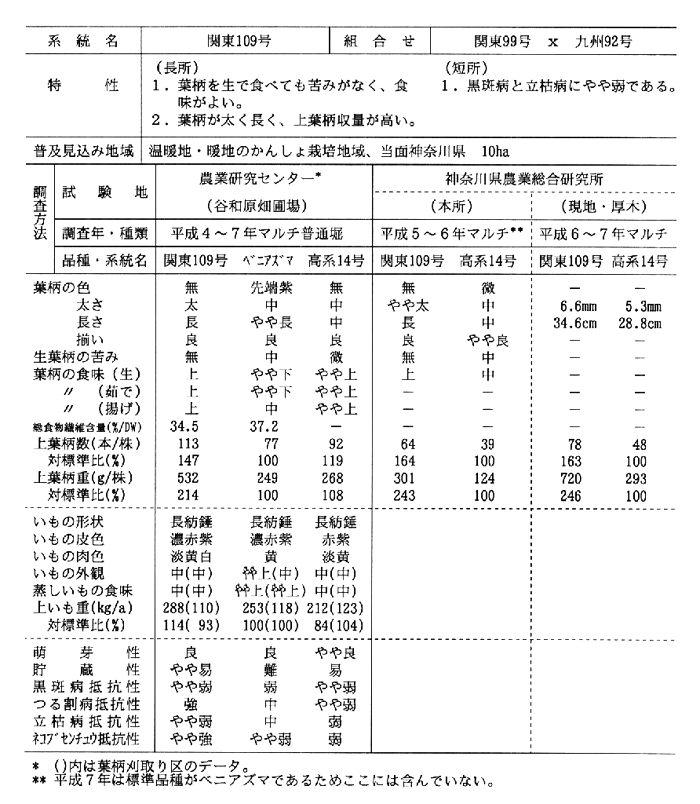
その他
- 研究課題名:温暖地向け青果用優良甘しょ品種の育成
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(昭和62年~平成7年)
