生協産直における需給調整
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
生協産直取引における需給アンバランスは供給側(農家)よりも需要側(生協)に由来する部分が大きく、その主たる原因は小売価格に敏感に反応する購買行動 にあった。今後の需給調整の手段としては、a生協へのロイヤルティを高めるような商品差別化を進める商品政策の採用、b生産者組織間の広域のネットワーク 化による対応、が求められる。
- 担当:農業研究センター 経営管理部 園芸経営研究室
- 連絡先:0298-38-8874
- 部会名:経営
- 専門:経営
- 対象:青果物
- 分類:指導
背景・ねらい
生協と生産者組織の産直取引では、作付(または収穫)前に出荷日、規格、数量、価格等の取引条件を交渉しておく。しかし生協からの最終的な発注では、事前に交渉した取引条件が変更され需給(数量)アンバランスが発生しやすい。このアンバランスは、生協側では欠品が発生した場合にのみ問題になるが、生産者組織が欠品を出した場合には以後の取引の縮小・停止が心配されるだけでなく、注文が減った場合にも過剰分の処理問題を引き起こして組織の成長・存続に係わる大きな問題となっている。そこで、実際の生協と生産者組織の産直取引を対象とした実証分析を行い、需給アンバランスを引き起こす主要因を明らかにするとともに、アンバランスを緩和するための需給調整方式を展望した。
成果の内容・特徴
- 極端な凶作年を除いては、生産者側の供給量の変動より消費者側の注文数量の変動の方が大きかった(表)。生協の消費者は、野菜に関しては一般の小売価格に反応し、生協への注文数量を大幅に変えるような購買行動をとっており、生協に対するロイヤルティ(生協に対する忠誠度)があまり強くないことが明らかになった(図)。
- 需給アンバランスは供給側よりも需要側に由来する部分が大きく、その主たる原因は小売価格に敏感に反応する購買行動にある。大型化した生協による共同購入タイプの産直取引においては、需給アンバランスの主要な要因の一つには、供給側の豊凶変動に直接起因する自明の要因の外に、このような生協組合員の行動様式(個々の消費者にとっては合理的ではあるが、組織とっては機会主義的な購買行動)があるものと推察される。
- 短期的な需給調整の手段としては、注文数量の大幅な変動に対して個々の生産者組織での対応には限界があるため、複数の生産者組織が広域ネットワークを形成し、過不足を調整するといった対応等が有望である。長期的な需給アンバランスを解消するための対策としては、生協と農家組織が共同して低農薬栽培等による安全性や有機栽培等による食味の良さ等を強調するといった製品差別化を図り、差別化商品を通じて生協組合員の生協へのロイヤルティを高め、生協価格と一般小売価格に多少の格差があっても組合員が安定的な発注を行うように誘導するといった方策が考えられる。
成果の活用面・留意点
この成果は、産直に取り組む生産者及び消費者(組織)が契約を結ぶ際に参考になる。
具体的データ
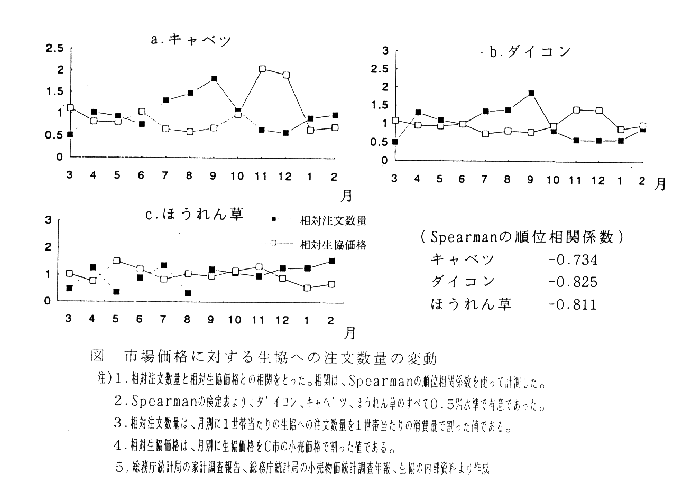
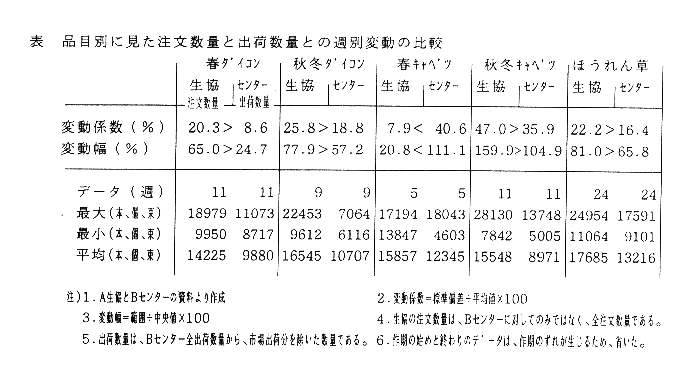
その他
- 研究課題名:産直組織における青果物の需給調整方式の策定
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(平成5年~7年)
- 担当者:大浦裕二
- 発表論文等:日本フードシステム研究会平成7年度研究大会報告
