食品・食事の血糖応答性の簡易評価法(GR法)の開発
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
食品・食事の食後血糖応答性を予測し、血糖上昇の穏やかな食品・食事の開発・提供に繋げるため、国際生命科学研究機構(ILSI Japan)と協力して開発した、ヒトの物理的・生化学的消化過程を模したインビトロ評価法(GR法)である。
- キーワード:GR法、血糖応答性、インビトロ評価法、グリセミックインデックス(GI)
- 担当:食総研・食品素材科学研究領域・糖質素材ユニット
- 連絡先:電話029-838-8053
- 区分:食品試験研究
- 分類:研究・普及
背景・ねらい
食後血糖値の急激な上昇は種々の生活習慣病の進行を促すことが示唆されており、血糖値の上昇を穏やかにする食品や食事の摂取が勧
められている。国際標準化機構(ISO)では、ヒト試験による食品の血糖応答性(グリセミックインデックス、GI)測定技術の標準化に向けて国際的検討を
行っている。しかし、ヒト試験によるGI測定は、個人差等の測定誤差が大きく、時間と経費がかかる上に、GI測定のための被験者の活動制約、ブドウ糖液の
大量摂取、採血等がストレスとなる。また、我が国の食品産業が消費者の健康維持に貢献する食品を開発・提供するための、簡便・迅速かつ信頼性の高い食後血
糖応答予測手法の開発が強く望まれている。
そこで、本研究では、特定非営利活動法人国際生命科学研究機構(ILSI
Japan)と協力し、物理的破砕および生化学的消化プロセスをモデル化して組み合わせた食後血糖応答予測手法(GR(Glucose
Releasing Rate)法)の開発を行う。
成果の内容・特徴
- ヒト試験によるGI法は、物理的破砕および生化学的消化の他に、ホルモンの影響を中心とした生理学的因子を反映する。しかしながら、生理学的因子は個人差や体調差などによる変動要因ともなりうる。そこでGR法は、食品の破砕特性と(図1に示すような)消化酵素の作用特性のみを反映させた評価系とする。また、GR法を簡便・迅速かつ安価な測定系とするため、肉挽き機(ミンサー)やプラスチック容器などの汎用性の高い器具を使用している。
- 物理的破砕法としては、ミンサー処理を咀嚼に対応させ、本工程およびその前後の工程における撹拌により、食塊を均一化させ る。また、生化学的消化工程としては、胃内消化を模したペプシン(0.3%)処理、腸内アミラーゼ消化を模したパンクレアチン(0.3%)処理(0.5% インベルターゼを含む)、そして腸管の二糖分解酵素系による消化を模したラット小腸アセトン粉末(1.5%)による単糖への分解を組み入れている(図2,3)。本法により測定した食品のGR値を図4に示す。
- 米飯、スパゲティなど8種類の食品(試料)のGR値とGI値の間にはR2=0.74の相関性が認められる。本法は、GI法では対応しにくい食事メニューの値を測定することが可能である。
成果の活用面・留意点
- 食事は多様な形状(形態)・消化性をもつ食品素材で構成されるため、GR法の適用性については、新たに個別検討・最適化が必要となるケースも考えられる。また、試験室間試験等を通じ、本法の汎用性を評価する必要がある。
- 健全な食生活を営む上では、栄養バランスと適正なエネルギー摂取が基本である。食品は総合的に評価されるべきであり、急激な 血糖上昇のみが抑制されればよいというものではない。GR値を普及させる際には、その値が一人歩きしないよう、両者を考慮した上で、健康への効果をアピー ルする必要がある。
具体的データ
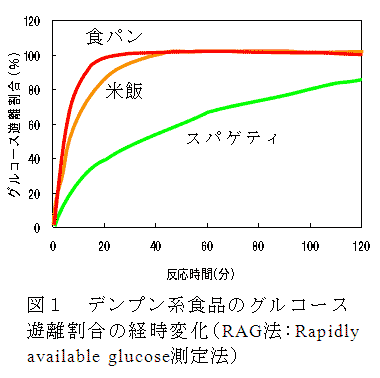
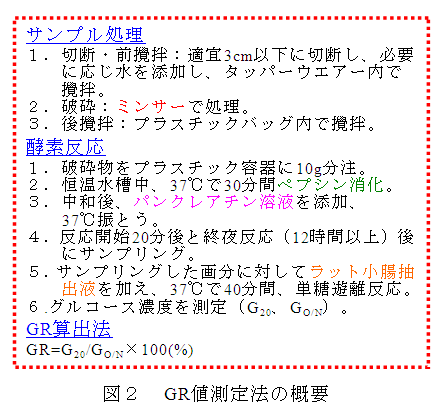
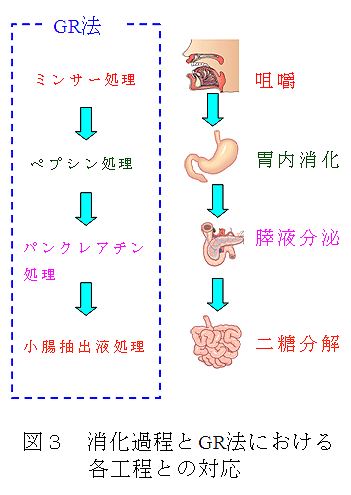
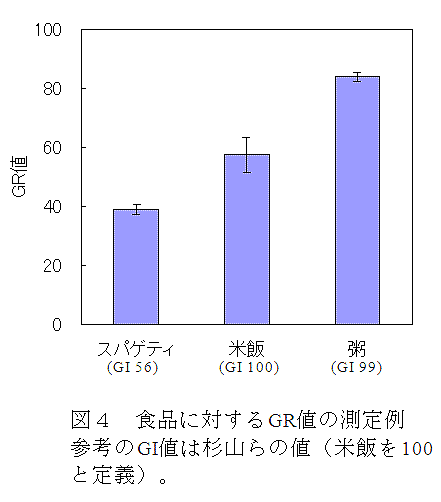
その他
- 研究課題名:血糖値上昇に関連するインビトロ評価法の開発と利用
- 課題ID:312-e
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2005~2007年度
- 研究担当者:與座宏一、熊井英志(明治乳業、ILSI Japan)、徳安健、松木順子、佐々木朋子、大江洋正、津志田藤二郎
- 発表論文等:熊井ら(2007)ジャパンフードサイエンス、46(7):33-37
