湛水直播水稲における耐ころび型倒伏性向上のための水管理
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
湛水直播水稲の耐ころび型倒伏性の向上には、土壌の表面硬度が1.5kg/cm2程度となるまでを限度とし、中干しにあわせ、生育中・後期に反復して落水期間を設ける水管理が有効である。
- 担当:東北農試・水田利用部・栽培生理研究室
- 連絡先:0187-66-2776
- 部会名:水稲
- 専門:栽培
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
水稲湛水直播栽培の耐ころび型倒伏性の向上を目的とした水管理条件を明かにするため、水稲品種どまんなかについて、 異なる回数で落水期間を設けた場合(幼穂形成期前、穂ばらみ期、 登熟初期の各時期に、7日ないし10日間無湛水で管理)の土壌の表面硬度、倒伏関連形質、生育収量の変動を解析する。
成果の内容・特徴
- 落水期間の回数が増えるにつれて倒伏程度が軽微となる傾向を示す(表1)。 こうした倒伏軽減効果は稈長の短縮ではなく、 押し倒し低抗の向上によるものである(表1)。
- 従来の中干し(落水1区)では落水期間中に土壌の表面硬度が高まっても、その後の湛水で急速に低下し、登熱期間中の硬度は0.6kg/cm2以下となる。 中干しにあわせ、穂ばらみ期もしくは登熟初期に、 反復して落水期間を設けると(落水2、落水2R、落水3)、 登熟期間中の土壌の表面硬度がより高く保たれる (図1)。
- 単位根量当たりでみた押し倒し抵抗は、 土壌の表面梗度が1.5kg/cm2程度となるまで 土壌梗度の変動に概ね比例して高まる (図2)。 落水に伴う根量の増大は比較的小さく (表1) 耐倒伏性の向上は、主に土壌硬度の増大 (図1) によってもたらされる。
- 中干しにあわせ、穂ばらみ期もしくは登熟初期に、 計2回の落水期間を設ける水管理(落水2、落水2R)は、 冷温等異常気象条件下でなければ、収量や品質に大きな悪影響を及ぼさない (表1)。
成果の活用面・留意点
- 本成果は湛水直播栽培の安定化技術確立に資する情報である。
- 土壌の表面硬度は面積2cm2 の平面型土壌硬度計を用いた測定値である。
- 本情報は沖積灰色低地土で得られたもので、 落水管理の効果は土壌の種類によって変動する可能性がある。
- 低温や高温乾燥等の気象条件におかれた場合は落水管理の実施をみあわせる。
具体的データ
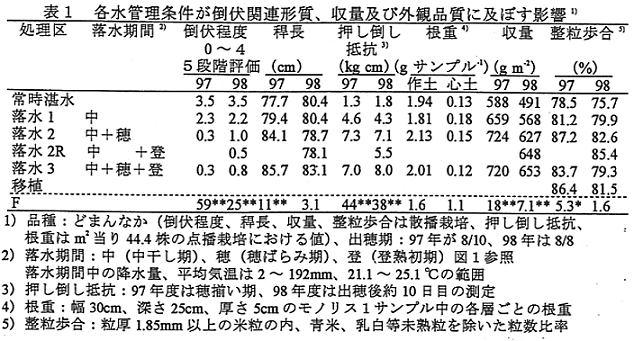
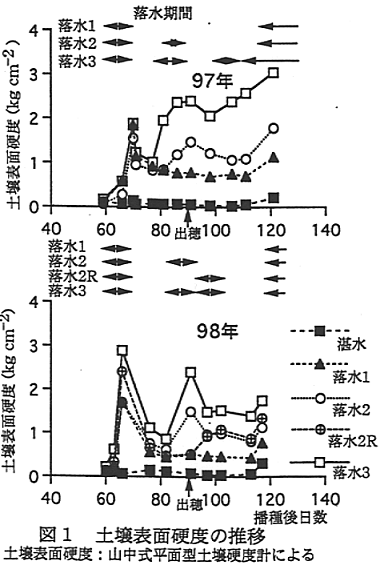
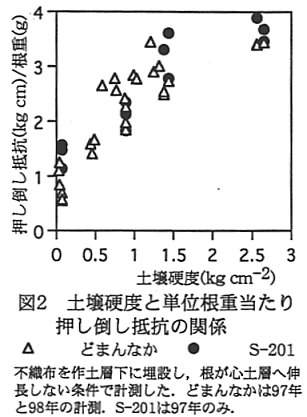
その他
- 研究課題名:作物根の地上部支持機構の解明と倒状軽減技術の開発、
- 株形式下における耐倒伏性の診断・制御技術の確立
- 予算区分 :経常、地域総合
- 研究期間 :平成10年度(平成8年~11年)
- 発表論文等:日作紀67別1,254-255,1998
