水稲における刈遅れ胴割れの品種間差異の検定法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
刈遅れによる胴割れの品種間差異は、成熟期に穂を採集後、数日間陰干し乾燥を行い、玄米水分が15~17%になったところで穂の水浸処理を30分以上する検定法で検出できる。
- 担当:東北農業試験場・水田利用部・稲育種研究室
- 連絡先:0187-66-2773
- 部会名:水稲
- 専門:育種
- 対象:稲類
- 分類:研究
背景・ねらい
米の胴割れは、刈遅れや急激な乾燥・吸湿によって発生するが、 胴割れ米は精米時に砕米となることから少ないほど望ましい。 そこで胴割れの少ない品種が求められるが、 その検定法については刈遅れによる方法以外に安定した検定法はない。一方、 刈遅れによる検定では、晩生種については検定できないこと、 年次によって発生が少ないこと等の問題があり、 刈遅れを待たずに成熟期に確実に検定できることが望ましい。そこで、 東北地域の品種について刈遅れ胴割れの多い品種と少ない品種を用いて成熟期に おける胴割れ検定の可能性を検討する。
成果の内容・特徴
- 胴割れは、 各品種10穂について陰干し乾燥後に穂の先端半分について籾摺りを行い、 百粒について玄米透視器により調査する。本方法によれば、 成熟期より30日程度遅れて収穫される(刈遅れ)米の胴割れには、 発生の多い年(1997)と少ない年(1998)が認められるが、 品種間差異は熟期別にみると年次間で同じ傾向が認められる (表1)。
- 成熟期に穂を採集し2日間陰干し乾燥後、 玄米水分が16.8%以下となったところで、穂を常温で水浸処理すると、 処理後30分まで胴割れが増加し、30分後は一定の値を示し、 品種間差異も明らかになる (表2)。
- 成熟期に穂を採集し陰干し乾燥を行い1日間隔で穂を30分間水浸処理すると、 玄米水分の低下に伴い胴割れも増加し、 品種間差異は玄米水分が17.7%に低下した2日目から確認できる (表3)。
- 上記の方法による胴割れと刈遅れ胴割との間に高い相関関係が認められる (早生:r = 0.95**、晩生:r = 095**、 図1)
- 以上のことから、刈遅れ胴割れの品種間差異は、 成熟期に穂を採集し数日間陰干し乾燥した後、 玄米水分が15~17%になったところで水浸処理を30分以上行い、 陰干し乾燥して調査することにより確実に検定できる。
成果の活用面・留意点
- 本検定法は、稲育種や品種選定における胴割れの品種間差異の検定に用いる。
- 浸水処理検定については、玄米水分が15%以下の場合、 胴割れ発生が多くなりすぎて 品種間差異が不明になる可能性があることに留意する。
- 品種間差異の判定は熟期別に行う。
具体的データ
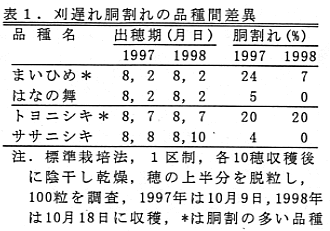
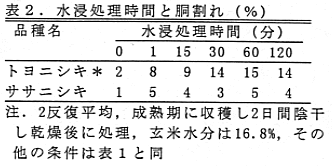
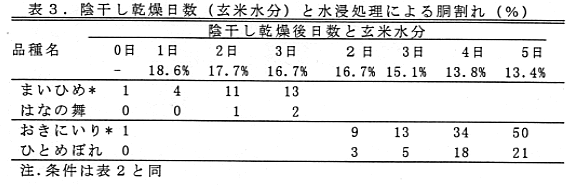
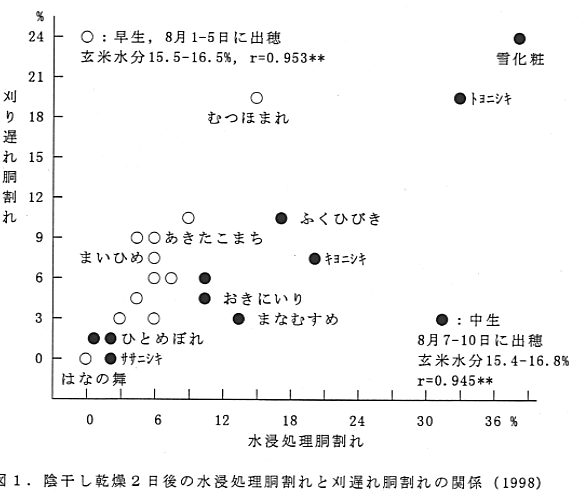
その他
- 研究課題名:いもち耐病性品種の育成
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成10年度(昭和26~)
- 発表論文等:なし
