草食家畜の放牧が二次林伐採跡地の植生遷移に及ぼす影響
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
伐採跡地へ草食家畜を放牧することにより先駆樹種等の木本類が衰退する。糞中種子によるシバ草地構成種の侵入後6年でシバが最も優占する。樹葉中タンニンに対する畜種の採食反応の違いにより、山羊を放牧する方が牛よりも木本頚の衰退とシバ草地化が早い。
- 担当:東北農業試験場・草地部・草地管理研究室
- 連絡先:019-643-3562
- 部会名:畜産(草地)
- 専門:生態
- 対象:家畜類
- 分類:研究
背景・ねらい
二次林伐採跡地に家畜の放牧のみを繰り返すことにより植生がどう遷移するかを 明らかにする。同時に畜種の違いがもたらす影響を検討する。 それにより放棄農林地等の放牧家畜による利用・保全技術の開発に資する。
成果の内容・特徴
-
伐採跡地0.67haに日本短角種成雌牛を2頭、0.33haに山羊10数頭を各々伐採翌年から
9年間、毎年春夏秋各々約4、4、1週間放牧した。
- 両放牧区とも類似した初期遷移のパターンを示し、木本類、草本類、 糞由来草種の順に優占化した(図1)。
- 両区とも糞上にシバの実生が出現して以来3年間はその被度の拡がりは僅かであるが、 4年目で顕在化する。その後は年毎に被度が倍加し、 6年目で第1位の優占種となる(図2)。また、 シバの増加とともにその随伴種であるオオチドメも増加する。 外来牧草やその随伴雑草は侵入当初の初期生育はシバより優れるが、 その後の被度の増加は小さい。
- 両区とも伐採直後は切り株からの萌芽が、次にヌルデ、 クマイチゴ等の先駆樹種が出現する(図3)。 ヌルデは樹葉中に採食防御物質であるタンニンの含量が当初高いため、牛は採食せず、 牛区で急速に繁茂する。同様にクリもタンニン含量が高いため維持される (図4)。しかし、 ヌルデはタンニン含量が低下する発芽6年目以降、 またタンニン含量が低いクマイチゴやヤマザクラ等は当初から、 牛に採食され衰退する。
- 山羊に対する樹葉中タンニンの防御効果は小さく、山羊区ではヌルデもよく採食され、 木本類の衰退が早い(図3)。その結果、 山羊区は牛区より放牧庄が低いにもかかわらず、シバ草地化は早い。
- 木本類、特に遷移初期に出現する先駆樹種が持つ採食防御機能の差と、 それに対する放牧畜種の採食反応の差が、 放牧条件下の伐採跡地の初期遷移に大きな影響を及ぼす。
成果の活用面・留意点
- 伐採跡地等の攪乱を受けた場所に出現する先駆樹種や 木本萌芽からなる植生の放牧条件下での遷移機構の解明やシバ草地化技術の開準、 また放牧家畜の嗜好性や植物の防御機構解明の参考となる。
- 放牧強度は各放牧回次毎に牧区内の可食葉量がなくなるまでの強放牧とする。
具体的データ
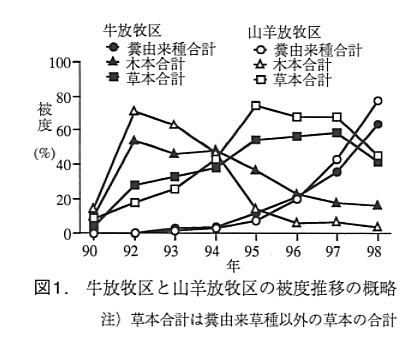
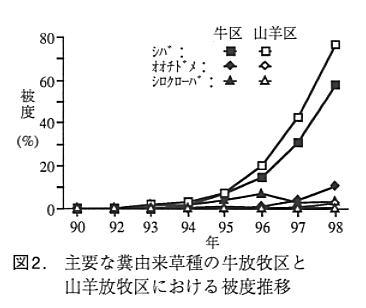
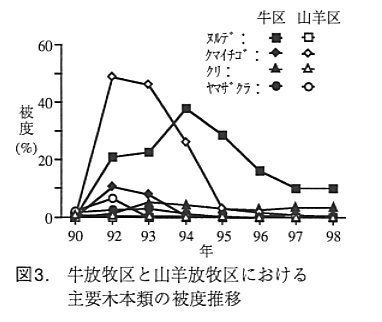
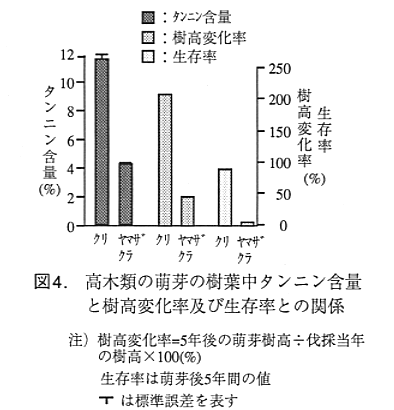
その他
- 研究課題名:アカマツ林伐採跡地の放牧条件下における植生遷移制御
- 予算区分 :大型別枠(生態秩序)
- 研究期間 :平成10年度(平成元年~10年)
- 発表論文等:森林極相地帯のシバ草原成立機構における草食動物の役割
5. タンニン含量を樹高の伸びに伴って変えるヌルデの採食防御機構
6. 樹葉中タンニン含量の変動が放牧畜種の採食反応と植生遷移に及ぼす
影響、平成9年度日本草地学会大会講演発表、1997
