兼業深化地域における民俗行事の社会的機能と課題
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
兼業深化地域における民俗行事の社会的機能は、「社会的まとまりの単位である集落を住民に認知させるシンボル」であることを解明した。民俗行事の「連帯感の醸成」機能を回復するには、資金面、労力面等での伝承基盤の強化が課題である。
- 担当:東北農業試験場総合研究都農村システム研究室
- 連絡先:019-643-3493
- 部会名:経営、総合研究(農村計画)
- 専門:農村計画
- 対象:
- 分類:研究
背景・ねらい
民俗行事は「連帯感の醸成」という社会的機能を持ち、 地域活性化を促進するとされてきた。しかし、こうした理解は、 兼業化が進んだ農村社会の現実に即していない。そこで、 民俗行事の社会的機能を解明し、 「連帯感の醸成」機能の回復に向けた課題を提起する。
成果の内容・特徴
- 岩手県北上市S集落(表1)の小正月行事(田植踊り)は、自治組織が伝承している。 かつてこの行事は、集落最大の娯楽であるとともに、 交流を通して集落への住民の帰属感を強化し、連帯感を醸成した。しかし、 娯楽手段・機会の多様化等により住民の関心が薄れ、一時期中断した。 行事の中断前(昭和29年以前)を第I期、中断期(昭和30~48年)を第II期、 復活後(昭和49年以降)を第III期とし、この間の自治組織活動の変化を踏まえ、 今日の小正月行事の伝承基盤と社会的機能の特徴を明らかにした。
- 第I期には小正月行事を含む多様な相互扶助活動が行われていたが、 第II期には大半が縮小・中止され、兼業化の進行に伴い住民の社会関係は希薄化した。 こうした中、住民活動の場を作るため、集会所の整備が始まり、 敷地確保や費用調達等の活動を通して住民の交流が維持された。 第III期には連帯感醸成を目的に小正月行事が復活された (表2)。
- 復活後の小正月行事の伝承基盤は、資金提供者、労力提供者、観客が減少し、 しかも資金、労力の提供者は自治組織役員と一部有志のみであった (表3)。こうした伝承基盤の脆弱化によって、 住民交流が減少したため、第III期の行事は連帯感醸成の機能を果たしていない。 現在、総会の開催を除き、小正月行事が唯一の定期的な自治組織活動となっている。 行事は、「集落が自治組織活動の拠点であり、社会的まとまりの単位であることを、 住民に認知させるためのシンボル」として機能しているに過ぎない (表4)。
- 小正月行事が「連帯感の醸成」の機能を果たすには、伝承基盤の強化が前提となる。 そのため、多様な参加の場の確保、 資金や労力の相互提供制等によって参加者を増やし、 自治組織役員及び一部有志の資金面、労力面の過剰負担を軽減することが課題である。
成果の活用面・留意点
-
社会的機能の分析であり、誘客等による経済的機能については、別途検証を要する。
具体的データ
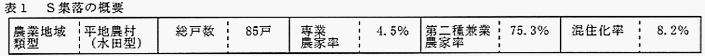
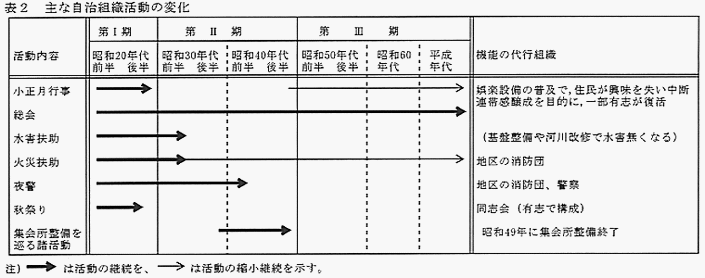
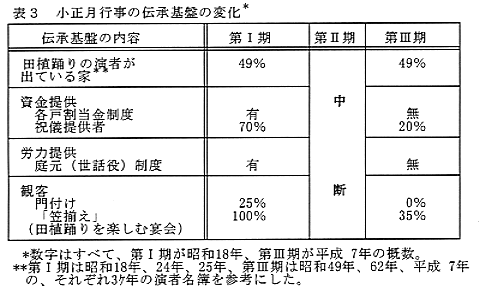
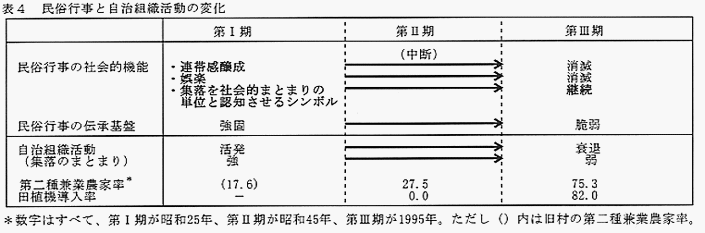
その他
- 研究課題名:民族行事の伝承過程の変容
- 予算区分 :経常
- 研究期間 :平成10年度(平成7年~10年)
- 発表論文等:民族行事の伝承過程の変容、日本村落研究学会自由報告,1997
