北日本の夏の天候は5年周期で変動している
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
北日本における近年の夏の天候は、明瞭な5年周期で変動している。1982年以降の主な冷夏年(1983年、1988年、1993年、1998年、 2003年)はすべて5年間隔で発現しており、冷夏の翌年は1989年を除いた3例が一転して暑夏となっている。
- キーワード:気象変動、周期性、やませ、冷夏
- 担当:東北農研・地域基盤研究部・農業気象研究室
- 連絡先:電話 019-643-3461、電子メール kanno@affrc.go.jp
- 区分:東北農業・生産環境(農業気象)、共通基盤・農業気象
- 分類:科学・参考
背景・ねらい
1980年代以降、北日本では冷夏と暑夏が頻発している。北日本で農業を安定的に営むには、気象変動を的確に予測することが重要であ る。そこで、北日本の気象変動を、やませの吹走をよく表す稚内と仙台の気圧差を用いて検討し、その周期性を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 稚内と仙台の気圧差の時間変化をみると、1982年以降、暖候季に明瞭な5年周期の変動が認められる(図1)。7月および6月~8月の3ヶ 月平均値(夏季平均値)で見ると、5年に一度値が高まっていることが分かる(図2)。
- やませの影響を最も強く受ける青森県八戸の6月~8月平均気温を、1982年を起点として5年ごとに重ね合わせると、2年目 のステージには1983年、1988年、1993年、1998年および2003年の冷夏が含まれ、3年目のステージは1989年を除いて暑夏となっている (図3)。このような傾向は北日本平均気温についても明瞭に認められる。
- 日本の夏の天候は、熱帯海洋の対流活動にも影響を受ける。そこで対流活動と関係の深い熱帯海水面温度の東西差(6月~8月平均) を計算し、図3と同様に時間変化を見た(図4)。 その結果、2年目のステージで値が大きく、熱帯太平洋海域での対流活動が抑制されていること、また、3年目のステージで値が小さく、 対流活動が強化されて いることが示唆された。従って、北日本の夏季に認められる5年の周期変動は、熱帯海水面温度の周期的な経年変動の影響を受けている と考えられる。
成果の活用面・留意点
- 熱帯海水面温度の周期性を監視することにより、北日本の夏季の長期気象予報に使える可能性がある。
- 仮に5年周期変動が今後も続くと仮定すると、2004年は高温の夏に相当する。ただし、過去4例のうち例外が1事例あること(1989年) 、2003年の熱帯海水面温度差が他の4事例に比較して最も小さかったこと(図4)など、マイナスの判断材料も存在するので、予測に用 いるには注意を要する。
具体的データ
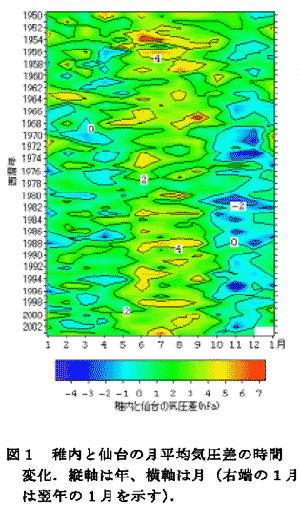
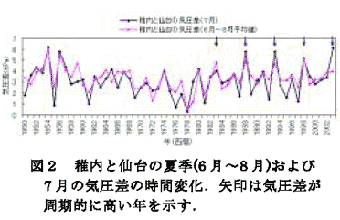
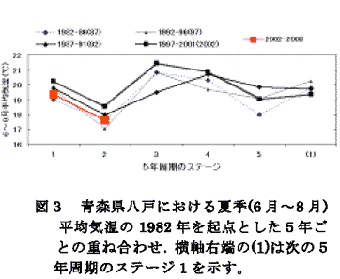
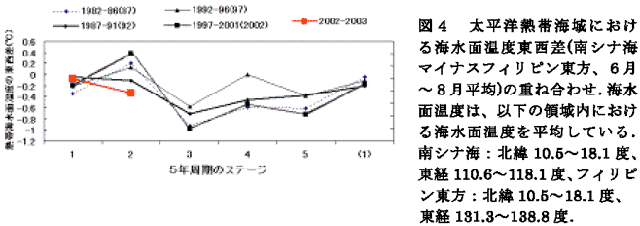
その他
- 研究課題名:東北地方における夏季気温の周期変動およびその影響の解明
- 課題ID:05-07-01-01-04-03
- 予算区分:交付金
- 研究期間:2003~2007年度
- 研究担当者:菅野洋光
