アネモネに発生した新病害、球根腐敗病
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
アネモネ球根が発芽阻害される被害が発生し、発芽阻害された球根は Rhizopus oryzae Went et Prinsen Geerligs に侵されていた。本病害は新病害であり、 球根腐敗病と命名した。
- キーワード:アネモネ球根、発芽阻害、Rhizopusoryzae、新病害、球根腐敗病
- 担当:野菜・茶業試験場環境部病害第2研究室
- 連絡先:0592-68-4642
- 部会名:野菜・茶業
- 専門:作物病害
- 対象:花き類
- 分類:研究
背景・ねらい
1994年10月に三重県津市で自家採取したアネモネの球根の発芽が阻害される被害が発生した。また、市販の球根を植え付けた場合にも同様の発芽阻害が認められた。被害を受けた球根は白色の菌糸に覆われ、糸状菌による病害と思われるため,本病害の病原体を同定し、発病条件、伝染源等を明らかにする。
成果の内容・特徴
- 本病の症状は、球根が白色の菌糸に覆われ土団子状になり、内部は乾燥条件下では褐変し、高湿下では白色のままペースト状に軟化・腐敗する。病状が進むと内部は層状に分離し白色の菌糸が充満する。密植した場合には、被害株周辺の土壌表面もマット状に白色の菌糸で覆われる。(図2)
- 本病を引き起こす病原体は、生育適温と形態的な特徴から接合菌類のRhizopusoryzaeWentetPrinsenGeerligsである。(表1)(図1)
- 本菌の胞子のう胞子懸濁液(106個/ml)に浸漬した球根を植え付けると,15~35°Cの温度条件下で本病が発生する。
- この温度条件では、球根が発芽するまでには植え付けてから1週間以上かかるのに対し、本菌の菌糸は3~4日で球根を覆い、発芽を阻害する。発芽後の球根、実生、展開後の葉や葉柄に胞子懸濁液、菌叢を接種した場合には、全く異常を引き起こさない。
- 前作で発病した土壌に植え付けた場合、あるいは、本菌の胞子懸濁液に球根を浸漬し、乾燥条件で保存した後に植え付けた場合にも発病する。
成果の活用面・留意点
- 本病を防ぐには土壌と球根の消毒を行うなどの予防対策が必要である。
- 病原体が同定されたので適切な薬剤の登録、選択ができる。
- 本病の伝搬には、土壌伝染、球根の収穫・貯蔵時における感染が示唆される。
- 本病菌は多くの植物を侵す多犯性菌であり、他の球根類にも同様の病害を引き起こす可能性がある。
具体的データ
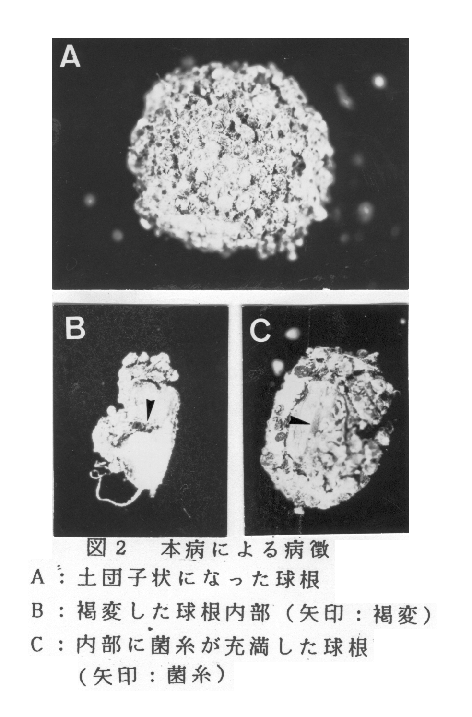
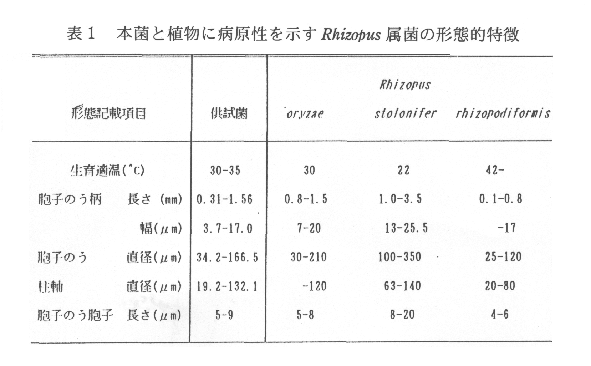
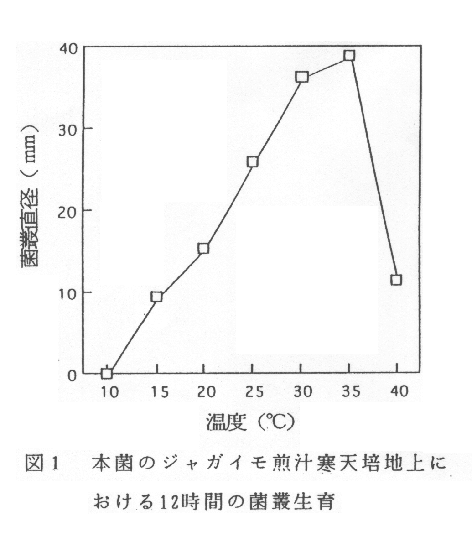
その他
- 研究課題名:Rhizopus属菌によるアネモネの新病害
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(単年度)
- 研究担当者:窪田昌春・我孫子和雄
- 発表論文等:日本植物病理学会関西部会(1995年10月)講演発表
