新香味茶用品種育種のための半発酵茶少量製茶法
※アーカイブの成果情報は、発表されてから年数が経っており、情報が古くなっております。
同一分野の研究については、なるべく新しい情報を検索ください。
要約
製茶工程中の発酵処理により煎茶とは異なる新たな香味をもった品種の育種に利用できる半発 酵茶の少量製茶法を開発した。生葉1Kgを遠赤外線萎凋後冷 却、揉捻、静置して釜炒り製茶 することで品種・系統の半発酵茶特性を再現性よく評価できる。
- キーワード:発酵処理、半発酵茶、少量製茶法、遠赤外線萎凋
- 担当:野菜・茶業試験場久留米支場・茶樹育種研究室
- 連絡先:0993-76-2126
- 部会名:野菜・茶業
- 専門:育種
- 対象:茶
- 分類:研究
背景・ねらい
チャの生葉を萎凋処理すると種々の香気が発揚されるが、これには品種間差が大きい。このため発酵処理により優良な香味を有する新香味茶向き品種の育種を効率的に行うために、遠赤外線処理による萎凋法を確立し、少量の生葉で半発酵茶を製造する方法を開発する。
成果の内容・特徴
- 半発酵茶の製造は、生葉1Kgをセラミックヒータによる遠赤外線萎凋(80分、水分減30~40%)、静置冷却(20分)、揉捻(10分)、室内静置(60分)、釜炒り(280°C、8分)、水乾(180°C、13分)、乾燥の工程で製造する。(図1)
- 半発酵茶向き品種選抜のための審査基準を策定した。(表1)
- 本法で製茶すると品種・系統の半発酵茶特性が評価でき、日干萎凋で製造した場合と同様の傾向が見られたことから育種の選抜に利用できる。(表2)
- 遠赤外線萎凋で製造した場合、日干萎凋に比べやや香味が劣るが、天候に左右されないため効率的な製茶が可能である。
- 日干萎凋で製造した場合、ウーロン茶風の香味となるが、遠赤外線萎凋で製造した場合にはウーロン茶と紅茶の中間の香味となる。
成果の活用面・留意点
- 遠赤外線萎凋では、萎凋時の生葉温度が40°C以上に上がらないように出力あるいは熱源と生葉との距離を調節する。
- 遠赤外線萎凋の場合、高温期の三番茶では、萎凋程度は30%とやや軽くする方が滋味が紅茶風とならず品質が良い。
- 揉捻は煎茶用の2Kg型揉捻機、釜炒りは2Kg型炒葉機、水乾は2Kg型水乾機が利用できる。
具体的データ
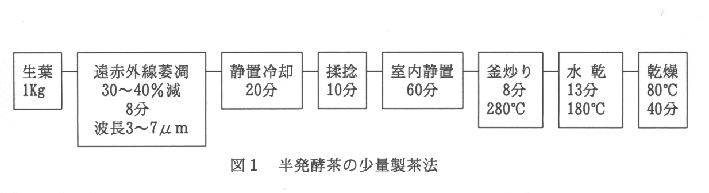
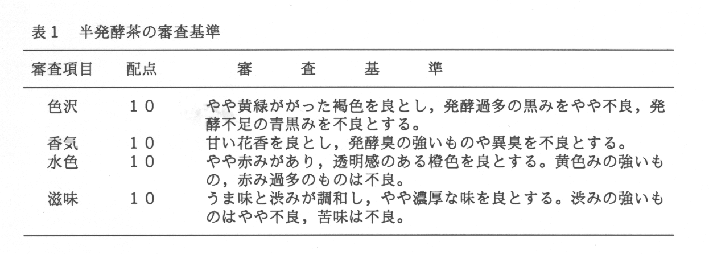
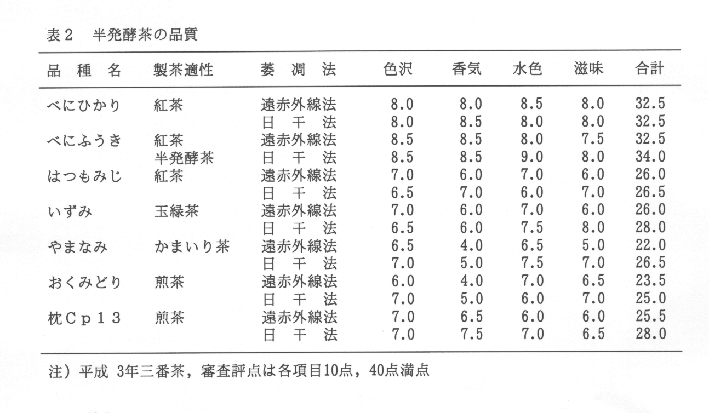
その他
- 研究課題名:アッサム雑種の利用による新香味品種及び耐病性品種の育種
- 予算区分:経常
- 研究期間:平成7年度(昭和62年~平成8年)
- 研究担当者:和田光正・武田善行・根角厚司
- 発表論文等:
①半発酵茶少量製茶法の確立,遠赤外線萎凋装置による萎凋程度の検討.久留米支場年報,6,199-202,1993.
②半発酵茶少量製茶法の確立少量製茶法における製茶工程の検討.久留米支場年報,6,202-204,1993.
