1. イチゴの消費量
いくつかの調査から、沖縄県のイチゴ消費量は生食用600トン程度、加工用200トン程度と推定されています。
2. 現在の販売状況
ほぼ100%県外産で主に航空便で搬入されています。九州産が多いようですが、東京などからも転送されてきます。
収穫後早くて2日目、普通は3日目の販売です。しかし、輸送中の積みかえやコールドチェーンの途切れによって荷傷みが起こり、1~2日間しか販売できません。
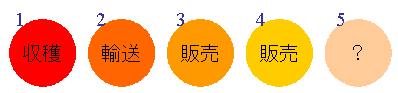
コールドチェーン…生鮮品などを冷凍、冷蔵、低温の状態で生産地から消費地に送っていく仕組みです。
中央卸売市場の価格を見ると、やはりクリスマスがある12月が高く、年が明けると入荷量が増えてくることもあって安くなってきます。12月中旬、本島内のあるお店では1パック780円で売られていました。
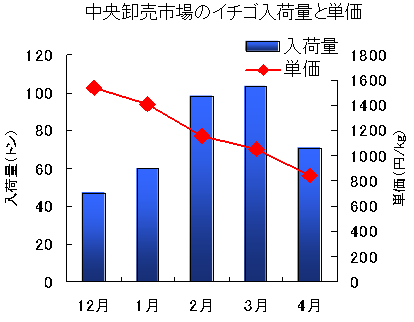
中央卸売市場のイチゴ入荷量と単価
3. 県産イチゴ
沖縄県産のイチゴだと収穫当日あるいは翌日から販売できるので、着色が十分進んだ段階で収穫できます。消費者も鮮度のよいものを食べることができます。もちろん、お店にとっても魅力のある商品になります。
実際、試験栽培のイチゴは好評ですし、お話を伺った量販店でも早く商品がほしいと言っています。
4. 鮮度第一を「売り」にできる小規模生産
沖縄県は気温も高く、イチゴの県内流通でもコールドチェーンが必要です。でも、小規模生産段階であれば専用の施設がなくても大丈夫でしょう(別の冷蔵庫の流用、クーラーボックスによる出荷など)。小規模だと収穫・調整も時間がかからないので、朝採ってお昼前にお店に搬入できるからです。
2アールくらいから始めてみませんか。この程度であれば高設栽培でなくてもあまり負担にならないと思います。
5. 出荷先
卸売市場への出荷は想定していません。直売所などが主な出荷先になるでしょう。生産者から直接買い付けてくれる量販店もあります。いずれにしても個人で搬入することになるでしょうから、近いところを選ばなくてはなりません。時間の節約だけでなく鮮度も保てます。
クリスマス前に出荷できれば、ギフト用としてより高値で販売できるのではとも考えられます。

宜野座村の直売所、未来ぎのざ
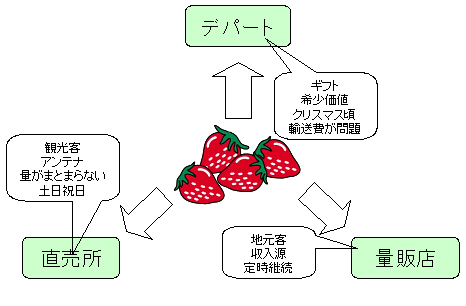
小規模段階で想定される出荷先
6. 心がけたいこと
鮮度をアピールし、消費者の信頼を得るために、例えば以下の点を心がけてください。
- 品質(大きさ、味、色、外観など)を一定以上に保つ。
県産イチゴは今まさに誕生しようとしているところです。それだけに一度評判を落とすと消費者にそっぽを向かれてしまうでしょう。 - 大きさによる選別はほどほどにする。
これは販売までの時間を短縮するためです。 - 生産者名とともに収穫日を表示する(シールを貼り付ける)。
収穫日表示は売れ残りなどを考えると勇気が入ります。しかし鮮度アピールにはとても効果があると思いますので、売れ具合を見て判断してください。 - 販売箇所では明るい照明してもらう。
今試験栽培されている「さちのか」は濃い赤色をしています。このため、明るいところではとても鮮やかなのですが、そうでないところでは黒ずんで見えてしまうことがあります。

