沖縄本島中部に分布するマージ土壌は、水持ちが悪く、また乾いた時に非常に硬くなるなど、土壌物理性が良くない。一般に土壌物理性の改善には、堆肥などの有機物を施用することが有効である。しかし、乾いたときの硬化については、有機物を施用した土の方が硬くなる場合もある。宜野座村内のマージ土壌の硬化の性質と、土を硬くすることなく物理性を改善するための有機物の施用例を提示する。
1. どんな土が硬くなるか
マージ土壌の、乾燥に伴う硬化の度合いを決めるのは『土の粒の細かさ』と『pH(酸性~アルカリ性を示す値)』の2つの要因である。粒の細かい(粘土が多い)土、また、pHの高い(アルカリ性)土が、より硬くなる。pHについては、もともと酸性の土に石灰を入れすぎてアルカリ性に傾いた場合にも、土が硬くなる。宜野座村の土壌の特徴として、隣接した畑同士や、一枚の畑の中の地点間でもpHが大きく違う場合があるので、石灰を入れる場合には土のpHを細かく把握して行い、局所的な入れすぎなどを避ける。
2. 各種の有機物の施用とその分解が土の硬化に与える影響
- 施用法: 有機物は、施用した直後には土の硬化を和らげるが、施用してから時間がたつとともに硬化の度合いが増し、3~6ヶ月後にはかえって土が硬くなることがある。特に、もともと硬くなる性質の強い土(粘土が多くアルカリ性)で、この問題が起こりやすい。しかし、施用して一年がたち、有機物の分解がさらに進むと、有機物による土の硬化の促進は起きなくなる。
一方、土の水持ちは、有機物の施用によって確実に改善される。水持ちの改善効果は、有機物を施用して一年たち、分解が進んだ状態でも維持される。このことから、土の物理性の改良に主眼をおく場合は、分解の進んだ状態の有機物を土の中に貯める。つまり、長年にわたって有機物を入れ続けることが望ましい。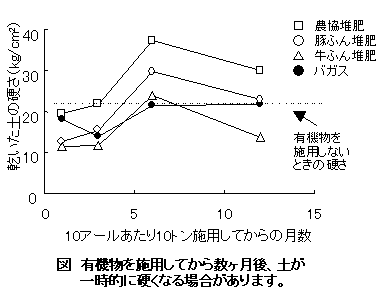
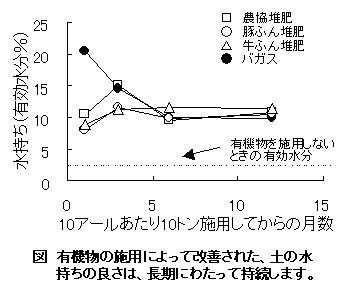
- 有機物の種類: 土を硬化させず、水持ちを改善する事を重視する場合は、バガスや牛ふん堆肥が、農協堆肥(けいふんとビールかす原料)や豚ふん堆肥に比べて優れる。リン酸など肥料成分の供給も期待したい場合や、酸性の土壌でpHを上げたい場合は、農協堆肥や豚ふん堆肥の方が優れる。
3. 目的に応じた有機物の選択と施用
以上をふまえて、土の性質、および目的とする土壌改良のポイント別に、施用すべき有機物の種類を整理して次の表に示す。
- 土壌の硬化を避けたい場合: 土をいじる頻度が高い作期の短い露地野菜など、土の扱いやすさを保ちたい場合は、バガスや牛ふん堆肥が望ましい。
- 土壌の硬化をある程度許せる場合: サトウキビ(特に株出しを行う場合)のように作期が長くて土をいじる頻度が低く、表土の硬化をある程度許せる場合は、目的(土の物理性の悪化防止や改善を主眼とするか、養分の供給も期待するか)に応じて有機物の種類を選択する。
1.、2.いずれの場合も、長期的な土つくりが基本。なお、チッソ、リン酸、カリなどは通常の施用量を化学肥料で施用することが前提。


