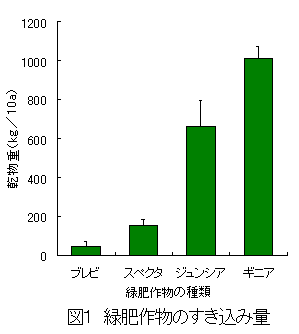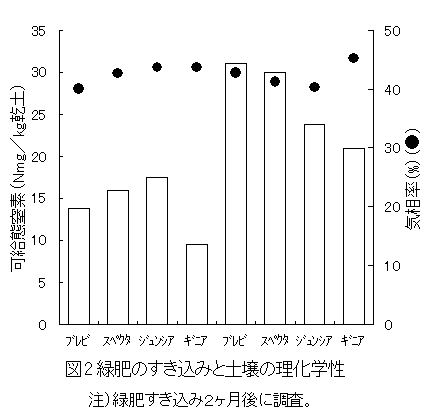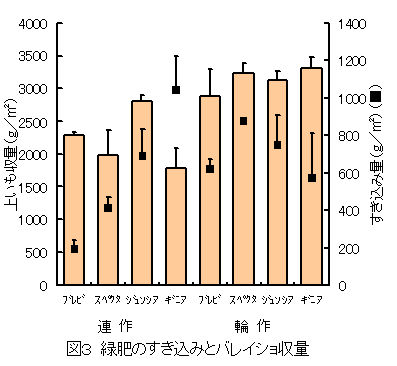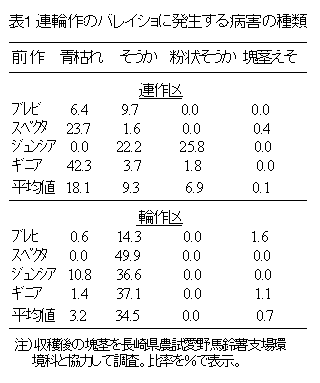沖縄南西諸島の農業においてサトウキビの生産は重要な位置を占めているが、収益性が低いため商品性の高い作物の導入が求められている。沖縄本島北部では、10数年前からサトウキビに替えて商品性の高い青果用バレイショが生産され、収益性向上に取り組んでいる。しかし、連作年数を経るにしたがって土壌病害による連作障害や有機物の不足に伴う地力の低下が生じ、バレイショを安定的に生産することが難しくなっている。そこで、バレイショの生産を安定させるために、緑肥作物のクロタラリアやサトウキビとの輪作による新しい作付体系を開発した。
1. 従来の作付け体系と新しい作付け体系
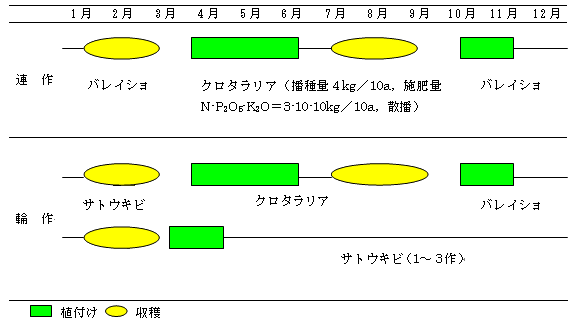
2. 緑肥作物のすき込みや輪作による土壌理化学性の改善とバレイショの収量
- クロタラリアのすき込みによる土壌の理化学性の改善効果
沖縄本島北部では、畜産業が盛んなため飼料作物としてギニアグラスが栽培されており、一部農家では輪作体系の中でそのすき込みを取り入れている。緑肥作物のクロタラリア類(ブレビフローラ・スペクタビリス・ジュンシア)のすき込み量をイネ科飼料作物のギニアグラスと比較するとやや少ないが、3種類の中ではジュンシアのすき込み量が最も多く、気相率、可給態窒素含量がともに高まる(図1、2)。一方、サトウキビとの輪作では、気相率はあまり変わらず、土壌の物理性の改善はあまり期待できないが、輪作条件の下ではブレビフローラとスペクタビリス跡の可給態窒素がジュンシアやギニアグラス跡より高くなる。 - クロタラリアのすき込みによるバレイショ生育収量の向上効果
クロタラリアをすき込むと、ギニアグラスに比べてバレイショの収量は増加する(図3)。特に、すき込み量が多いジュンシアで最も多収となる。地上部の生育に対するすき込み効果をみると、生育初期には緑肥作物による影響は小さいが生育が進むにつれて効果が現れ、ジュンシア跡が旺盛な生育を示す。サトウキビとの輪作条件では、連作より多収となるが、緑肥すき込みを加えることによる増収効果は小さい。があり、青枯れ病の出やすい畑では耐病性のメイホウを作付けると良いことがわかってきた。一方、緑肥作物の種類や輪作体系によっても病気の現れ方が異なる。緑肥では、クロタラリア跡での青枯れ病の発生が少ない傾向がみられる(表1)。また、総合的にみると、サトウキビと輪作した場合にも病気の発生は少ない。これらの理由はまだ良く分かりませんが、青枯れ病の被害を少なくするためには、緑肥のすき込みに加えてサトウキビとの輪作を行うのが有効である。