最近、沖縄のバレイショ産地では連作圃場が多くなったため、青枯病が多発して収量・品質が著しく低下し、生産量が急激に減少している。この対策として抵抗性の品種を利用するのが効果的である。他にも輪作を行う、排水を良くする等の方法もあるが、ここでは青枯病に強い新しい品種メイホウ(昭和61年長崎県愛野支場育成)の特性と栽培法を紹介する。
1. 特性
- 青枯病抵抗性:連作圃場でも青枯病発生株率は、デジマ、ニシユタカに比べてかなり低い。収穫した上いもの青枯病罹病塊茎率もデジマ、ニシユタカに比べてきわめて低い(図1、2)。
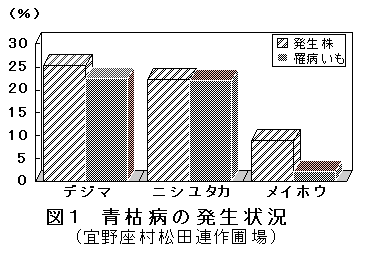
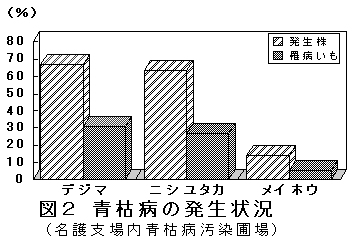
- 生育収量および塊茎の特徴:慣行品種のデジマと比べ、茎長、茎数は同程度、上いも数はほぼ同じであるが、1個重はやや小さい。L、Mサイズが多く、収量はやや低い。澱粉価は同程度である(表1)。中早生性で塊茎の揃いは中、皮色は白黄、形は楕円で目はやや浅く、表皮はやや滑らかで外観の評価は良い(表2)。
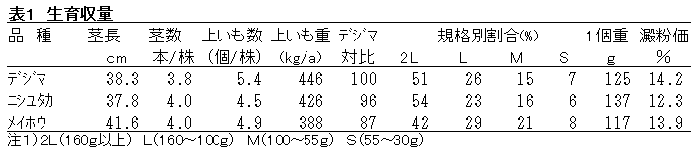
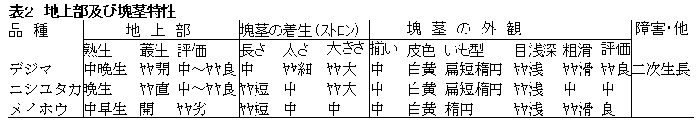
2. 栽培暦
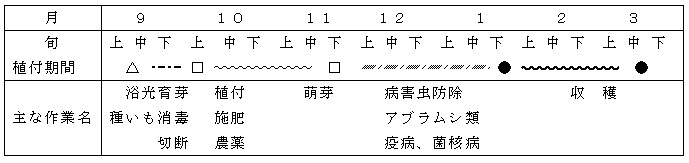
3. 種いも準備
- 種いもの量:10a当たり200~250kg、休眠の醒めた入荷種いもはすみやかに開封して腐敗いもを除き直射日光の当たらない場所に広げて浴光育芽をする。
- 消毒:芽が動き出したら切断の前に種いも消毒を十分に行う。アグリマイシン水和剤(40~100倍液)、フロンサイド水和剤(100~200倍液)で瞬間浸漬をする。
- 分割:大きい種いもは切断して重さを30g~50gに揃え、切断面の乾燥及びコルク化を促すため、1日~2日陰干しをする。
4. 定植
- ほ場の準備:排水良好で、前作にナス科作物等を栽培していない圃場を選ぶ。植え付け2週間前までに施肥、耕耘・砕土(3~4回)を済ませておく。
- 施肥:全量元肥とする。堆肥は圃場準備の時に10aあたり2~3tを全面散布する。また、バレイショ配合肥料(N:P205:K20、10:10:10)を熟畑は10a当たり120kg、普通畑は10a当たり160kg、新開地では10a当たり200kgを施用する。施用量の約80%を圃場準備の時に堆肥と同時に施用して土と混和し、残りの20%は芽出し肥料として種いも植付け溝に条施用する。
- 畝立て・マルチ:ハリガネムシやネキリムシ類の土壌害虫防除のためにダイアジノン粒剤等の殺虫剤を施用してから畦立てマルチを行う。
- 植え付け:10月上旬~11月下旬に植え、1月下旬~3月中旬の早期収穫とする。気温の高い10月植えは連作圃場で青枯病が発生し易い。栽植密度は畦幅65~75cm、株間20~25cm(7.7~5.3株/m2)の高畦とする。植え付けはプランタで伏せ込む。
5. 定植後の管理
- 一般的な管理:慣行のバレイショ栽培に準ずる。
- 病害虫防除:10日~15日に一度は薬剤散布を徹底して行う。疫病にはリドミルMZ水和剤(500~750倍)、サンドフアンM水和剤(500~750倍)、菌核病にはロブラ-ル水和剤(1000倍)、スミレックス水和剤(1000~1500倍)、そうか病対策として、有機資材の過剰施用は避け、pHを.5~4.8に保ち、種いもは必ず消毒する。青枯病にはナス科作物との連作を避け、サトウキビ等との輪作を行う。圃場の排水を良くする。ウイルス病は主にアブラムシによって媒介、伝染されるのでアブラムシの防除を徹底する。農機具や育苗箱の消毒を行う。アブラムシの防除にはDDVP乳剤(1000~2000倍)、アリルメ-ト乳剤(1000倍)、オルトラン水和剤(1000~1500倍)、ニジュウヤホシテントウにはデイプテレックス乳剤(1000倍)バイジット乳剤(1000倍)、ジャガイモガにはパダン水和剤、ビニフエ-ト乳剤(500倍)、ネキリムシ類にはダイアジノン粒剤6~9kg、ネキリトン1~3kg/10aを土壌混和あるいは散布する。
6. 収穫・調整
- 収穫:植え付け後110日をめどに葉が黄化しはじめたら収穫する。収穫はしばらく晴天が続いて土壌が乾燥したころに行う。堀取りが遅れるとマルチによって地温が上がり過ぎ、疫病や二次生長、休眠覚醒による輸送中の萌芽等の障害が出やすい。堀取り後長時間日光にあてると緑化による品質低下の原因になるので、いもの表面が乾いたら早めに収納する。
- 調整:堀取ったいもは付着している土を落とし、キズいも、罹病いも、裂果いも等を除いてコンテナに入れ、仮乾燥してから出荷する。

