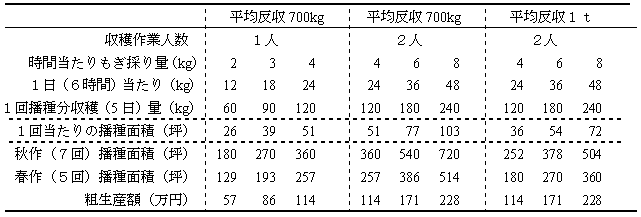1. 栽培の特徴
- 露地栽培が可能で、支柱やネット等を使用しない、簡易な栽培法である。
- 栽培管理は、播種と収穫だけで、特別な技術を必要としない。
- 収穫作業が、室内で楽な姿勢でできる。
- 雨降りでも収穫ができ、計画出荷が可能。
- 作付けをずらすことにより、面積の拡大が可能。
- 栽培期間が短いため、薬剤散布を極力抑えた、無農薬・減農薬栽培が可能。
- 商品化収量は、10aあたり1作で0.7~1トンで適期採りに劣らない。
- 基肥一発施用による畦連続使用で、低コスト省力栽培法である。
2. 栽培暦
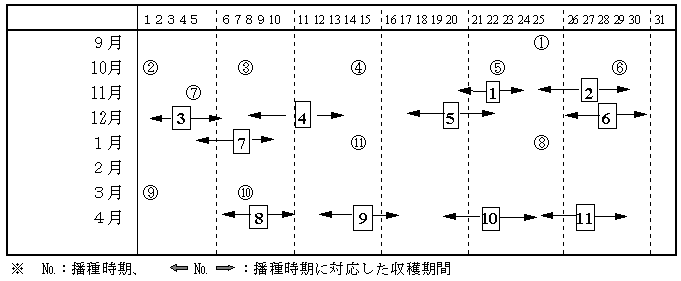
3. 品種
- ソネット
多収でサヤ色が濃く、Mサイズが殆どで莢揃いがよい。秋作には非常に適する。春作では寒さで発芽が遅れがちであるが、サビ病に強いので、後期播種には適する。開花までの日数がキセラより2~3日ほど遅く、収穫までの日数が長目。草姿が立ち葉型なので、莢のもぎとりが楽。 - ベストクロップキセラ
ソネットには及ばないが、比較的多収で、市場評価が高い。寒さに強いので春作に適する。さび病に弱いので初期播種に適する。
4. 圃場の準備
- 酸度矯正
酸性土壌の場合、以下の資材を良く混和し酸度を矯正する。pH5以下:750kg/10aの炭カルまたは1t/10aの苦土石灰、pH5以上:500kg/10aの炭カルまたは750kg/10aの苦土石灰を施用する。また、堆肥を10a当たり2.5トン施用して耕耘・混和する。 - 施肥
元肥としてまとめどりインゲン肥料(被覆尿素入複合肥料140日タイプ:15-10-10)を、10a当たり240kg(12袋)を全面施用し、再度耕耘・混和する。 - マルチ
全面マルチャーを用いて畦巾5cmの畦立てとマルチングを同時に行う。
5. 播種
- 秋作(播種期間:9月下旬~11月上旬)
株間25cmの植え穴を開け、潅水する。植え穴に一穴3~5粒の種子を浅めに蒔き、軽く覆土する。間引きは必要ない。 - 春作(播種期間:1月下旬~2月下旬)
秋作収穫後の植え穴をそのまま利用する。施肥は必要としない。植え穴に適度な湿りをもたせるように、潅水する。植え穴に一穴3~5粒の種子を浅めに蒔き、軽く覆土する。間引きは必要ない。
6. 病害虫防除
播種前にカタツムリ対策としてマイマイペレットや安全スネック等を、圃場周辺および植え穴に散布する。秋作の早い時期の播種で疫病がみられることがあるので、予防策として、畦を高く立て排水性を良くし、過湿を避ける。春作の遅い播種でサビ病がみられることがある。被害がひどい場合はバイレトン水和剤5の1000倍液や、ジネブ水和剤の500倍液を散布する。
7. 収穫
7~8割の株が開花した日から20~24日目頃に、株ごと抜き取る。または、地際から切り取り、莢のもぎ取り作業をする場所へ運ぶ。
播種から収穫までの日数は、ソネットで秋59日、春75日、キセラで秋58日、春72日である。
8. 調整
極端な曲果・病害虫被害果等を除く、A・B品莢実をハサミで切り落とす。莢実を切り落とす前に、葉を除去しておくと作業効率が良い。果柄部を揃えて共選へ。
9. 注意事項
- 過繁茂に注意(多肥を避ける)し、草丈は50cm程度に抑える。
- 収量の確保と高品質維持のため、収穫は開花後20日以上25日未満を厳守する。
- 硬い莢の混入を防ぐために、共選においてはM莢の100本重を守るよう心がける。[100本重のめやすはソネットで300g、キセラで375g]
- 収穫適期を過ぎた莢はランクを下げ、品質のチェックを厳しくする。
- 収穫能力により、1回当たりの播種面積を決め、計画播種・出荷をめざす。
10. 収穫能力に応じた播種面積とその収益性