新里さんは農業委員を退職後、本人と母親(85歳)の2人(サトウキビは作業委託)で、サトウキビ(1,000坪)、キャベツ(500坪)、マンゴー(ハウス200坪)、露地わい性サヤインゲン(150坪)を栽培している。インゲンは10年ほど前までは両親とサーベルを栽培していたが、その後5年間は適期収穫摘みの作業が困難で、栽培を止めていた。5年前から露地での一斉収穫栽培を試みている。
1. 作型
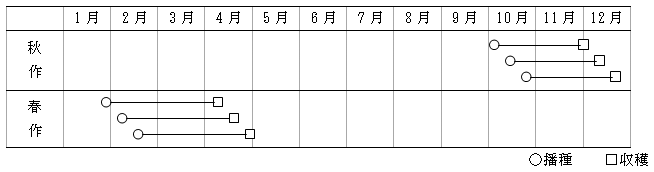
2. 栽培法
- 土つくり
土壌は沖縄本島北部に広く分布する国頭マージと呼ばれる細粒赤黄色土で、土性は重粘質である。pHは5.3程度と酸性ではあるが、酸度矯正は特に行っていない。初年度は堆肥を施用し過繁茂となったため、以降堆肥の施用はひかえている。 - 防風垣
密植により倒伏を防いでいるが、風速12m/秒以上の季節風では被害が出るため春作では防風垣を風上に設置している(2mmメッシュの防風ネットを建築用足場パイプ2-2.5mスパンの支柱に1.8mの高さで張り巡らす)。 - 栽植様式
畦幅45cm、株間27cmの1条植え。栽植密度としては10a当たり16,460株である。保温・保湿・雑草防除のためマルチを掛けるが、土の跳ね返りを避けるため全面マルチである。 - 品種
栽培開始当初は当時主流だったライトグリーンやサーベルを用いたが、ライトグリーンは莢実の色が薄く商品性が低いため、サーベルは収量性が低いため、農業試験場の試験結果で有望とされたソネット、ベストクロップキセラに変えている。 - 施肥
秋作播種前に複合LPコート(140日タイプ、緩効率50%、窒素:リン酸:カリ=15:5:15)を150坪当たり125kg全層施用し、春作収穫まで追肥を行わない(2作全量基肥体系)。 - 潅水
播種前にマルチ内水分を適度に保つようにかん水しておく。その後は、極度の乾燥時にかん水する他は降雨にまかせている。 - 播種
秋作では10月上旬から1週間おきに、50坪ずつ3回播種。春作は1月下旬から1週間おきに50坪ずつ3回播種。1穴当たり3粒を蒔き、間引きはしない。 - 病害虫防除
播種前に圃場周辺と植え穴にマイマイペレットを施粒する。カタツムリが多いので、生育途中に追施する場合もある。カタツムリ対策以外は今のところ必要ない。
3. 収穫・調整
収穫は地際から刈り取り、家に運び莢を鋏で切り離す。1日に1回刈り取るが、量として半日で調整できるだけの株(20坪程度、圃場と家の往復時間込みで約1時間)を刈り取っている。
4. 出荷
地産地消を経営方針としているので、出荷先は地元の直売店である。荷姿は220g入りビニール袋詰めで、A品・B品混包である。
5. 一斉収穫栽培を経験して
農薬の使用も非常に少なくて済み、追肥も必要ないので管理が楽である。収穫・調整作業が楽で、高齢の母親でも難なくでき、今後も続けたい。定植から収穫まで1月以上かかるゴーヤーとの混作も考えている。



