ユーチャリスは熱帯原産のヒガンバナ科の球根植物である。沖縄は冬期が温暖で、夏の高温期の最高温度は比較的低く生育に適している。沖縄では寒冷紗ハウス内で栽培され、初冬から早春にかけて出荷される。この花は結婚式で花嫁が持つブーケやコサ-ジュの素材として人気があるが、現在の栽培法では、需要期の結婚式シーズンの開花が少なく、市場の要求に応えられていない。需要に応えられる生産体系を確立することが必要である。
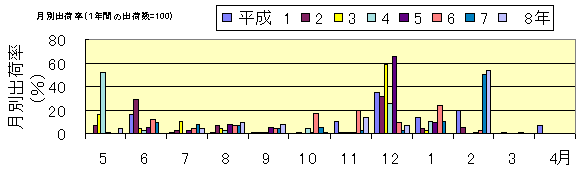
切り花月別出荷量の年変化
1. 生育開花習性
ユーチャリスは、夏期に球根が充実し、自然条件では10月頃摂氏20度程度の低温に感応して花芽を分化し、約2~3ヶ月後から開花するために12月から3月に開花のピークを迎える。また十分に充実した球根は、1週間前後気温が摂氏25度以下に低下すると花芽を分化し散発的に開花することがある。しかし、開花は球根充実の程度と、気温の低下の程度によって影響されるために年による変動が大きく、目的とする時期に確実に採花できる技術が必要である。
2. 採花型
ユーチャリスは温度条件を制御することにより採花期を選択できる。
- 12月~3月採花
寒冷紗ハウスで無加温・無冷房での採花。球根の充実程度、夏の暑さで開花盛期は変わる。 - 4月~6月採花
秋冬期摂氏25度加温による抑制栽培。秋冬期の自然の低温で花芽分化を始める前に摂氏25度以上に加温し、花芽分化を抑えることによって翌年春期から初夏に開花させる。 - 7月~9月採花
高温や低温処理を組み合わせた超促成栽培。4~5月の高温後の梅雨期の低温による自然開花もあるが、4月~6月にかけて、高温処理と低温処理を組み合わせて花芽分化を促進し、確実に夏から初秋に開花させる。 - 9月~10月採花
低温処理による促成栽培。7月ごろまでの初夏の高温を受けて充実してきた株を摂氏20度前後で低温処理し、処理後80~90日後に開花させる。 - 11月採花
晩夏の低温時に花芽を分化して開花する。多数開花する年もあるが、夏が暑いと少なくなる。8月下旬からの低温処理は逆効果の場合もある。
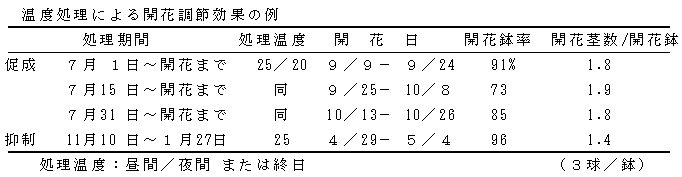
3.需要期に合わせた生産技術
- 促成栽培(秋の結婚シーズン向け)
初夏の高温を受け十分に充実した球根に、7月初旬から摂氏20度程度で出蕾まで約2ヶ月間低温処理を行うと9月中旬から10月に採花できる。- 株の充実
沖縄では7月上旬までに株が春~初夏の高温によって充実するので、この時期から低温処理が行える。これより早い時期では、高温遭遇が少ないために、充実不足の球根が多くなり、採花率が低下する。 - 低温処理
処理は摂氏18~20度で終日行う。充実が進んでいる球根を使用すると、昼/夜温摂氏25/20度の変温処理や、摂氏23度処理の処理でも効果があるが、充実の程度は把握できないので摂氏20度以下での処理が無難である。処理は花茎が確認されるまで行う。処理温度が低いほど開花までの日数を必要とする。 - 簡易低温処理装置
- 冷房: 冷房温度が摂氏20度程度であるので、家庭用のエアコンを安価に利用できる。冷房機の能力はm2当たり消費電力200w程度の能力がある機種でよい。施設の高さを低くして冷房体積を減らすとともに、入射光の抑制や保温資材を活用することなどにより、エネルギーロスを防ぐ。冷房の際の廃熱は他の作型の高温処理に利用できる。
- 光環境: 1mm目寒冷紗ハウス(光透過率28%)の中にさらにサニーコート(2層保温資材光透過率80%)+ピアレスフィルム(反射断熱資材透過率35%)で作った内部への光透過率が屋外の10%弱の簡易冷房施設で対応できる。
- 換気: 昼間に植物は光合成を行っているので、換気による炭酸ガスの補給が必要である。土壌に施用した有機物からも補給される。
- 低温処理法
- 地植えした株への低温処理
地植えした株に冷房施設を移動して処理する。鉢の管理と移動労力が緩和されるが、採花茎数を増加させるために、栽植密度を計画的に高めておく。小規模な施設を数施設作り、処理時期を変えて計画出荷する場合に向く。室温を冷やす変わりに地中の株下に塩ビ管等を配管し、その中に摂氏5度の冷却水を循環させて、地温を下げる地温冷却法もある。 - 鉢植えした株への低温処理
鉢に植えて育てたものを低温処理室へ搬入する方法で施設の利用度を高めることができる。採花が済んだ鉢は、そのまま、あるいは一周り大きめの鉢に鉢上げし、翌年の処理に利用する。前回開花してからの期間が長い株のほうが充実度が高い。採花後に葉が1枚増える養成期間をおくと次の処理に利用できるが、採花率は低下する。
- 地植えした株への低温処理
- 病害防除
白絹病の予防に、リゾレックス等を灌注する。
- 株の充実
- 7~9月向けの超促成栽培
株を摂氏32度2週間の短期間の高温処理後、摂氏18度で低温処理することで斉一に花芽が分化する。
高温処理にはビニルフィルムで覆った施設内で温風暖房機等を使い、最低気温摂氏25度を目標として、低温処理日まで2週間暖房する。室温が摂氏30度以上になったら換気扇あるいは側窓の開閉で換気する。ビニルフィルムを張ったハウス内のトンネルは黒1mm防風ネットで覆って遮光する。その後、促成栽培と同様に低温処理を行う。冷房廃熱を高温処理のために活用することもできる。 - 抑制栽培(春の結婚式シーズン向け)
摂氏25度以上の温度では花芽分化が抑えられる。この性質を利用して、10月初旬から目的とする開花時期の2~3ヶ月前まで最低気温摂氏25度の温度で管理して、花芽分化を遅らせる。1月下旬以降に暖房を止めると、自然低温で花芽を形成し、4月下旬~6月に開花する。暖房停止時期の調節で採花時期を制御することができる。
高温処理にはビニル等を利用した被覆内で温風暖房機等を使い、最低気温摂氏25度で管理する。室温が摂氏30度以上になったら換気扇、あるいは側窓の開閉で換気する。黒1mm防風ネットで覆って遮光する。
晩夏~初秋期に摂氏20度程度の低温に遭遇すると花芽が形成され、高温処理によって早期に開花してしまう個体がある。防ぐ必要がある場合には加温開始時期を早くする。12月上旬までは平均気温が高いので、暖房コストは少ない。
4. 人工的な開花調節に向けた株の養成
人工的な環境でエネルギーを使った冷暖房で開花調節を行うので、採花率を高めるために、球根を十分に養成する必要がある。
ユーチャリスは熱帯球根であり、わずかの環境の変化で開花する。1つの球根が年に数回開花することもあるが、目的とする時期以外の開花や分球による消耗が伴うので、処理時に全部の球根を開花させることは難しい。
- 親株の養成
処理に利用する球根を得るための親株を準備することが必要である。
地床に元肥として窒素成分で20Kg/10aを施用し、90~100cm幅のベッドに3条植、株間30cm程度に1球づつ植え付ける。植え付け適期は初夏ごろである。自然環境で数年間採花を行いながら、分球を待ち、処理用の球根を養成する。 - 開花調節のための球根の鉢上げ
- 使用容器と鉢用土
開花調節処理装置への搬出入のためには鉢やプランターで株を養成しておく。7号ポリ鉢や60cmプランターが適当である。植え付け適期は初夏ごろである。鉢用土は通気性と軽量化を図るために、1/4量程度の堆肥をいれて堆積しておいた培土に1/4程度のピート等を混合して使う。酸性が強いときは苦土石灰などを用いてpH6前後に調整する。 - 球根植え付け
分球が進んだ親株を分球し、葉を除く。球根の直径が5cm以上の球根を選んで鉢当たり3~4球植え付ける。60cmプランターの場合は10球程度とする。 - 株の養成期間
鉢上げから処理まで1年程度の期間を取り、少なくとも1球根から3~4枚以上の出葉を待つ。なお処理株が急に入り用の場合、4月に地床から掘り上げて直径が6cm以上の特に大きな球根を選び、側球を外して、葉・根を付けたまま、鉢上げして養成すれば、7月からの低温処理に対応できる。 - 鉢上げ後の水管理、追肥
過度の乾燥を避ける。1鉢(7号鉢)当たり被覆緩効性肥料やIB化成の大粒を5g程度を植え付け後に施用する。必要に応じて窒素有濃度で100ppm程度の複合液肥を施す。 - 遮光処理
育苗中は黒1mm目の防風ネットで覆って75%程度の遮光を行う。 - 温度条件
摂氏25度以上の環境で管理すれば、生育速度が増すとともに、不時開花が少なくなり、採花率が向上できる。しかし、コストがかかるので、一般には自然環境で対応する。
- 使用容器と鉢用土
- 株の充実
自然環境では摂氏25度以上が球根の充実に有効な温度域である。球根の充実は終日約摂氏30度で1ヶ月程度管理すると早まる。また、高温が不足する(摂氏25度以下)時期や前回開花した後で球根が充実不足の場合、摂氏32度2週間の高温処理と行うと充実が促される。
なお、11月採花を目的として低温処理を8月下旬から行った試験で採花率が0に近かったことから、夏に長期間高温期間が継続すると花芽分化がしにくくなるようである。

寒冷紗ハウス内で養成中の鉢上げ株

鉢上げ2年後の株内球根の状態
※6月に掘りあげた球根を1鉢に3球づつ定植し、次回翌年7月の低温処理開始まで養成中の株。株の養成が採花率を高める上で重要な作業である。
※植え付けた親球の外に、子球、孫球の分化が見られるが、小球の開花は期待できない。

