山内さんは、観葉植物の価格低下を補填する意味で、ユーチャリスの導入を行いましたが、開花時期が高価格となる需要時期と合い難く、収入はあまり期待できませんでした。そこで、低温処理装置を導入し、促成栽培による需要期の出荷技術の開発を試みることになりました。
1. 株の養成
6月に掘りあげた球根を1鉢に3球づつ定植し、翌年7月の低温処理開始まで養成。植え付けた親球の外に分化した子球、孫球については開花が期待できないので、母球の充実を図ることが重要。
2. 自作した簡易低温処理装置
1mm目寒冷紗ハウス(透過率28%)内に10%弱の光を通す小ハウス(10m2)を設け、これをサニーコート(2層保温資材透過率80%)+ピアレスフィルム(反射断熱資材透過率35%)で被覆して低温処理用ハウスとした。冷房には消費電力800wの家庭用エアコン4台を用いた。この装置で7号鉢400鉢1200球相当が処理可能。消費電力は7月23日~9月2ヶ月弱で1100kw/h程度。

鉢植え株処理用の処理装置

地床植株用の処理装置(採花終了後の骨組)
3. 低温処理効果
2000年と2001年には処理を行った区のそれぞれ31%、39%の鉢が平均1.5本開花した。2002年には透過率28%の寒冷紗ハウス内の地床に定植されていた株に小型トンネルを被せ、保温被覆材のサニーコートを2枚重ねて覆い、窓用の可搬型クーラ(消費電力790w・使用電力量378.5kwh)を設置して冷房処理を7月23日~9月1日まで行った結果、約5m2の地床に植えた定植5年後の40株から120本が9月下旬に採花できました。
一方、2002年6月に、前年使用株を一回り大きな鉢に移植して低温処理した場合の採花率は19%、その採花本数は1.2本であった。これは株の充実不足と台風時の停電による冷房の一時中断の影響である。
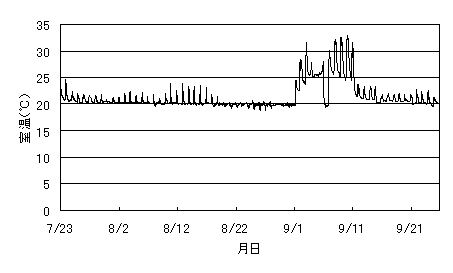
低温処理装置内の温度環境(2002年度)
(9月上旬の高温は台風時の停電による)
4. ユーチャリス導入に当たっての留意点
農協を通して、4月下旬、9月下旬に開花した切り花を東京市場に出荷したところ、期待に外れ、高価格では取り引きされず、逆に、沖縄県内出荷の方が高価格で取引された。この花は結婚式と結び付いた需要であるために、買い手との接触のもとで売買する必要がある。有利な経営をするには、客の需要に応えられる関係、すなわち、いつでも物があり、需要に応えられる生産体制を個人あるいは沖縄県の生産者団体が共同で確立しておくことが生産性の向上のために必要である。

