沖縄では冬季も温暖なため、電照やジベレリン処理、暖房は必要とせず、簡易な雨よけハウスでイチゴ栽培が可能である。ハウス側面は常時(雨天や強風時以外)開放しておくが、害虫の侵入を防ぐための防虫ネットを張る。促成栽培のためには、適切な花芽分化処理が肝要である。
1. 栽培暦
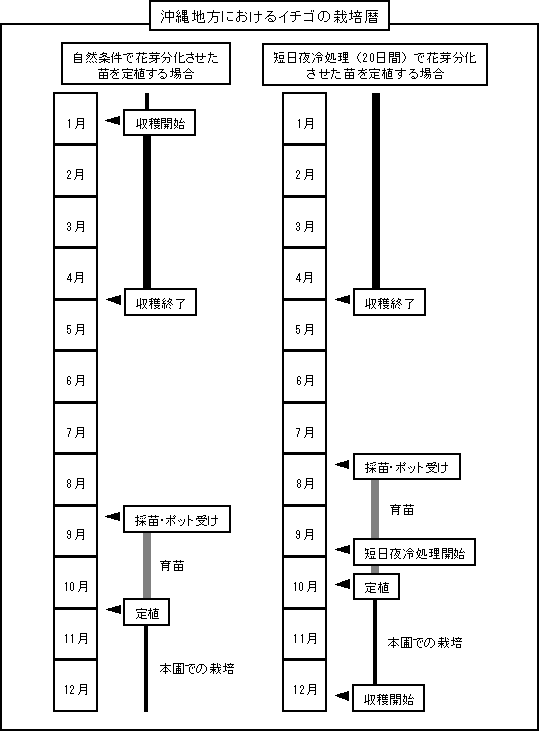
2. 品種
さちのか
3. 育苗
前項「沖縄に適した品種と苗作り」参照
4. 花芽分化
イチゴは低温・短日条件に感応して花芽分化する。花芽分化は頂果房から始まり、第1次、第2次と腋果房の分化が続く。
年内から収穫を開始するためには、育苗期間中に短日夜冷処理(花芽分化処理)を行い、花芽分化した苗を定植する。年明けから収穫するのであれば自然分化苗でよい。

写真1 短日夜冷装置
(沖縄県農業試験場園芸支場)
- 自然分化
沖縄の自然条件では、頂果房は10月20日ころ、第1次腋果房は11月初めころ分化する。 - 短日夜冷処理
短日夜冷処理までにクラウン径10mm以上の充実した苗に育てておく。定植する前20~40日間8時間日長・夜温摂氏15度で管理すると花芽分化が誘導される。例えば、夕方5時に夜冷庫に入れて翌朝9時に出庫する。写真1のような簡易な装置が利用できる。
10月中旬に定植する場合、20日間の短日夜冷処理を行うと、頂果房が分化する。40日間の短日夜冷処理を行うと、第1次腋果房まで分化する。
定植時には実態顕微鏡(25~100倍)を用いて花芽分化を確認するのが望ましい。
5. 収穫
 写真2 イチゴの試験栽培
写真2 イチゴの試験栽培
(沖縄県農業試験場園芸支場)
開花後1ヶ月で収穫できる。温度が高くなりと開花から収穫までの期間が短くなる。12月中旬から4月までの収穫で400g/株程度の収量が見込める。
早期収穫をねらって頂果房の花芽分化を早めると、次の第1次腋果房の収穫が始まるまでの時間差が大きくなり、その間の収量が低下する。

