1. 発生する病害と特徴
- 沖縄県で特に問題になる病害は、炭疽病、うどんこ病、萎黄病、疫病であり、九州以北と同じである。この他には菌核病と灰色かび病の発生が認められる(図1、2、3)。
- 炭疽病と萎黄病は、罹病株が1、2月の低温期であっても枯死するため、育苗期に十分防除しなければならない。
- 炭疽病はランナーや葉柄に発生しやすく、紡錘形の黒褐色の浅く陥没した病斑を生じる。やがて鮭肉色の胞子塊を生じ、胞子により周囲の株にも感染する。クラウン部には外側から内部に向かって赤褐色の病変が生じ、維管束が犯されるため、葉が奇形症状を呈する。
- 萎黄病も葉が奇形症状を呈する。奇形症状で萎黄病と炭疽病を区別することは難しいが、クラウン部の病変部が外側から中心部へ向かって広がっているものは炭疽病、維管束のみに赤褐変が認められるものは萎黄病と判定できる。
- 疫病はクラウン部に炭疽病と類似した症状を生ずる。

図1 育苗期に発生したイチゴ炭疽病
三複葉の1、2枚が小型化した奇形症状

図2 本圃で発生したイチゴ萎黄病
三複葉の1、2枚が小型化した奇形症状

図3 果実に発生したイチゴうどんこ病
2. 防除対策の要点
- 二段階採苗技術を利用する
一次及び二次親株養成期に炭疽病、萎黄病、疫病の徹底防除を図る。 - 一次親株と二次親株をポット育苗する
奇形症状や下葉の萎凋を呈した発病株は廃棄して焼却する。 - 炭疽病防除
雨よけ育苗、ミストまたはドリップ灌水、薬剤による総合防除が必要である。また、葉柄またはランナーに病斑が出現した場合は、薬剤防除を徹底し、他の苗への病原菌の飛散を防ぐ。 - うどんこ病防除
下葉かき、ランナー取りを十分行って、薬剤がかかりやすい状態に株を管理して薬剤で防除する。 - 株の管理
下葉かき、ランナー取りを十分行わないと、薬剤防除の効果は上がらない。初期防除が大切であり、株の観察を欠かさず、病斑を発見したら直ちに薬剤防除を開始する。 - 萎黄病の拡散を防止
健全親株を配布する。萎黄病が発生した畑では燻蒸剤または太陽熱により土壌消毒する。
3. 年間防除体系
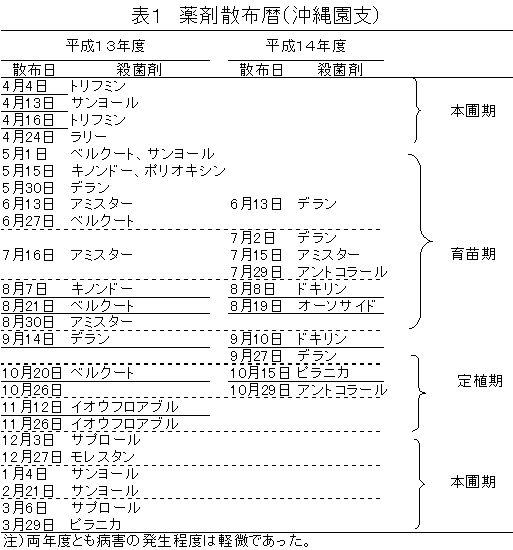
※最新の使用薬剤については農業試験場または普及センター等に確認する

