国内唯一の未発生地域"沖縄"の「ミカンキイロアザミウマ・フリー」を持続させよう!!
ミカンキイロアザミウマ
学名: Frankliniella occidentalis (Pergande)
英名: Western flower thrips
1. 分布
アメリカ西部原産、温室花き類や果樹などの害虫であった。1970年代から80年代にヨーロッパなどへ分布を拡大し、現在では、南北アメリカを始めとして西欧から北欧、ロシア、韓国、ニュージーランドなど世界中に分布を拡大し続けている。
我が国では1990年に千葉県、埼玉県のシクラメンやガーベラなどで初確認されて以来、発生地域は拡大し、1996年には沖縄県を除く全ての都道府県で発生している。
2. 被害
花を特に好み、激しい被害痕を残すため恐れられており、寄主範囲は、花き類、野菜類、果樹類、野草・雑草など200種以上にも及ぶ。
加害により、トマトやブドウなどでは「白ぶくれ症」、イチゴでは着色異常、他の果菜類でもカスリ症状などを呈し商品価値をなくす。果樹では、多くの種類の果実に「まだら症状」を出し商品価値を低下させる。
さらに、トマト黄化えそウイルス(TSWV)を高率で媒介し、特にナス科、キク科、マメ科、ウリ科などで激しい被害を出すため、施設の野菜や花き類の重要害虫となっている。
本種は各種の殺虫剤に対して非常に抵抗力が強く、防除が困難な害虫である。

キク圃場における被害状況
(一畝全面が枯れあがる、急激な被害拡大がミカンキイロアザミウマの被害の特徴)


花弁のカスリ状被害痕(右:スプレーギク、左:ニチニチソウ)
3. 沖縄県内の発生経過
沖縄県では、1999年と2002年に侵入が確認されたが、いずれも迅速な徹底防除に務めた結果、現在は新たな発生は認められていない。
4. 今後の対策
本県では、キク類やトマト等の生産が着実に拡大しつつある。また、新規品目としてイチゴの導入が試みられ、本格的な栽培が始まろうとしている。これらの生産において、ミカンキイロアザミウマは、かつてのミナミキイロアザミウマやマメハモグリバエ以上の脅威である。さいわい現状では定着蔓延は阻止されているが、常に侵入の危険にさらされている。特に、沖縄県以外の地域からの花き類や野菜類の苗の移入に際しては、現地での消毒を徹底するなどの侵入予防措置を講ずる必要がある。
5. 主な防除薬剤
(農薬施用に当たっては、適用作物、使用基準を遵守して使用する。)
スピノエース顆粒水和剤、アファーム乳剤、コテツフロアブル、トクチオン乳剤、DDVP乳剤、モスピラン水溶剤、アーデント水和剤など幼虫:IGR系(カスケード乳剤、アタブロン乳剤、マッチ乳剤)
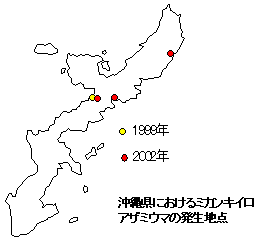
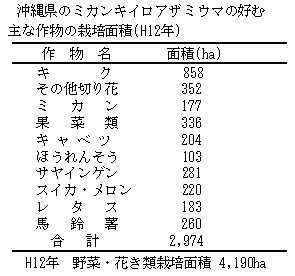

左からミナミキイロアザミウマ、
ヒラズハナアザミウマ、
ミカンキイロアザミウマ
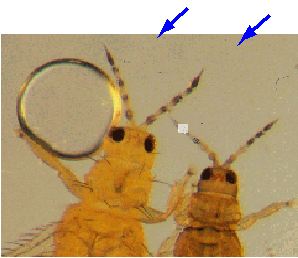
ミカンキイロアザミウマ
複眼後方の刺毛の有無がポイント
左: ミカンキイロアザミウマ、右: ヒラズハナアザミウマ)

