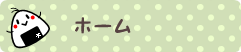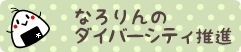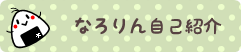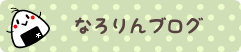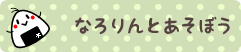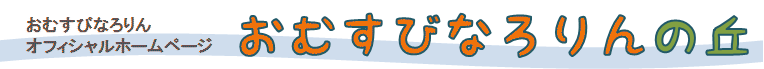

なろりん、熱研(ねっけん)くんと会う! の巻
お天気: くもりときどき雨
こんにちは なろりんです♪
気の向くままに全国にある農研機構の研究センターを巡って紹介しています。
80回目のなろりんリポート、略して「なろリポ」です。
今回は番外編!
農研機構から外にお出かけして、「国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(国際農研)熱帯・島嶼研究拠点」を訪ねました。
「国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター」は農林水産業研究分野での国際的な貢献と連携の中心的な役割を担っていて、茨城県つくば市に本所があるよ。
こちらの「熱帯・島嶼研究拠点」は沖縄県石垣市(石垣島)にあって、「熱研(ねっけん)」の愛称で石垣島のみなさんに親しまれているんだって。

やってきました。熱研(ねっけん)!
石垣島は12月とは思えないくらい暖かいよ。本日の気温は26°C!

正門にはヤエヤマヤシ並木♪
熱研は国内で唯一の亜熱帯の環境にある国立研究開発法人の農業研究拠点なのだそう。
こちらの気候条件や地理的条件を活かして、熱帯・亜熱帯の開発途上地域に活用できる農業技術の研究開発に取り組んでいるんだって。
海外に向けた研究の他にも、国内農業への貢献としても重要な役割を担っているよ。
案内されたお部屋に入ると、熱研のキャラクター「ねっけんくん」がお出迎え。

おーりとーり!
ねっけんくんは、ヤシの実の形をした農業の妖精。
「おーりとーり」は、石垣島の方言で「ようこそ、いらっしゃい」って意味なんだって。
歓迎してくれてありがとう♪
「熱研のお仕事について、それぞれの担当者が紹介するよ!」とねっけんくん。
今回、1) インド型イネ開発研究、2) イネやコムギの世代促進、3) 熱帯作物の遺伝資源の保存・管理、4) 主に南西諸島に向けた農作物の品種育成、5) サトウキビの交配、について紹介してもらうよ。たくさんお話が聴けてうれしいな!

よろしくお願いします♪
まずはじめに、1) インド型イネ開発研究 についてお話を聴いたよ!
熱帯・亜熱帯では、主にインド型イネ品種が栽培されているんだって。
でも、開発途上地域の多くでは、農作業そのものの道具がなかったり、水田ではなく畑のやり方で稲作をしたりしているところもあったり、あまりたくさんお米がとれないんだって。
石垣島にある熱研は、これらの開発途上地域と似た熱帯・亜熱帯の環境なので、インド型イネの栽培や育種ができるのだそう。
開発途上地域で起こっているイネの問題を解決するため、海外との共同研究を通じてイネ遺伝資源や育種素材を集めて調査していて、よりよい品種を作り、調査でわかった情報や新しい品種になるための素材を提供しているんだって。
「海外からいただいた遺伝資源をさらにいいものにして返していくことが大切」なのだそう。
「施設などのサポートはもちろんのこと、国際農研が取り組んでいる育種のプロジェクトでは、海外の研究者を受け入れて一緒に研究調査をして、技術やノウハウを学んでもらうなど、人材育成のサポートをすることも重要なポイントのひとつかな」と話していたよ。
また、国内に向けての研究として、熱帯地域で栽培されているインド型米を国産化して、沖縄県の地酒の泡盛を作れないか試しているそうだよ。他にも、内閣府のプロジェクトになっている事業もあり、支援しているのだそう。
海外から導入した材料の中に、たくさん収穫できるタイ産のインド型イネの品種があって、それを沖縄で栽培して泡盛の生産に使えないかな、と思ったんだって。
泡盛は現在、タイから輸入したお米を100%使っていて、それを沖縄で生産したお米にかえることで、安心・安全の付加価値を付けることができ、沖縄の地域産業の活性化にもなるのではないかと、地元の造り酒屋さんと協力して、泡盛を試作したのだそう。

紹介してくれた研究者さんと。
試作した3種類の泡盛もいっしょに♪
いつか国産米を使った泡盛がたくさんお店に並ぶ日がくるかも?! 楽しみだね♪
次は、2) イネやコムギの世代促進 について。
案内してもらってやってきたのは、細かく区切られた田んぼ。
石垣島は暖かいから、1年間に2回、種まき~収穫することができるのだそう。
11月下旬に2回目の稲刈りが終わって、今は何もない状態だったよ。

「世代促進」ってどういうこと?
新しい品種を作るには、交配させた種を育てて収穫した中からより良いものを選抜し、そしてその選抜した種を育てて収穫してさらに選抜して...を何度も繰り返すよ。
そうやってたくさんの世代を重ねる必要があるため、新しい品種が誕生するまでに、10年以上の長い年月がかかるのだそう。
普通の栽培方式だと年に1回収穫するので1世代進むよ。
こちらでは年に2回収穫して世代が1年で2つ進むから、その分早く選抜を進めることができる。これが「世代促進」ということなんだって。
実は、農研機構で育成している品種の種子もこちらに送って育ててもらっているのだそう。
今年は150点くらいの種類を育ててもらったんだって。
研究センターの地域ごと種類ごとに分けて少量ずつ植えるから、種まきから収穫までの作業は田植機やコンバインなどの機械を使わず、すべて手作業なのだそう。とても手をかけて育ててもらっているんだね。
農研機構の研究を支えてもらっています!

なろりんも支えてもらっています♪
次は、3) 熱帯作物の遺伝資源の保存・管理 について。
熱研は、農研機構遺伝資源センターが実施している「農業生物資源ジーンバンク事業」の熱帯・亜熱帯作物サブバンクにもなっていて、遺伝資源として熱帯作物を育てて保存・管理しているよ。
作り続けて残していく、という大切なお仕事だね。
こちらでは主にサトウキビなど(約530点)、パインアップルなど(120点)、熱帯果樹など(約150点)を育てているのだそう。種類の多さにビックリ!
ハウスの中ではいろんな種類の熱帯果樹が育てられているけど、今の時期はほとんど実も花もない状態...。

実がなる6~8月が一番見頃なのだそう

実際に育てている熱帯果物の模型

ひろ~いパインアップル畑♪

農研機構が育成したサトウキビも保存しているよ
それから、熱研が遺伝資源や研究材料として独自で持っているのが、マンゴーのコレクション。62品種もあるのだそう。
国際農研の「マンゴー遺伝資源サイト」は、楽しい情報がたくさん♪
次は、4) 主に南西諸島に向けた農作物の品種育成 について。
これまでに、パインアップル、パパイヤ、パッションフルーツの品種育成をしてきたんだって。
2019年に品種登録されたパッションフルーツの新品種「サニーシャイン」は、今までのパッションフルーツと比べて酸味が少なく食べやすいと評判♪
これまでのパッションフルーツは、収穫直後は酸っぱくて食べにくいのでしばらく置いて追熟させるよ。表面がシワシワになった頃が食べ頃なのだそう。
「サニーシャイン」は収穫直後でも酸っぱくなくて、すでに食べ頃なので、表面がツヤツヤのキレイな状態で食べることができるんだって。食べてみたくなるね!
「サニーシャイン」の情報はこちらから。
今回は、新たに育成中のパッションフルーツを見せてもらったよ。

赤くなっている実を発見!
パッションフルーツは暑すぎると高温障害を起こして花が落ちてしまうので、生産・出荷時期が限られているのだそう。
そこで、暑くなっても安定して花が咲き、今よりも長い期間生産・出荷できるような品種が作れないか調査しているんだって。
農家さんに喜んでもらえるようなパッションフルーツを作りたい、と話してくれたよ!

新しい品種の誕生を楽しみにしています♪
最後は、5) サトウキビの交配 について。
こちらがサトウキビの花。
ススキのような穂が、サトウキビの花なんだって。

12月に花が咲くんだね!
よりよいものを選抜して交配させ、新しい品種を作るよ。
選抜の基準は、糖度、収穫量、茎の丈夫さなどさまざまで、ここに植えてあるサトウキビ1本1本の長さや太さを全部測るんだって!! 気が遠くなりそう~。
この畑ではポールを立ててロープを張って、サトウキビがまっすぐ伸びるように支えていたよ。こうすることで他の茎と比べて選抜しやすいし、台風対策でもあるんだって。

まっすぐ伸びていて調査しやすそうだね!
こちらは、エリアンサスという植物。
エリアンサスは、サトウキビと近縁(近縁属植物)なので、お互いを交配させて今までにない新しいサトウキビ品種をつくることができるんだって。

ピンクの花がきれい♪
エリアンサスは根っこがとても深いので、海外の乾燥地帯でもしっかり育つのだそう。
そこでサトウキビと交配したら乾燥に強いサトウキビができるのではないか?と調査中。
ほかにも、収穫量だったり糖度が高いものだったり、国によって求められる品種は違うんだって。
ちょうどサトウキビの交配作業中ということで、交配施設も見学させてもらったよ!
建物の中には、長細い小さな部屋がたくさんあるよ。

キリンさんのお部屋みたい!
この中に交配させたいお父さんサトウキビ、お母さんサトウキビをペアで入れて交配させるよ。
自然界では風が吹いて受粉するのだけど、ここは屋内なので、お父さんサトウキビをトントントンと揺らして花粉を落とし、少し下に置いたお母さんサトウキビの花にふりかけて受粉させるんだって。
受粉させたお母さんサトウキビの花(穂)には袋をかけるよ。

袋の中で受粉させた種が育つよ
実は、この施設で交配作業をしていたのは、農研機構九州沖縄農業研究センター種子島研究拠点のさとうきび育種グループのみなさん。
以前ブログで訪ねた時(なろりん、南の島の研究拠点を訪ねる の巻)、「種子島はサトウキビにとって寒くて花が咲かないから、石垣島に行って交配作業をしている」って言っていたよね。
それはここ、熱研のことだったんだね!!
熱研の技術支援室のみなさんのサポートのおかげで、交配作業ができるのだと話していたよ。

熱研の技術支援室の方(向かって左側)と、
農研機構の二人と一緒に♪
熱研では、この他にもさまざまな研究をおこなっているよ。
まだ知らないワクワクがたくさんありそう!
ぜひ国際農研のホームページをチェックしてみてね。
いろんなお話を聴けて、ねっけんくんにも会えて、大満足ななろりんなのでした。
次はどこの研究センターへいこうかな。お楽しみに♪
●「国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター(国際農研)」の詳細は、ホームページ 【外部リンク】を見てね。
おまけ

青い海、青い空♪