1. 開国と茶業
茶は、幕末の1860年代に初めて輸出され、明治に入ってからは、国内生産量の70~80%を主としてアメリカやカナダに輸出するようになり、生糸と並んで重要な輸出産品となりました。戦前(太平洋戦争)までは生産量の30~40%を輸出していました。
2. 品種と栽培技術
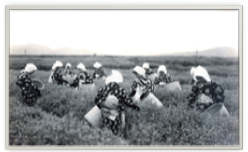
その後は緑茶の国内需要を中心に生産は順調に拡大します。挿し木繁殖による優良品種への転換、整せん枝技術による生育のそろいが進み、品質が向上するだけでなく摘採の機械化も急速に進みました。このように茶の品種化、栽培技術はわが国の茶業の近代化に大いに貢献しました。
3. 製茶の機械化
茶は明治時代までは手揉み製法により作られていましたが、茶の需要が増え、生産性の向上は緊急の課題となりました。1885(明治18)年、埼玉の高林謙三氏は製茶機械を発明(特許第2号、3号、4号)し、製茶の機械化がはじまりました。その後、揉捻機、中揉機、精揉機などが次々に開発され、20世紀初めには、これらの機械による一貫体系を導入する製茶工場も現れました。


4. 再び日本茶輸出へ
洗練された日本食と健康イメージにより、世界的に日本茶の需要が拡大しています。2001年からの20年間で輸出額はおよそ20倍に増加し、輸出茶の約7割が抹茶・粉末茶です。 日本茶の輸出には高い品質だけでなく、輸出相手国の検疫基準などをクリアする必要があります。
そこで、農研機構では、日本茶の輸出向けの病害虫防除体系を開発するとともに、品質・収量性に優れるとともに、病害抵抗性を有する新品種を育成しました。また、スマート農業を利用した大規模生産体系や有機茶栽培に関する研究も進めており、今後の安心・安全な日本茶の持続的安定生産と海外輸出の更なる拡大に向けた研究開発を進めています。

抹茶としての品質に
優れる品種「せいめい」

ロボット摘採機

